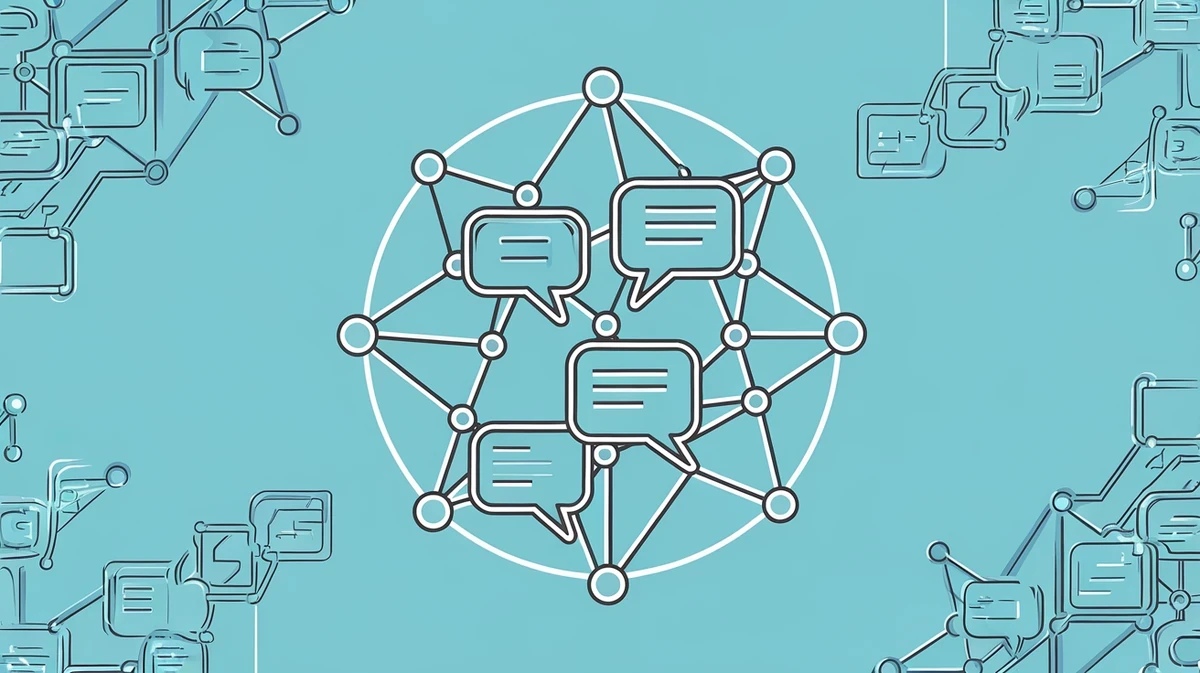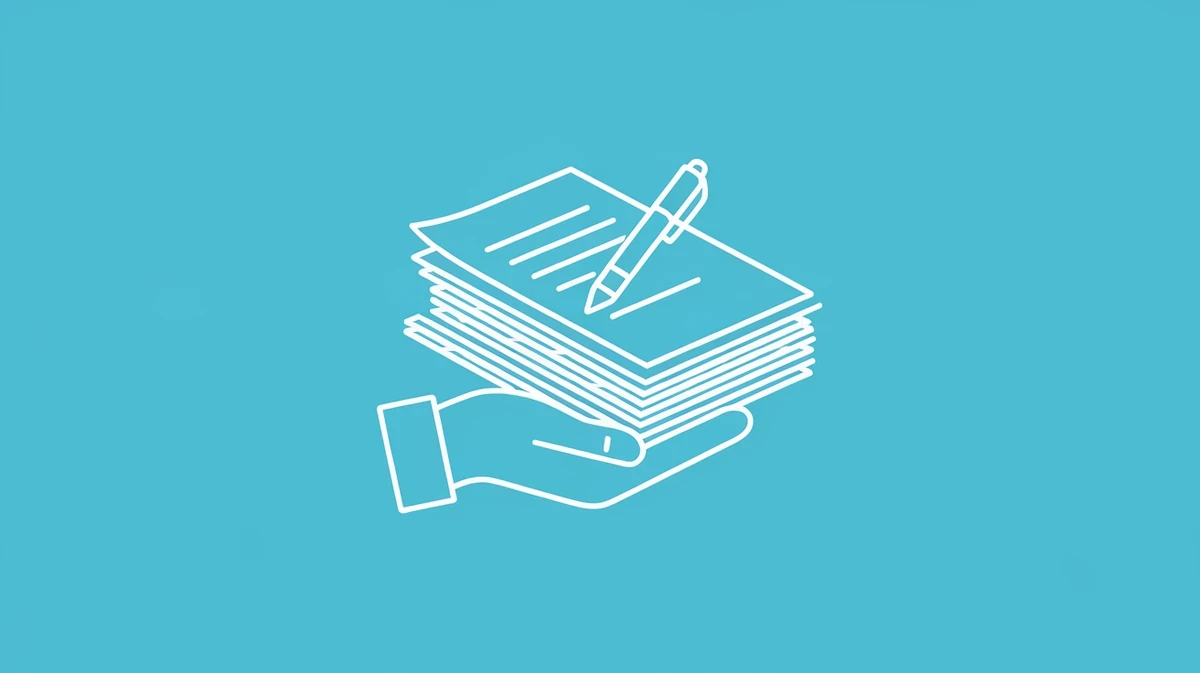件名:[大学名][氏名]:[OB・OG氏名]様へのOB訪問のお願い
[OB・OG氏名]様
いつも大変お世話になっております。
[大学名]の[学部名]に在籍しております、[氏名]と申します。
この度は、貴社でご活躍されている[OB・OG氏名]様の[役職・部署]でのご経験について、ぜひお話を伺いたく、ご連絡させていただきました。
貴社の[事業内容]に大変興味があり、特に[具体的な興味のある分野]について深く知りたいと考えております。
[OB・OG氏名]様が[役職・部署]でご経験された[具体的な業務内容]について、お話を伺うことで、貴社でのキャリアを具体的にイメージしたいと考えております。
つきましては、大変恐縮ですが、下記の日程でご都合の良い日時をいくつかお教えいただけないでしょうか。
- [日付1] [時間帯1]
- [日付2] [時間帯2]
- [日付3] [時間帯3]
もし、上記日程でご都合がつかない場合は、別途ご相談させていただければ幸いです。
お忙しいところ大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
就活生の皆さん、こんにちは。
いよいよ就職活動が本格化してきましたね。
企業研究や自己分析と並行して、OB・OG訪問を検討している方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、OB・OG訪問を成功させるための第一歩、依頼メールの書き方について徹底解説しちゃいます。
この記事を読めば、人事担当者やOB・OGの心に響くメールが書けるようになるはず。
メールの基本構成から、アポ取りのコツ、さらに送る上での注意点まで、例文付きで詳しくご紹介します。
この記事を読めば、あなたの就活が有利に進むこと間違いなし。
まずは、メールの基本構成と重要ポイントから見ていきましょう。
OB訪問依頼メールの基本構成と重要ポイント

OB・OG訪問の依頼メールは、ただ用件を伝えるだけでなく、あなたの熱意や誠意を伝えるチャンスです。
丁寧で分かりやすいメールを作成して、OB・OG訪問を成功させましょう。
ここでは、メールの基本構成と、特に重要なポイントを解説していきます。
件名で差をつける:人事担当者の目を引く書き方
毎日たくさんのメールを受け取る人事担当者やOB・OGの目に留まるためには、件名がとっても重要です。
「OB訪問のお願い」のようなありきたりな件名では、他のメールに埋もれてしまう可能性も…。
そこで、件名には、大学名や氏名を加えて、誰からのメールか一目で分かるようにしましょう。
例えば、以下のような件名がおすすめです。
- 「〇〇大学の[氏名]と申します。OB訪問のお願い」
- 「〇〇大学[氏名]:[OB・OG氏名]様へのOB訪問のお願い」
- 「[OB・OG氏名]様にご相談させて頂きたい件:〇〇大学[氏名]」
件名を見ただけで「誰が」「何のために」メールを送ってきたのかが伝わるように工夫しましょう。
また、件名に大学名を入れることで、人事担当者も「どこの大学の学生だろう?」と興味を持ってくれるかもしれません。
宛名の書き方:失礼のない丁寧な表現
宛名は、メールを送る相手への敬意を示す大切な部分です。
宛名を間違えたり、略称を使ったりすることは失礼にあたりますので、十分に注意しましょう。
まず、企業の人事担当者宛に送る場合は、以下のように書くのが基本です。
株式会社[企業名]
人事部 [部署名]
[担当者氏名]様
OB・OG個人に送る場合は、以下のように書きます。
[OB・OG氏名]様
氏名の後に「様」をつけることを忘れないようにしましょう。
もし、部署名や担当者名が分からない場合は、「株式会社[企業名] 人事部 御担当者様」と記載しても問題ありません。
相手への敬意を払い、丁寧な宛名で、OB・OG訪問の第一歩を踏み出しましょう。
OB・OG訪問依頼メールの例文と書き方

OB・OG訪問を成功させるためには、丁寧で分かりやすいメールを作成することが重要です。
このセクションでは、具体的な例文を交えながら、メールの各要素の書き方を解説していきます。
メール本文の構成:必須項目をチェック
OB・OG訪問の依頼メールには、いくつかの必須項目があります。
これらの項目をきちんと含めることで、相手に失礼なく、スムーズにアポイントメントを取り付けることができます。
必須項目は、以下の通りです。
- 宛名
- 自己紹介
- OB・OG訪問の目的
- アポイントメントの希望
- 結びの挨拶
これらの項目を順番に記載することで、読みやすく、丁寧な印象を与えるメールを作成できます。
自己紹介:簡潔かつ熱意を伝える
メールの冒頭では、まず自己紹介をします。
大学名、学部名、氏名といった基本情報に加え、なぜOB・OG訪問を希望したのかを簡潔に伝えましょう。
長文にならないよう、3~4行程度でまとめるのがおすすめです。
熱意を伝えることも大切ですが、あくまでも簡潔に、丁寧な言葉遣いを心がけてください。
例文1:自己紹介の例
件名:OB・OG訪問のお願い [大学名] [氏名]
[OB・OG名]様
初めまして。[大学名]の[学部名]に在籍しております、[氏名]と申します。
貴社でご活躍されている[OB・OG名]様の[役職・部署]でのご経験について、ぜひお話を伺いたく、ご連絡させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。
この例文では、大学名、学部名、氏名を明記し、OB・OG訪問を希望する理由を簡潔に述べています。
OB・OG訪問の目的:明確に伝える
次に、OB・OG訪問の目的を具体的に伝えましょう。
「なぜその企業で働きたいのか」「なぜそのOB・OGに話を聞きたいのか」を明確にすることで、相手に訪問の意義を理解してもらうことができます。
企業の事業内容や、OB・OGの業務内容に対する興味を具体的に記述しましょう。
抽象的な表現は避け、具体的な内容を心がけることが大切です。
例文2:訪問目的の例
件名:OB・OG訪問のお願い [大学名] [氏名]
[OB・OG名]様
貴社の[事業内容]に大変興味があり、特に[具体的な興味のある分野]について深く知りたいと考えております。
[OB・OG名]様が[役職・部署]でご経験された[具体的な業務内容]について、お話を伺うことで、貴社でのキャリアを具体的にイメージしたいと考えております。
何卒よろしくお願いいたします。
この例文では、企業の事業内容と具体的な興味のある分野を述べ、OB・OGの業務内容に焦点を当てて訪問目的を説明しています。
アポイントメント希望:日程候補を提示
最後に、OB・OG訪問の希望日程を提示します。
相手の都合を考慮し、複数の候補日を提示するようにしましょう。
具体的な日付と時間帯を複数提示することで、相手が調整しやすくなり、スムーズにアポイントメントが成立する可能性が高まります。
例文3:アポイントメント希望の例
件名:OB・OG訪問のお願い [大学名] [氏名]
[OB・OG名]様
つきましては、大変恐縮ですが、下記の日程でご都合の良い日時をいくつかお教えいただけないでしょうか。
1.[日付1] [時間帯1]
2.[日付2] [時間帯2]
3.[日付3] [時間帯3]
もし、上記日程でご都合がつかない場合は、別途ご相談させていただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
この例文では、複数の日程候補を提示し、都合がつかない場合の対応についても言及しています。
OB訪問依頼メールを送る上での注意点

誤字脱字のチェック:社会人としての基本
OB訪問の依頼メールは、社会人として初めてビジネスの場に足を踏み入れるための、重要なステップです。
ここで、誤字脱字が多いと「基本的なことができていない」という印象を与えかねません。
送る前に必ず見直し、Wordやテキストエディタなどのツールを使ってチェックしましょう。
第三者に読んでもらうのも効果的です。
返信期限の設定:相手への配慮を忘れずに
OB訪問を依頼する際、返信期限を設けることは、相手への配慮を示す上で非常に重要です。
期限を設けないと、相手はいつ返信すれば良いのか分からず、対応が後回しになる可能性があります。
具体的な期日を明記し、「〇月〇日までにご返信いただけると幸いです」のように、相手に負担をかけない形で伝えましょう。
返信が来ない場合:再送メールの書き方
期日までに返信が来ない場合は、まず迷惑メールフォルダを確認しましょう。
それでも返信がない場合は、再度メールを送信します。
再送する際は、件名に「再送」と明記し、以前のメールを送った日付を記載します。
決して催促するような文面ではなく、相手への配慮を忘れずに「お忙しいところ恐縮ですが」といった言葉を添えましょう。
例文:返信を促す再送メール
件名:【再送】OB訪問のお願い[大学名][氏名]
[OB・OG名]様
先日は、OB訪問のお願いメールをお送りしましたが、
ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、
ご返信いただけていないため、再度ご連絡させていただきました。
もし、メールが届いていない場合や、
ご確認が難しい状況でしたら、ご容赦ください。
改めて、[簡単な自己紹介]と申します。[大学名]に在籍しており、
[OB・OG名]様のご経験をお伺いしたく、ご連絡いたしました。
もしご都合がよろしければ、
[希望日程]のいずれかで30分ほどお時間をいただけないでしょうか。
お忙しいところ大変恐縮ですが、
ご検討いただけますと幸いです。
[大学名] [氏名]
この例文は、返信がなかった場合に、再送メールを送る際の文面例です。
件名に【再送】と明記し、以前のメールを送った日付を記載することで、相手に状況を伝えやすくしています。
また、相手への配慮を忘れずに、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
OB訪問メールでアポを成功させるためのコツ

メールを送るタイミング:適切な時間帯を選ぶ
OB訪問のメールを送るタイミングは、相手への配慮を示す上で非常に重要です。
企業の人事担当者や社員は多忙なため、メールを送る時間帯によっては、見落とされたり、後回しにされたりする可能性があります。
一般的に、企業の始業直後や終業間際は避けるのが無難です。
お昼休憩の時間帯も、相手が休憩している可能性があるので避けるべきでしょう。
メールを送るのに最適な時間帯は、午前10時から11時頃、または午後2時から4時頃と言われています。
これらの時間帯は、比較的落ち着いてメールを確認できる可能性が高いです。
また、週明けの月曜日や週末の金曜日も避けるのが賢明です。
週初めは業務が立て込んでいることが多く、週末は休暇に入る人が多いため、メールを見落とされるリスクがあります。
火曜日から木曜日の間に、上記のような時間帯を意識してメールを送信することで、返信率を高めることができるでしょう。
OB・OGへの質問:事前に準備しておく
OB・OG訪問は、企業や業界理解を深める絶好の機会です。
しかし、貴重な時間を割いていただくため、質問は事前にしっかりと準備しておくことが重要です。
質問内容が曖昧だったり、企業のホームページを見れば分かるような内容だと、相手に「準備不足だ」という印象を与えてしまいます。
質問を準備する際には、まずOB・OG訪問の目的を改めて明確にしましょう。
自分が何を知りたいのか、どのような情報を得たいのかを具体的にすることで、質問内容も絞りやすくなります。
次に、企業の事業内容、業界の動向、OB・OGのキャリアパスなどについて、事前に調査しておきましょう。
その上で、さらに深掘りしたい点や、ホームページだけでは分からない疑問点を質問として準備します。
質問例としては、「入社を決めた理由は何ですか?」「仕事のやりがいや苦労は何ですか?」「学生時代にやっておいて良かったことは何ですか?」などがあります。
これらの質問を参考に、自分ならではの疑問をぶつけることで、より有益な情報を得られるでしょう。
ただし、質問ばかりではなく、OB・OGの話をしっかりと聞き、会話を楽しむことも大切です。
感謝の気持ちを伝える:お礼メールは必須
OB・OG訪問後には、必ずお礼メールを送ることが社会人としてのマナーです。
お礼メールは、訪問後できるだけ早く、遅くても当日中に送るようにしましょう。
メールを送るのが遅れると、相手に失礼な印象を与えてしまいます。
お礼メールには、訪問の時間を割いていただいたことへの感謝の気持ちを丁寧に述べることが大切です。
また、訪問を通じて得られた学びや、今後の就職活動への意欲などを具体的に書くことで、より誠意が伝わるでしょう。
お礼メールは、単なる形式的なものではなく、相手への感謝の気持ちを伝えるための大切なコミュニケーションツールです。
しっかりとしたお礼メールを送ることで、今後の関係性にもつながる可能性があります。
以下に、お礼メールの例文を記載します。
お礼メール例文
件名:OB訪問のお礼 [大学名] [氏名]
[OB・OG氏名]様
先日はお忙しい中、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。[大学名]の[氏名]です。
[OB・OG氏名]様のお話から、[企業名]での仕事のやりがいや、[業界名]の現状について深く理解することができました。
特に、[具体的な学びや気づき]についてのお話は、大変参考になりました。
今回の訪問で得た学びを活かし、今後の就職活動に邁進していきたいと考えております。
今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
[氏名]
[大学名]
[学部・学科名]
[連絡先]
『代筆さん』でOB訪問依頼メールも安心して作成
適切な敬語の使い方や相手に失礼のない文面構成が大切だとわかっていても、OB訪問依頼メールを一から丁寧に作成するには相応の時間と労力を要します。
就職活動を控えた学生の皆さんにとって、初めてのビジネスメール作成は特に難しく感じられるかもしれません。
件名の書き方から本文の構成、適切な敬語表現まで、気を付けるべき点は数多くあります。
そんなときに心強い味方となるのが、AI文章作成支援ツール『代筆さん』です。
『代筆さん』は、OB訪問依頼メールの作成でも威力を発揮します。「大学名」「訪問希望の理由」「興味のある分野」など、簡単な要点を入力するだけで、ビジネスマナーに沿った自然で丁寧なメール文を自動で提案してくれます。
敬語の使い分けや文体の調整も自動で行われるため、就活初心者の方でも安心してご利用いただけます。
さらに、相手や状況に応じた文体の変換も可能で、企業の人事担当者向けには格式高い表現を、同世代のOB・OG向けには親しみやすい表現を使い分けることも可能です。
社内規定や商品情報の登録機能を使って、あなたの大学情報や専攻分野、研究内容などを事前に登録しておけば、より個人に最適化されたメール文の作成も実現できます。
もちろん、AIが生成する文章は万能ではありませんので、最終的にはあなた自身の目で内容を確認し、必要に応じて調整することが大切です。
しかし、ゼロから文面を考える手間が省けることで、企業研究や面接対策など、本来注力すべき就職活動の準備に時間を割くことができるようになるでしょう。
『代筆さん』には無料プランも用意されており、初めての方でも気軽にお試しいただけます。
本格的に活用したい場合でも、比較的手頃な価格の有料プランが用意されているため、学生の皆さんにも無理なく導入していただけます。
OB訪問依頼メールの作成に不安を感じている就活生の皆さんは、ぜひ一度『代筆さん』の便利さを体験してみてはいかがでしょうか。
まとめ:OB・OG訪問依頼メールで就活を有利に進める

OB・OG訪問を実りあるものにするためには、心を動かす依頼メールを丁寧に届けることが何よりも重要です。
- 件名と宛名:人事担当者の目を引く件名で、失礼のない宛名を書く
- メール本文:自己紹介、訪問目的、アポ希望日を明確に記載する
- メール送信後の注意点:誤字脱字のチェックや返信期限の設定を徹底する
これらのポイントを踏まえ、まずは一通、心を込めた依頼メールを作成してみましょう。
完璧な文章でなくても、あなたの熱意が伝わるメールであれば、きっと良い結果につながるはずです。
もし、「言葉遣いや敬語に自信がない」「ビジネスメールの書き方に不安がある」と感じている方は、『代筆さん』の力を借りてみてはいかがでしょうか。
伝えたい内容を入力するだけで、失礼のない、丁寧なOB・OG訪問依頼メールを素早く作成できます。
就職活動は長く、大変な道のりですが、OB・OG訪問はあなたのキャリアを考える上で、非常に貴重な機会となります。
勇気を出して一歩踏み出すことで、新たな視野や気づきが得られるはずです。
あなたが自分らしい道を見つけられるよう、心から応援しています。
今すぐAIでメールを作成してみよう!
伝えたいことを入力するだけで、プロ級のビジネスメールが完成します