
勤怠入力の遅れを改善!催促メールで未入力を減らす3つのポイントと例文・注意点
 AIメール作成ツール 代筆さん
2025-06-11
AIメール作成ツール 代筆さん
2025-06-11
件名:【要対応】[対象期間]の勤怠入力のお願い
[従業員名]様
お世話になっております。
[会社名]、[部署名]の[担当者名]です。
[日付]現在の勤怠データを確認したところ、[従業員名]様の[対象期間]の勤怠入力が確認できておりません。
お忙しいところ大変恐縮ですが、[期日]までにご入力をお願いいたします。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
何卒よろしくお願いいたします。
日々の業務お疲れ様です。
今回は、みなさんの勤怠入力をスムーズにするための記事をお届けします。
「あれ?まだ勤怠入力してなかった。」なんて経験、ありますよね?
ついつい後回しにしてしまいがちな勤怠入力ですが、実は会社の運営にはとっても大切なんです。
未入力のまま放置してしまうと、給与計算に影響が出たり、労務管理が複雑になったり…。
そこで今回は、勤怠入力の遅れをなくすための「催促メール」に焦点を当てて、その基本から具体的な方法までを徹底解説します。
この記事を読めば、催促メールで未入力を減らし、みんなが気持ちよく働ける環境を作れますよ。
催促メールの基本と重要性、効果的な書き方、状況別の例文、注意点、そして遅延を防ぐための対策まで、ステップごとに解説していきます。
ぜひ最後までお付き合いください。
勤怠入力催促メールの基本と重要性

なぜ勤怠入力の催促が必要なのか
勤怠入力の催促が必要な理由は、大きく分けて2つあります。
1つ目は、正確な給与計算のためです。
従業員の労働時間や休暇日数を正しく把握することで、給与の過不足を防ぎ、トラブルを未然に防ぐことができます。
もし勤怠入力が遅れたり、間違っていたりすると、給与計算が正確に行われず、従業員の不信感につながる可能性も。
2つ目は、労務管理の適正化のためです。
従業員の労働時間を把握することで、過重労働の防止や、適切な人員配置が可能になります。
また、労働基準法を遵守するためにも、正確な勤怠データは不可欠です。
勤怠入力の遅れは、これらの労務管理を困難にし、企業のコンプライアンスリスクを高めることにもつながります。
これらの理由から、勤怠入力の催促は、従業員にとっても会社にとっても非常に重要な業務と言えるでしょう。
催促メールを送る前に確認すべきこと
催促メールを送る前に、いくつか確認しておきたいことがあります。
まず、勤怠入力の締め切り日を再確認しましょう。
従業員が締め切り日を勘違いしている可能性もあります。
また、勤怠入力の方法やシステムについて、従業員が正しく理解しているかどうかも確認が必要です。
もしシステムが使いにくい場合は、入力方法を再周知したり、システム自体を改善する必要があるかもしれません。
さらに、過去の未入力状況を確認し、特定の従業員に未入力が集中している場合は、個別に対応を検討する必要があります。
これらの事前確認をしっかり行うことで、より効果的な催促メールを作成することができます。
効果的な催促メールを書くための3つのポイント

効果的な催促メールは、従業員に不快感を与えることなく、迅速な勤怠入力を促すための重要なツールです。
ここでは、催促メールを作成する際に特に注意すべき3つのポイントを解説します。
これらのポイントを押さえることで、よりスムーズな勤怠管理が実現できるでしょう。
1. 件名で用件を明確に伝える
まず、メールの件名で用件を明確に伝えることが重要です。
これにより、受信者はメールの内容をすぐに理解し、対応の優先度を判断できます。
件名が曖昧だと、メールが見過ごされたり、後回しにされたりする可能性が高まります。
例えば「【要対応】勤怠入力のお願い」のように、具体的なキーワードと緊急度を示す表現を使いましょう。
2. 丁寧で具体的な文面にする
メール本文は、丁寧で具体的な文面を心がけましょう。
高圧的な表現や抽象的な言葉は避け、相手に不快感を与えないように配慮が必要です。
未入力の期間や、入力が必要な具体的な内容を明記することで、従業員はスムーズに対応できます。
例えば、「[対象期間]の勤怠入力が確認できておりません。お手数ですが、ご確認をお願いいたします」のように、具体的な情報を伝えましょう。
3. 期日と対応を明記する
最後に、いつまでにどのような対応が必要かを明確に示すことが大切です。
期限を設けることで、従業員は「いつまでに行動すれば良いか」を把握でき、対応漏れを防げます。
また、対応方法についても具体的に指示することで、従業員が迷うことなく行動できます。
例えば「[期日]までにご入力をお願いいたします。入力方法については[URL]をご確認ください」のように、期日と対応方法を具体的に示しましょう。
状況別 勤怠入力催促メール例文集

ここでは、勤怠入力の遅れに対して、状況に応じた催促メールの例文を紹介します。
未入力者への初回連絡、未入力が続く従業員への対応、部署全体へのリマインドと、3つのケースを想定しました。
それぞれの状況に合わせて、適切なメールを送りましょう。
未入力者への初回催促メール
まずは、勤怠入力が初めて遅れている従業員への、丁寧な催促メールです。
やむを得ない事情で遅れている可能性も考慮し、まずは穏やかに状況の確認を促しましょう。
入力忘れを防ぐため、入力期限やシステムについて改めて周知することも大切です。
例文 未入力者への初回催促メール
件名:【[会社名]】勤怠入力のお願い
[従業員名]様
いつも業務にご尽力いただき、ありがとうございます。
さて、[日付]現在の勤怠データを確認したところ、[従業員名]様の[対象期間]の勤怠入力が確認できておりません。
お忙しいところ大変恐縮ですが、[期日]までにご入力をお願いいたします。
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後とも、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
この例文では、件名で用件を明確にし、丁寧な言葉遣いを心がけています。
具体的な期日を記載することで、従業員が対応しやすくなるでしょう。
また、問い合わせ先を明記することで、不安を解消できます。
未入力が続く従業員へのメール
次に、複数回にわたり勤怠入力が遅れている従業員への催促メールです。
初回よりも強く注意を促すとともに、状況によっては面談などの対応が必要になる場合があることを伝えましょう。
改善が見られない場合は、人事担当者などと連携し、より丁寧なコミュニケーションを心がけてください。
例文 未入力が続く従業員へのメール
件名:【[会社名]】勤怠入力のお願い(再通知)
[従業員名]様
いつも業務にご尽力いただき、ありがとうございます。
以前よりご案内しておりますが、[従業員名]様の[対象期間]の勤怠入力が、再度確認できておりません。
大変恐縮ですが、[期日]までにご入力をお願いいたします。
度重なるお願いとなり大変申し訳ございませんが、もし何かご事情がありましたら、遠慮なくお申し出ください。
このまま未入力が続く場合は、面談など、対応が必要となる場合があることをご了承ください。
今後とも、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
この例文では、再通知であることを明記し、具体的な期日を再度伝えています。
未入力が続く場合の対応についても触れており、より強いメッセージを伝えることができます。
ただし、高圧的な印象にならないよう、丁寧な言葉遣いを心がけてください。
部署全体へのリマインドメール
最後に、部署全体に向けて勤怠入力を促すリマインドメールです。
個別の催促メールと並行して、定期的に部署全体へ注意喚起することで、未入力を減らす効果が期待できます。
入力漏れがないように、再度入力期限やルールを周知しましょう。
例文 部署全体へのリマインドメール
件名:【[会社名]】勤怠入力のリマインド
[部署名]の皆様
いつも業務にご尽力いただき、ありがとうございます。
[対象期間]の勤怠入力について、改めてリマインドさせていただきます。
未入力の方がいらっしゃいましたら、[期日]までにご入力をお願いいたします。
勤怠システムの入力方法についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後とも、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
この例文では、部署全体へのリマインドであることを明記し、丁寧な言葉遣いを心がけています。
入力期限を再度周知することで、未入力を防ぐ効果が期待できます。
部署全体へのメールは、個別の催促メールと合わせて、定期的に送信することが望ましいです。
催促メールを送る際の注意点

勤怠入力の催促メールは、従業員にきちんと対応してもらうために重要です。
しかし、送り方を間違えると逆効果になることもあります。
ここでは、催促メールを送る際に注意すべき3つのポイントを解説します。
送信タイミングと頻度を考慮する
催促メールを送るタイミングは非常に大切です。
早すぎると「まだ時間があるのに」と思われてしまい、遅すぎると「もう締め切りが過ぎている」と混乱を招く可能性があります。
適切なタイミングは、まず、締め切りの1日前、または当日の午前中など、従業員が対応しやすい時間帯に送るのがおすすめです。
また、催促メールを送る頻度も重要です。
何度も送ると、従業員に不快感を与えてしまう可能性があります。
初回はリマインドとして、未入力者のみに送信し、それでも入力がない場合にのみ再度送るなど、段階的に対応しましょう。
目安として、初回、2回目、最終の3段階程度で対応するとよいでしょう。
感情的な表現は避ける
催促メールを作成する際は、感情的な表現は避けるようにしましょう。
「なぜ入力しないのか」「いい加減にしてほしい」といった表現は、相手に不快感を与え、反発を招く可能性があります。
あくまでも、冷静で丁寧な言葉遣いを心がけ、入力の遅れに対する注意喚起と、期日までの対応を促す内容に徹することが大切です。
例えば、「ご多忙中恐縮ですが」や「お手数をおかけしますが」などのクッション言葉を使うことで、柔らかい印象を与えることができます。
また、入力が遅れている状況を具体的に示し、「〇月〇日の勤怠入力が未入力です」と伝えることで、相手も状況を把握しやすくなります。
個別の状況に配慮する
従業員によって、勤怠入力が遅れる理由は様々です。
システムの使い方を理解していない、業務が立て込んでいて忘れていた、体調不良で対応が遅れているなど、様々なケースが考えられます。
そのため、催促メールを送る際は、個別の状況に配慮することが重要です。
例えば、システムの使い方に不慣れな従業員には、操作方法を丁寧に説明するなどのフォローを合わせて行うと良いでしょう。
また、体調不良などで対応が遅れている場合は、状況をヒアリングし、必要に応じて猶予を与えるなどの柔軟な対応も検討しましょう。
状況を考慮した上で、一人ひとりに寄り添った対応を心がけることで、従業員の理解と協力を得やすくなります。
勤怠入力の遅延を防ぐための対策
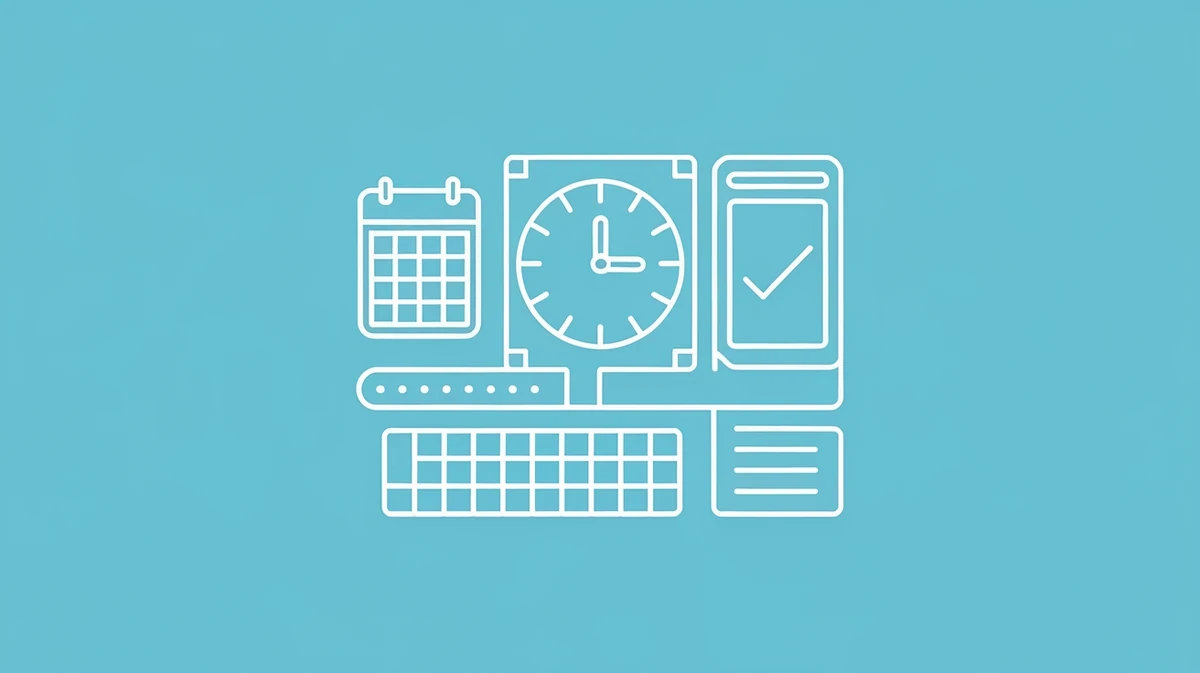
勤怠入力の遅延は、催促メールを送るだけでなく、根本的な対策を講じることで、より効果的に改善できます。
ここでは、勤怠入力の遅延を防ぐための具体的な対策を3つご紹介します。
定期的なリマインドの実施
まず、最も基本的な対策として、定期的なリマインドの実施が挙げられます。
単に「入力してください」と伝えるだけでなく、例えば、
- 週の初めに、その週の勤怠入力を促すリマインドメールを送る。
- 締め切り日の数日前に、未入力者に対して個別にリマインドメールを送る。
- 入力が完了した従業員にも、完了報告のリマインドメールを送る。(二重入力を防ぐ)
など、状況に応じたリマインドを行うことで、入力漏れを減らすことができます。
リマインドメールを送る際には、期日を明確に伝え、入力方法を再確認できるようなリンクを記載すると、より効果的です。
勤怠入力システムの改善
次に、勤怠入力システムの改善も重要な対策です。
もし、現在のシステムが使いづらいと感じている従業員が多いようであれば、システムの改善を検討する必要があります。
例えば、
- 入力項目が多すぎる場合は、必要最低限の項目に絞る。
- スマートフォンからの入力に対応させるなど、場所を選ばず入力できるようにする。
- 入力画面のデザインを改善し、直感的に操作できるようにする。
など、従業員がより簡単に、そしてストレスなく勤怠入力ができるよう、システムの改善を行うことが重要です。
また、システム変更を行う際には、従業員への事前説明や操作研修を実施することで、スムーズな移行を促すことができます。
従業員への周知徹底
最後に、勤怠入力の重要性や、期日を従業員に周知徹底することも、遅延を防ぐための重要な対策です。
具体的には、
- 勤怠入力のルールや締め切り日を、社内ポータルや掲示板などで定期的に周知する。
- 勤怠入力の重要性を説明する機会を設け、従業員の意識を高める。
- 勤怠入力に関するFAQを作成し、疑問点を解消できるようにする。
などが挙げられます。
周知徹底を行うことで、従業員の勤怠入力に対する意識が高まり、遅延を未然に防ぐことができます。
これらの対策を組み合わせることで、勤怠入力の遅延を効果的に減らし、よりスムーズな勤怠管理を実現できるでしょう。
『代筆さん』で催促メール作成もスムーズに
勤怠入力の重要性や、その遅れがもたらす影響について理解していても、相手に配慮しつつ、適切なタイミングと文面で催促メールを送るには、それなりの手間と時間がかかるものです。
一人ひとりの状況に配慮した丁寧な文章を用意するとなると、なおさら負担を感じてしまいますよね。
そんなときに頼れるのが、AIを活用したメール作成支援ツール『代筆さん』です。
『代筆さん』は、簡単なキーワード入力だけで、ビジネスマナーに沿った自然な文面を、AIが自動で生成してくれるWebサービスです。
「未入力者にだけ個別で送る」「全体へリマインドする」といった用途ごとに文調や言い回しを調整でき、場面に応じた最適なメール作成を効率的に行えます。
定型文の登録機能も充実しており、よく使う催促文を一括で呼び出すことも可能です。
さらに、社内ルールや業務内容に応じた文案をカスタマイズできるため、より実務に即したメール作成が実現します。
もちろん、AIが生成する文章は常に完ぺきとは限りませんが、ゼロから構成を考えるよりも格段に負担が軽減されるため、最終チェックや細かな修正に集中できます。
『代筆さん』には無料プランがあり、気軽に試せるのも大きな魅力です。
有料プランも比較的安価に提供されており、日々の業務を効率化したい方には特におすすめです。
まとめ 勤怠入力の催促メールで業務効率化を促進

ここまで、勤怠入力の催促メールについて、その重要性から具体的な作成方法、送る際の注意点、そして遅延を防ぐための対策まで、幅広く解説してきました。
これらの情報を踏まえ、最後に改めて重要なポイントを整理しましょう。
- 催促メールは、未入力者への迅速な対応を促し、正確な勤怠管理に不可欠である
- 効果的な催促メールは、明確な件名、丁寧な文面、期日の明記が重要となる
- システム改善や定期的なリマインドは、遅延防止のための有効な対策である
これらのポイントを踏まえ、日々の業務でぜひ実践してみてください。
もし、勤怠入力の遅れが頻繁に発生する場合は、まずは現状の勤怠管理システムを見直すことから始めてみましょう。
システムが複雑で使いにくい場合、従業員は入力を後回しにしてしまいがちです。
催促メールの文面づくりに悩むことが多いと感じている方は、『代筆さん』を活用してみてはいかがでしょうか。
未入力者への丁寧な個別連絡や、部署全体へのリマインド文も、目的に合わせたトーンで素早く作成できます。
業務負担を減らしつつ、伝わりやすい文章で勤怠管理の精度向上にもつながります。
よりシンプルで使いやすいシステムへの移行や、入力方法に関する研修の実施を検討してみましょう。
スムーズな勤怠管理を実現し、あなたがより働きやすい環境を築けるよう、心から応援しています。
今すぐAIでメールを作成してみよう!
伝えたいことを入力するだけで、プロ級のビジネスメールが完成します
