
感情的なクレーマーを冷静に説得する魔法のコミュニケーション術|もうクレーム対応は怖くない!
 AIメール作成ツール 代筆さん
2025-06-03
AIメール作成ツール 代筆さん
2025-06-03
お客様からの厳しいご意見、時には感情的なクレームに、どう対応したらいいか悩んでいませんか?
私も以前は、クレーム対応が本当に苦手で、電話が鳴るたびにドキドキしたり、お客様の強い言葉に心が折れそうになったり、胃が痛くなる毎日でした。
「どうして分かってもらえないんだろう」「これ以上どうすれば…」と途方に暮れることも一度や二度ではありませんでした。
しかし、いくつかのコミュニケーションのコツを掴むことで、驚くほど冷静に対応できるようになり、お客様にも納得していただけるようになったのです。
今回は、そんな私が実践してきた、感情的なお客様を冷静に説得するためのコミュニケーション術をお伝えします。
なぜお客様は感情的になってしまうの?その心理を理解しよう
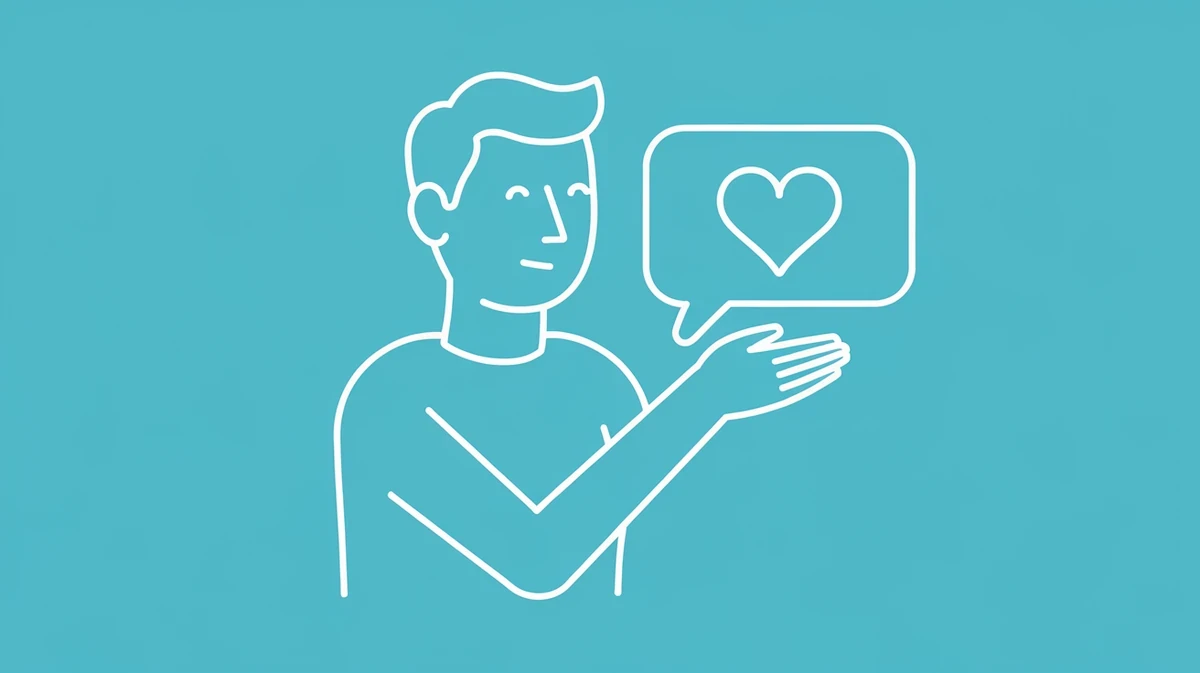
まず大切なのは、お客様がなぜ感情的になってしまうのか、その背景にある心理を理解しようと努めることです。
相手の気持ちが見えてくると、対応方法も自然と変わってきます。
期待外れが生んだ失望感
お客様は、商品やサービスに対して、何らかの期待を持っています。
その期待が裏切られたとき、大きな失望感を抱くのは当然のことです。
そして、「こんなはずじゃなかったのに」という気持ちが、怒りや不満として表に出てしまいます。
特に、事前に良い口コミを聞いていたり、高い料金を支払っていたりすると、そのギャップはさらに大きくなるでしょう。
不安や不満が怒りに変わる瞬間
はじめは小さな不満や、些細な疑問だったかもしれません。
しかし、それがうまく解消されなかったり、ぞんざいに扱われたと感じたりすると、不安が募り、やがて怒りへとエスカレートしてしまうことがあります。
「このまま放置されたらどうしよう」「誰も私の言うことを聞いてくれない」という気持ちが、強い言葉になってしまうと考えられます。
「ちゃんと聞いてほしい」という承認欲求
感情的になっているお客様の多くは、「自分の話をちゃんと聞いてほしい」「このつらい気持ちを分かってほしい」という強い承認欲求を抱えています。
問題解決そのものよりも、まずは自分の言い分を最後まで聞いて、共感してほしいと願っている場合も少なくありません。
無視されたり軽んじられたりしたと感じると、さらに声が大きくなってしまうものです。
日本特有の「おもてなし」への高い期待値
日本では、「お客様は神様」という言葉が一時期よく使われたように、サービスに対する期待値が非常に高い傾向があります。
丁寧な言葉遣いや、細やかな配慮を当然のこととして求める文化があるため、少しでも雑な対応だと感じると、敏感に反応してしまうことがあります。
この文化的背景も、クレームが感情的になりやすい一因と言えるでしょう。
クレーム対応の心構え|冷静さを保つための第一歩

お客様の心理を理解した上で、次に対応する側の私たちが持つべき心構えについてお話しします。
ここがブレてしまうと、相手のペースに巻き込まれてしまうので、しっかり押さえておきましょう。
まずはあなたの心を落ち着かせる深呼吸
お客様の怒りを目の前にすると、誰でも緊張したり、動揺したりするものです。
まずは、ゆっくり深呼吸をしましょう。
これだけでも少し心が落ち着き、客観的に状況を見られるようになります。
あわせて、「大丈夫、私ならできる」と心の中でつぶやくのも効果的です。
「攻撃されている」ではなく「困っている」と捉える
お客様の強い言葉は、あなた個人に向けられた攻撃ではありません。
お客様は、商品やサービス、あるいはその状況に対して「困っている」のです。
その「困りごと」を解決してほしい、というメッセージだと捉え方を変えてみましょう。
そうすると少し肩の力が抜けて、相手に寄り添う気持ちが生まれてくるはずです。
相手の感情を受け止める姿勢の重要性
たとえお客様の言い分に納得できない点があったとしても、まずは「そうお感じになったのですね」「不快な思いをさせてしまい申し訳ありません」と、相手の感情を一旦受け止めることが大切です。
ここで反論したり言い訳をしたりすると、火に油を注ぐことになりかねません。
まずは「あなたの気持ちを理解しようとしています」という姿勢を示すことが、信頼関係を築く第一歩です。
日本のビジネス文化における「傾聴」の価値
日本では、相手の話を丁寧に聞く「傾聴」の姿勢が非常に重視されます。
特にクレーム対応においては、お客様が話し終わるまで、じっくりと耳を傾けることが求められます。
途中で話を遮ったり、自分の意見を挟んだりするのは避けましょう。
相手に「しっかり聞いてもらえた」と感じてもらうことが、その後の説得をスムーズに進めるための鍵となります。
感情的な相手を冷静に導く具体的なコミュニケーション術

さて、ここからは具体的なコミュニケーション術の解説です。
ステップごとに分かりやすくご説明しますので、ぜひ実践してみてください。
ステップ1:徹底的に聞く「アクティブリスニング」
最初に行うべきは、とにかくお客様の話を「聞く」ことです。
ただ聞くだけでなく、積極的かつ能動的に聞く「アクティブリスニング」を心がけましょう。
相槌とうなずきで「聞いています」を伝える
「はい」「ええ」「さようでございますか」といった相槌や、適度なうなずきは、「あなたの話をしっかり聞いていますよ」というサインになります。
電話越しであれば、声のトーンで相槌を表現することも大切です。
ただし、あまりに頻繁すぎると逆効果になることもあるので、自然なタイミングを心がけましょう。
感情のオウム返しで共感を示す
お客様が「本当に腹が立ったんです!」と言われたら、「それはさぞお腹立ちだったこととお察しいたします」や「それほどまでにご不快なお気持ちになられたのですね」というように、相手の使った感情表現を繰り返すことで、共感の気持ちを伝えることができます。
「私の気持ちを分かってくれている」と感じてもらえると、お客様の興奮も少しずつ収まってくるでしょう。
事実確認は相手の話を遮らずに
話の途中で事実確認が必要な場合でも、できるだけ相手の話を遮らないようにしましょう。
一通り話し終えた後で、「恐れ入ります、いくつか確認させていただいてもよろしいでしょうか」と丁寧に切り出し、要点を整理しながら確認していくとスムーズです。
また、メモを取りながら聞くことも大切です。
ステップ2:共感と謝罪で心の壁を取り払う
お客様の話を十分に聞いたら、次は共感と謝罪のステップです。
ここでお客様の心の壁を取り払うことができれば、その後の話し合いが格段に進めやすくなります。
「お気持ちお察しします」は魔法の言葉
「さぞご不便をおかけしたことと存じます、お気持ちお察しいたします」
「ご期待に沿えず、大変申し訳ございませんでした。そのようにお感じになるのも無理はございません」
このように相手の感情に寄り添う言葉は、お客様の心を和らげる効果があります。
紋切り型ではなく、心からそう思っていることが伝わるように、言葉に感情を乗せることが大切です。
具体的な不快ポイントへの謝罪
何に対してお客様が不快な思いをされたのか、具体的なポイントが分かれば、それに対して明確に謝罪しましょう。
「〇〇の件につきまして、ご不快な念をおかけし、誠に申し訳ございません」というように、具体的に言及することで、謝罪の言葉がより真摯に伝わります。
ただし、全面的に非を認める必要はない
謝罪は大切ですが、事実関係が不明な段階で、全面的に会社の非を認めてしまうのは避けるべきです。
あくまで「ご不快な思いをさせたこと」「ご迷惑をおかけしたこと」に対して謝罪するというスタンスが重要です。
安易な約束や、できないことまで「やります」と言ってしまうのは、後々さらなるトラブルの元になりかねません。
ステップ3:問題解決に向けて具体的な提案をする
お客様の気持ちが少し落ち着いてきたら、いよいよ問題解決に向けて具体的な話し合いに入ります。
ここでは、建設的な提案を心がけましょう。
相手の要望を明確にする質問
「お客様としては、私どもにどのような対応をご希望でいらっしゃいますでしょうか」
「具体的に、どのような状態になればご満足いただけますでしょうか」
このように、お客様の真の要望を引き出すための質問を投げかけてみましょう。
感情的な言葉の裏に隠された、本当の望みが見えてくることがあります。
できないことは正直に、代替案を提示
お客様の要望が、会社の規定や物理的な制約からどうしても実現不可能な場合もあります。
そのような場合は、正直に「申し訳ございません、そのご要望にお応えすることは難しい状況でございます」と伝え、その理由も丁寧に説明しましょう。
そして、「代わりにこのような方法ではいかがでしょうか」と、必ず代替案を提示することが大切です。
選択肢を示すことで、お客様も検討の余地が生まれます。
解決策は複数提示し、相手に選んでもらう
可能であれば、解決策は一つだけでなく、いくつか選択肢を提示し、お客様自身に選んでいただく形を取ると良いでしょう。
「Aという方法とBという方法がございますが、どちらがよろしいでしょうか」というように、相手に選択の主導権を委ねることで、納得感が高まります。
自分で選んだという事実は、満足度にも繋がります。
ステップ4:感謝の言葉で締めくくる
問題解決の目処がついたら、最後は感謝の言葉で締めくくりましょう。
ご意見への感謝を伝える
「この度は、貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございました」
「お客様のお声が、今後のサービス改善に繋がります」
クレームは、企業にとって改善のヒントが詰まった宝物でもあります。
その機会を与えてくださったことへの感謝を伝えることで、お客様の気持ちも少しは報われるのではないでしょうか。
今後の改善を約束する
「いただきましたご意見は社内で共有し、再発防止に努めてまいります」
具体的な改善策まで言及できればベストですが、まずは改善に向けて努力する姿勢を示すことが大切です。
口先だけでなく、実際に行動に移すことが信頼回復には不可欠です。
ポジティブな印象で終わる工夫
最後に、「今後とも弊社サービスをご愛顧いただけますようお願い申し上げます」といった言葉を添えるなど、少しでもポジティブな印象で終われるように工夫しましょう。
クレームを乗り越えて、より良い関係を築ける可能性もあるため、最後まで丁寧な対応を心がけましょう。
説得を成功させるための言葉選びと非言語コミュニケーション

これまでのステップに加えて、説得をよりスムーズに進めるためには、言葉選びや声のトーン、態度といった非言語的なコミュニケーションも非常に重要です。
細やかな配慮が、お客様の心を開く鍵になります。
クッション言葉で柔らかい印象を
相手に何かをお願いしたり、反論したり、あるいは良くない知らせを伝えたりする際には、「クッション言葉」を上手に使いましょう。
これがあるだけで、言葉の印象がぐっと柔らかくなります。
- 「恐れ入りますが」
- 「申し訳ございませんが」
- 「お手数をおかけしますが」
- 「まことに恐縮ですが」
- 「差し支えなければ」
これらの言葉を会話の冒頭や途中に挟むことで、相手への配慮を示し、角が立つのを防ぐことができます。
ポジティブな言葉への言い換えテクニック
ネガティブな言葉は、相手に不快感を与えたり、反発を招いたりしやすいものです。
できるだけポジティブな言葉に言い換える工夫をしてみましょう。
- 「できません」 → 「いたしかねます」「難しい状況です」(理由を添えて)
- 「問題があります」 → 「改善すべき点がございます」「確認が必要な箇所がございます」
- 「それは違います」 → 「恐れ入りますが、私どもの認識では~となっております」
- 「待ってください」 → 「少々お待ちいただけますでしょうか」
こうした小さな心がけが、コミュニケーションを円滑にします。
落ち着いたトーンと話すスピード
感情的になっているお客様に対して、こちらも早口になったり声が大きくなったりしては逆効果です。
意識して普段よりも少しゆっくりと、落ち着いたトーンで話すように心がけましょう。
穏やかな話し方は、相手の興奮を鎮める効果があります。
深呼吸をして、自分のペースを保つことが大切です。
姿勢や表情も大切なメッセージ
対面での対応はもちろん、電話越しであっても、あなたの姿勢や表情は声のトーンを通じて相手に伝わるものです。
背筋を伸ばし、穏やかな表情を意識するだけでも、声に誠実さや落ち着きが乗ってきます。
「見えないから大丈夫」と思わず、相手に敬意を払う姿勢を忘れないようにしましょう。
それでも解決しない…長期化・悪質化した場合の対処法

ここまでお伝えした方法を試しても、残念ながら全ての問題が円満に解決するわけではありません。
中には、対応が長期化したり、理不尽な要求が続いたりするケースも出てくるかもしれません。
そういったケースに直面したときのために、いくつかの対処法を知っておくことも大切です。
一人で抱え込まない!上司や同僚に相談する勇気
クレーム対応は、精神的にも大きな負担がかかります。
「自分の力で何とかしなければ」と一人で抱え込んでしまうと、追い詰められてしまいます。
困った時や手に負えないと感じた時は、ためらわずに上司や経験豊富な同僚に相談しましょう。
客観的なアドバイスをもらえたり、対応を代わってもらえたりするかもしれません。
組織として対応することが重要です。
日本の職場では「報連相(報告・連絡・相談)」が基本ですが、特にクレーム対応ではこれが本当に大切です。
記録の重要性|いつ、誰が、何を、どうしたか
対応が長引く場合や、後で「言った・言わない」のトラブルになりそうな場合は、対応記録を詳細に残しておくことが非常に重要です。
- 発生した日時
- お客様のお名前
- クレームの内容
- クレームに対してどのように対応したか
- お客様はどのような反応を示したのか
といった内容を残しておきましょう。
その際、時系列で客観的な事実を記録することが重要です。
これは自分自身を守るためにも、組織として情報を共有するためにも不可欠です。
明確なデッドラインの設定と毅然とした態度
理不尽な要求が繰り返されたり、解決の糸口が見えないまま時間が過ぎていくような場合は、どこかで見切りをつける勇気も必要です。
「これ以上の対応はいたしかねます」「〇月〇日までにご返答いただけない場合は、この件は一旦終了とさせていただきます」というように、明確なデッドラインを示し、毅然とした態度で臨むことも時には求められます。
もちろん、これは最終手段であり、上司とよく相談した上で慎重に判断すべきですが、引き際を見極めることも重要です。
専門機関への相談も視野に
あまりにも悪質なクレーマーや、脅迫まがいの言動がある場合は、企業の法務部や弁護士、場合によっては警察といった専門機関に相談することも検討しましょう。
社員の安全と心身の健康を守ることは、企業の責任です。
一人で悩まず、適切な窓口に助けを求めることを忘れないでください。
クレーム対応後の心のケアと次に活かす振り返り

クレーム対応が無事に終わった後も、大切なことがあります。
それは、あなた自身の心のケアと、今回の経験を次に活かすための振り返りです。
自分を褒めてあげよう!ストレス発散法を見つける
クレーム対応は、非常にエネルギーを使うものです。
対応が終わったら、まずは「よく頑張ったね」と自分自身をたくさん褒めてあげてください。
そして、自分なりのストレス発散法を見つけて、心と体をリフレッシュさせましょう。
美味しいものを食べる、好きな音楽を聴く、運動する、友人と話すなど、何でも良いのです。
溜め込まないことが一番大切です。
対応内容を客観的に振り返る
少し落ち着いたら、今回のクレーム対応について客観的に振り返ってみましょう。
- お客様がなぜ感情的になったのか?
- 自分の対応で良かった点と、反対に改善すべき点はどこか?
感情的にならず、冷静に分析することで、次の対応に活かせる学びが見つかるはずです。
失敗から学ぶことはたくさんありますから、恐れずに向き合ってみましょう。
チームで共有し、組織全体の対応力を高める
個人の経験として留めておくだけでなく、可能であればチームや部署内でクレーム事例と対応策を共有しましょう。
「こんなケースがあった」「こんな対応が効果的だった」という情報を共有することで、組織全体のクレーム対応力を高めることができます。
特に日本では、業務の属人化が課題となることもあるので、ノウハウを共有することはとても重要です。
ここで役立つのが、文章作成サポート
クレーム対応後には、お客様への謝罪文やお礼状、社内向けの報告書など、文章を作成する機会も多いのではないでしょうか。
丁寧かつ正確な言葉遣いが求められるこれらの文書作成は、意外と時間がかかり、精神的な負担になることもあります。
特に、人手不足や長時間労働が問題となっている職場では、こうした事務作業の効率化は喫緊の課題です。
ここで、AIを活用したメール作成支援ツール『代筆さん』をご紹介します。
『代筆さん』は、簡単な指示や要件を伝えるだけで、AIがビジネスメールを作成してくれるWebサービスです。
例えば、お客様からのクレームメールの内容と、「謝罪の言葉を伝えたい」「〇〇という代替案を出したい」といった指示を入力するだけで、AIが状況に応じた丁寧な返信メールの案を作成してくれます。
相手に合わせた適切なトーンの文章を自動で作成してくれるので、言葉遣いに悩む時間も減らせるでしょう。
もちろん、AIが作成した文章をそのまま送るのではなく、最終的には自身の目で内容を確認し、適宜修正やニュアンスの調整を行う必要がありますが、ゼロから文章を考える手間は大きく省けます。
無料プランから試すことができますので、日々の業務の効率化に、ぜひ一度お試しください。
まとめ|クレーム対応は成長のチャンス!AIも活用して負担を軽減
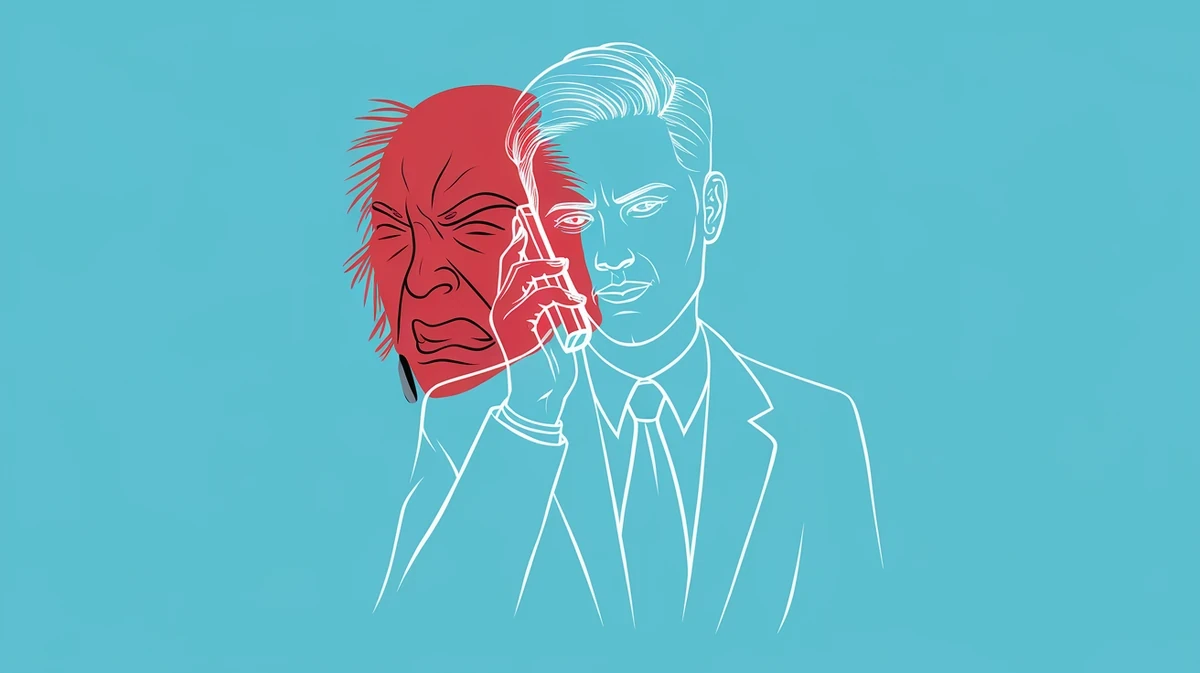
クレーム対応は確かに大変ですが、お客様の生の声に触れ、真摯に向き合うことで、あなた自身のコミュニケーション能力を高める絶好の機会にもなります。
何よりも大切なのは、お客様の感情に寄り添い、「お困りごとを解決したい」という誠実な気持ちで対応することではないでしょうか。
そして、クレーム対応後のフォローアップメールや報告書の作成など、丁寧さが求められる文章業務も発生します。
その際、『代筆さん』といったメール作成支援ツールを活用するのも良いでしょう。
クレーム対応後のお客様へのお詫びメールや、経緯をまとめた社内報告書など、正確かつ配慮の行き届いた文章を作成しなければならないシーンで、あなたの負担を大幅に軽減します。
クレーム対応のスキルを磨きつつ、便利なツールも活用して、あなたの負担が少しでも軽くなることを心から願っています。
今すぐAIでメールを作成してみよう!
伝えたいことを入力するだけで、プロ級のビジネスメールが完成します
