
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?その定義とクレームとの境界線を徹底解説
 AIメール作成ツール 代筆さん
2025-06-03
AIメール作成ツール 代筆さん
2025-06-03
顧客からの厳しい言葉に「これってカスハラ?」と悩んでいませんか?
私も以前、接客業でお客様の心無い言葉に傷ついた経験があります。
どこからが正当なクレームで、どこからが許されないハラスメントなのか、その境界線は曖昧に見えるかもしれませんね。
今回は、そんなあなたの悩みに寄り添い、カスタマーハラスメントの定義と、クレームとの違いを分かりやすく解説します。
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは何か?その定義を知ろう

近年よく耳にするようになった「カスタマーハラスメント」、略して「カスハラ」。
一体どのような行為を指すのか、まずはその定義をしっかり理解しましょう。
カスハラの基本的な定義
厚生労働省によると、カスタマーハラスメントは「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義されています。
少し難しい言葉ですが、要するに、お客様からの要求が、その内容や伝え方において、社会的に見て「やりすぎ」であり、それによって働く人の環境が悪くなるような行為を指します。
正当なクレームとの違いはどこにある?
お客様からのご意見やご指摘、いわゆる「クレーム」は、サービス改善につながる貴重な声でもあります。
しかしその表現方法や要求内容が度を超えると、カスハラになってしまう可能性があります。
大切なのは、その要求が「妥当」かどうか、そして要求を伝える「手段・態様」が「社会通念上相当」かどうかという点です。
この違いを理解することが、カスハラ問題への適切な対応を考える上での第一歩となります。
カスハラが問題視される背景
なぜ今、カスハラがこれほど問題視されているのでしょうか?
背景には、SNSの普及による個人の発信力の増大や、消費者意識の変化など、様々な要因が考えられます。
誰もが簡単に情報を発信できるようになったことで、企業や従業員へのプレッシャーが増しているのかもしれません。
また、日本の労働市場における人手不足も、従業員一人ひとりにかかる負担を増やし、カスハラの影響をより深刻にしています。
丁寧な対応を心がけていても、理不尽な要求に疲弊してしまうケースは少なくありません。
こうした状況が、社会全体でカスハラ対策の必要性を高めていると言えます。
これってカスハラ?具体的な事例と判断基準

定義だけではピンとこないかもしれませんね。
ここでは、どのような行為がカスハラに該当する可能性があるのか、具体的な事例を見ていきましょう。
あなたも似たような経験があるかもしれません。
暴言・侮辱・脅迫的な言動
「バカ」「使えない」「死ね」といった人格を否定するような暴言や侮辱は、言われた側の心を深く傷つける、許されない行為ですね。
また、「土下座しろ」「SNSで拡散してやる」「家に火をつけるぞ」といった脅迫的な言葉は、相手に恐怖を与え、精神的に追い詰めるものです。
これらは明らかに社会通念上許される範囲を超えており、カスハラに該当する可能性が高いです。
丁寧な言葉遣いが重視される日本のビジネス文化において、このような言動は特に受け入れがたいものです。
過剰または不合理な要求
商品やサービスの内容とは関係のない、過剰な金銭的要求や謝罪の要求。
例えば、「誠意を見せろ」と言って高額な金品を要求したり、何度も繰り返し謝罪を強要したりする行為です。
もちろん、企業側に非があれば謝罪は必要ですが、その要求が度を超えている場合は問題です。
また、実現不可能なサービス提供を執拗に求めたり、従業員に対して個人的な関係を要求したりするのも、カスハラと判断される場合があります。
こうした要求は従業員を困惑させ、業務の妨げになります。
長時間拘束や執拗なつきまとい
何度も電話をかけてきたり、店舗に長時間居座ったりして、業務を妨害する行為。
他の顧客への対応ができなくなったり、閉店時間を過ぎても帰らなかったりするのは、明らかに迷惑行為です。
担当者を指名して、何時間も説教を続けたり、個人的な連絡先を聞き出そうとしたりするケースも報告されています。
これは、従業員の精神的な負担になるだけでなく、プライバシーの侵害にもつながりかねません。
こうした行為は、従業員の精神的な負担になるだけでなく、他の顧客へのサービス提供にも支障をきたします。
テレワークが増える中でも、オンラインでの執拗な連絡なども問題になることがあります。
プライバシーの侵害や差別的な言動
従業員の容姿やプライベートについて執拗に詮索したり、侮辱したりする行為。
仕事とは全く関係のない個人的な情報を聞き出そうとしたり、外見をからかったりするのは、非常に不快ですよね。
性別、国籍、性的指向などに関する差別的な発言も、決して許されるものではありません。
「女だから」「外国人だから」といった決めつけや偏見に基づく発言は、人としての尊厳を傷つけます。
このような言動は、個人の尊厳を深く傷つけ、職場環境を著しく悪化させます。
クレームとカスハラの境界線を見極めるポイント

正当なクレームとカスハラの線引きは、時に難しいものです。
しかし、いくつかのポイントを押さえることで、冷静に判断しやすくなります。
焦らず、状況を客観的に見てみましょう。
要求内容の妥当性
まず、お客様の要求内容が、提供している商品やサービスに対して妥当なものかを確認しましょう。
商品の不具合に対する返品や交換、サービスの契約内容に関する問い合わせなどは、基本的に正当な要求と考えられます。
しかし、明らかに過剰であったり提供範囲を超えていたりする場合は、カスハラの可能性があります。
例えば、購入した商品の不具合に対する交換要求は正当なクレームですが、それに対して慰謝料として高額な金銭を要求するのは、妥当性を欠く可能性があります。
要求内容が、社会一般の常識から考えてかけ離れていないか、という視点が大切ですね。
要求を実現する手段・態様の相当性
要求内容が妥当であっても、その伝え方や手段が社会的に見て相当な範囲を超えている場合は、カスハラと判断されることがあります。
- 大声で怒鳴り散らす、机を叩く、物を投げつけるなどの威圧的な態度
- 暴力を振るう、または暴力を示唆するような脅迫
- 長時間にわたって電話をかけ続ける、執拗にメールを送り続けるなどの行為
これらは、明らかに不相当な手段と言えるでしょう。
特に日本のコミュニケーション文化では、相手への配慮や丁寧さが求められ、それを著しく逸脱する行為は問題視されます。
たとえ不満があったとしても、冷静に、適切な方法で伝えるべきです。
従業員の就業環境への影響
その言動によって、従業員が恐怖を感じたり、精神的に追い詰められたりして、安全に働ける環境が脅かされているかどうかも重要な判断基準です。
- 特定の従業員が集中的に攻撃されたり、その従業員が出勤できなくなったりする
- 職場全体が萎縮してしまい、他の従業員も恐怖を感じながら働いている
このような状況は、カスハラによる深刻な影響と言えます。
従業員が安心して、安全に働ける環境が守られているか、という視点も忘れてはいけません。
業務の属人化が進んでいる職場では、特定の担当者が標的になりやすい傾向もあるため、注意が必要です。
カスハラに遭遇してしまったら?従業員ができること
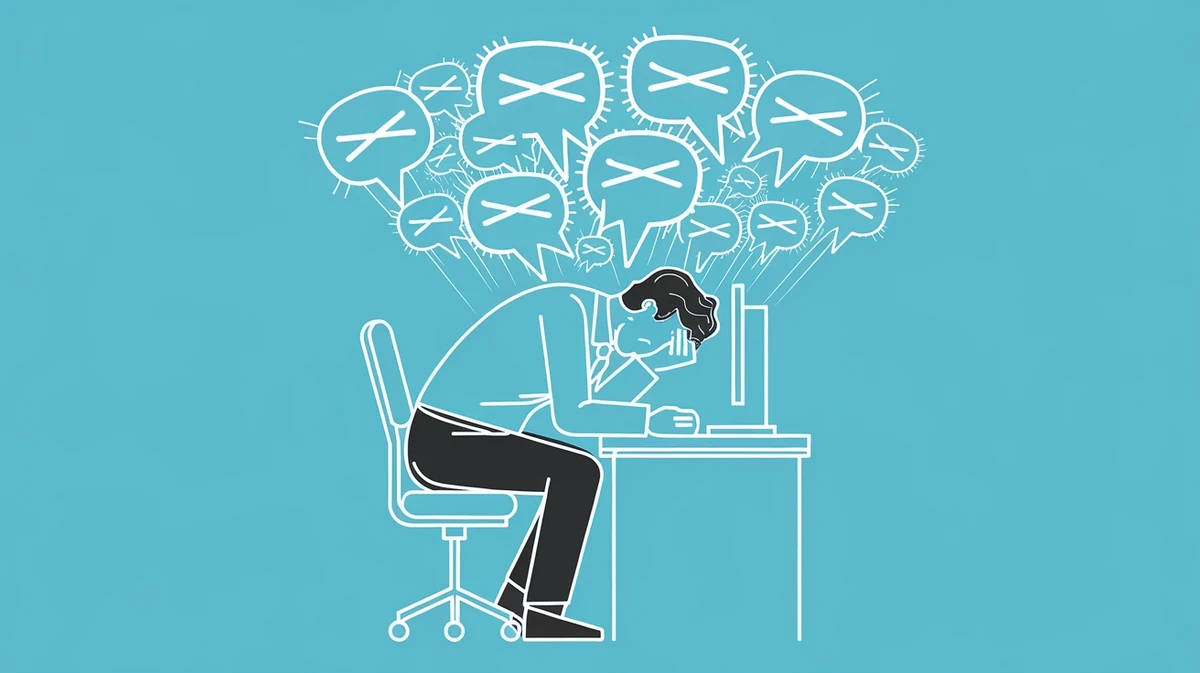
もし、あなたがカスハラに遭遇してしまったら、決して一人で抱え込まず、冷静に対応することが大切です。
どのように対応すれば良いのか具体的にご紹介しますので、万が一の時の心構えとして確認しておきましょう。
まずは落ち着いて対応する
相手が感情的になっている場合でも、こちらも感情的にならず、冷静に対応することを心がけましょう。
深呼吸をして、落ち着いて相手の話を聞く姿勢を見せることが大切です。
相手の話を一旦は傾聴する姿勢を見せつつも、無理な要求や理不尽な要求には毅然とした態度で「できません」「対応いたしかねます」と伝える勇気も必要です。
丁寧語を使いながらも、要求に応じられない理由をはっきりと、簡潔に説明することが大切です。
曖昧な返事をすると、相手に期待を持たせてしまい、問題を長引かせる可能性もあります。
一人で対応せず、上司や同僚に相談・報告する
カスハラかもしれないと感じたら、決して一人で抱え込まず、すぐに上司や同僚に相談・報告しましょう。
「こんなことで相談していいのかな?」とためらう必要はありません。
日本の職場文化では「報・連・相(報告・連絡・相談)」が重視されます。
状況を共有することで、組織として対応策を考えることができますし、何よりもあなたの精神的な負担を軽減できます。
可能であれば、複数人で対応するようにしましょう。
複数人で対応することで、客観的な判断もしやすくなりますし、万が一の場合の証言者にもなります。
記録を残す
いつ、どこで、誰から、どのような言動があったのか、具体的な内容を記録しておくことが非常に重要です。
- 日時、場所
- 相手の名前や特徴(わかれば)
- 具体的な言動(暴言、要求内容など、できるだけ詳細に)
- 対応内容(自分がどう対応したか)
- 周囲にいた人(目撃者)
などを、メモや日誌の形で残しておきましょう。
録音や録画が可能であれば、それらも有力な証拠となります。
ただし、無断での録音・録画はトラブルになる可能性もあるため、可能であれば相手に断ってから行うか、会社のルールに従ってください。
これらの記録は、後々会社として対応する際や、警察や弁護士に相談する際に、客観的な事実を示す重要な資料となります。
自分の心を守ることを最優先に
カスハラは、あなたの心身に大きなダメージを与える可能性があります。
決して「自分が悪いのかもしれない」「私の対応が悪かったからだ」などと思い詰める必要はありません。
あなたは何も悪くありません。悪いのは、ハラスメント行為そのものです。
つらいと感じたら、無理せず休憩を取ったり、その場を離れたりすることも考えましょう。
必要であれば上司に相談して、一時的に担当を代わってもらうなどの対応をお願いすることもできます。
もし、精神的なダメージが大きいと感じる場合は、社内の相談窓口や、産業医、カウンセラーなどの専門家に相談することも検討してください。
自分の心と体の健康を守ることが何よりも大切です。
企業が取るべきカスハラ対策とは?従業員を守るために

従業員をカスハラから守るためには、個人の努力だけでは限界があります。
企業側の積極的な対策が不可欠です。
安全で働きやすい環境を作ることは、企業の重要な責任でもあります。
カスハラに対する方針の明確化と周知徹底
企業として、どのような行為をカスハラと定義し、断固として許さないという姿勢を明確な方針として定め、全従業員に周知徹底することが重要です。
「お客様は神様」という考え方も大切ですが、従業員の人権を守ることも同じくらい大切です。
就業規則などにカスハラに関する規定を盛り込み、「当社はハラスメント行為には毅然と対応します」といったポスターを掲示するなど、社内外に方針を示すことも有効です。
これにより、従業員は「会社が守ってくれる」という安心感を持って対応できるようになり、カスハラ行為者に対しても、組織として毅然とした態度を示しやすくなります。
相談窓口の設置と対応体制の整備
従業員がカスハラ被害を気軽に、安心して相談できる窓口を設置し、その存在をしっかりと周知しましょう。
相談窓口は、人事部だけでなく、信頼できる上司や同僚、あるいは外部の専門機関など、複数の選択肢があるとより良いですね。
相談を受けた際の対応フロー(誰が、どのように対応するのか)を明確にし、迅速かつ適切に対応できる体制を整備することが求められます。
プライバシーに配慮し、相談したことによって不利益な扱いを受けないことを保証することも重要です。
人事部、法務部、現場の管理職、場合によっては外部の専門家などが連携して対応できる仕組み作りが理想的です。
日本の企業文化においては、内部で問題を解決しようとする傾向がありますが、時には外部の専門家の力も借りることも検討しましょう。
従業員への教育・研修の実施
カスハラの定義、具体的な事例、正しい対処法、相談窓口の利用方法などについて、従業員向けの教育や研修を定期的に実施しましょう。
知識として知っているだけでなく、いざという時に行動できるよう、ロールプレイングなどを取り入れることで、実践的な対応スキルを身につけることができます。
特に、管理職向けの研修では、部下から相談を受けた際の適切な対応方法(傾聴、共感、具体的な指示など)や、組織としての対応の重要性を深く理解してもらうことが大切です。
管理職が率先してカスハラ対策に取り組む姿勢を示すことが、職場全体の意識向上につながります。
警察や弁護士など外部機関との連携
悪質なカスハラ事案、例えば脅迫や暴力、業務妨害など、犯罪行為に該当する可能性がある場合は、ためらわずに速やかに警察に相談しましょう。
従業員の安全確保が最優先です。
また、損害賠償請求など、法的な対応が必要な場合に備えて、日頃から顧問弁護士など法律の専門家との連携体制を構築しておくことも重要です。
いざという時に迅速に相談できる相手がいることは、企業にとって大きな安心材料となります。
顧客対応の効率化による負担軽減
日々の顧客対応業務、特にメールでのやり取りは、丁寧さが求められる一方で、時間と精神的な労力がかかるものです。
クレーム対応はもちろん、定型的な問い合わせへの返信作業も、積み重なると大きな負担になり得ます。
対応が遅れたり画一的な返信が続いたりすると、それがお客様の不満を招き、新たなクレームや、場合によってはカスハラにつながる可能性もゼロではありません。
実は、こうしたメール対応の負担を軽減し、より質の高いコミュニケーションを実現する方法があります。
それは、AIの力を借りることです。
メール対応の効率化で、心にゆとりを

日々のメール対応、特にクレームへの返信などは、言葉遣いに細心の注意が必要で、精神的にも負担が大きいですよね。
「この表現で相手を怒らせないだろうか」「もっと丁寧な言い方はないか」と考え出すと、なかなか筆が進まないこともあります。
定型的な問い合わせへの返信に時間がかかったり、海外からの問い合わせに翻訳ツールを使いながら四苦八苦したりすることもあるかもしれません。
そんな悩みを解決するのが、『代筆さん』です。
『代筆さん』は、簡単な指示や要点を伝えるだけで、AIが状況に応じた丁寧なビジネスメールを作成してくれるWebサービスです。
例えば、お客様から厳しい内容のクレームメールを受け取った際に、そのメール内容と、あなたが伝えたい返信の要点(謝罪、状況説明、今後の対応など)を『代筆さん』に入力するだけで、相手への配慮が行き届いた、適切な敬語を使った返信文案をAIが作成してくれます。
これにより、文章作成にかかる時間と、「これで大丈夫だろうか」という精神的な負担を大幅に軽減できるはずです。
もちろん、AIが作成した文章は、必ずご自身で内容を確認し、必要に応じて修正を加えることが大切です。
しかし、ゼロから文章を構成する手間が省けるだけでも、大きな助けになるのではないでしょうか。
海外の顧客からの問い合わせにも、心配いりません。
日本語で「〇〇について問い合わせがあり、△△と回答したい」と指示を出すだけで、AIが相手の言語に合わせた自然なメールを作成してくれます。
言語の壁を気にせず、よりスムーズで迅速なコミュニケーションが可能になります。
さらに、よく使う返信パターンや、特定の状況で送るメールの指示などをテンプレートとして保存しておくことができます。
次回からは、保存した指示を選ぶだけで、さらに効率的にメールを作成できます。
これは、カスタマーサポート部門など、同じような問い合わせが多い場合に特に便利です。
メール対応にかかる時間を短縮できれば、その分、より複雑な問題への対応や、他の重要な業務、例えばサービス改善のための分析などに集中することができます。
時間に追われるストレスが減れば、心のゆとりも生まれます。
心のゆとりが生まれれば、お客様に対しても、より丁寧で、温かみのある、質の高い対応ができるようになるかもしれません。
人の手による温かみのある対応はもちろん大切です。
しかし、AIの力を賢く借りて効率化できる部分は効率化し、従業員の負担を減らすことも、これからの時代には必要不可欠と言えるでしょう。
まとめ:カスハラを正しく理解し、適切な対応を

カスハラは決して許される行為ではなく、働く人々の心身を傷つけ、健全な職場環境を脅かす深刻な問題です。
まず大切なのは、カスハラの定義を正しく理解し、どのような行為が該当するのかを知ることです。
そして、正当なクレームと、度を超えた要求や不当な言動との境界線を見極めるポイント(要求内容の妥当性、手段・態様の相当性、就業環境への影響)を意識することです。
もし、あなたがカスハラに遭遇してしまったら、決して一人で抱え込まず、冷静さを保ち、上司や同僚に相談し、必ず記録を残すことを忘れないでください。
あなたの心と体の安全を守ることが最優先です。
企業側も、従業員を守るために、カスハラに対する明確な方針を示し、相談しやすい体制を整え、教育・研修を実施し、外部機関との連携を図るなど、組織的な対策を講じることが強く求められます。
加えて、日々の顧客対応、特にメール作成の負担を軽減するために、『代筆さん』のようなAIツールを活用することも、従業員の負担軽減と業務効率化、ひいてはカスハラ発生の予防にもつながる有効な手段の一つです。
AIのサポートを得ながら、より効率的で質の高いコミュニケーションを目指しませんか?
カスハラのない、誰もが尊重され、安心して働ける社会を実現するために、私たち一人ひとりがこの問題を正しく理解し、適切な行動をとっていくことを心がけていきましょう。
今すぐAIでメールを作成してみよう!
伝えたいことを入力するだけで、プロ級のビジネスメールが完成します
