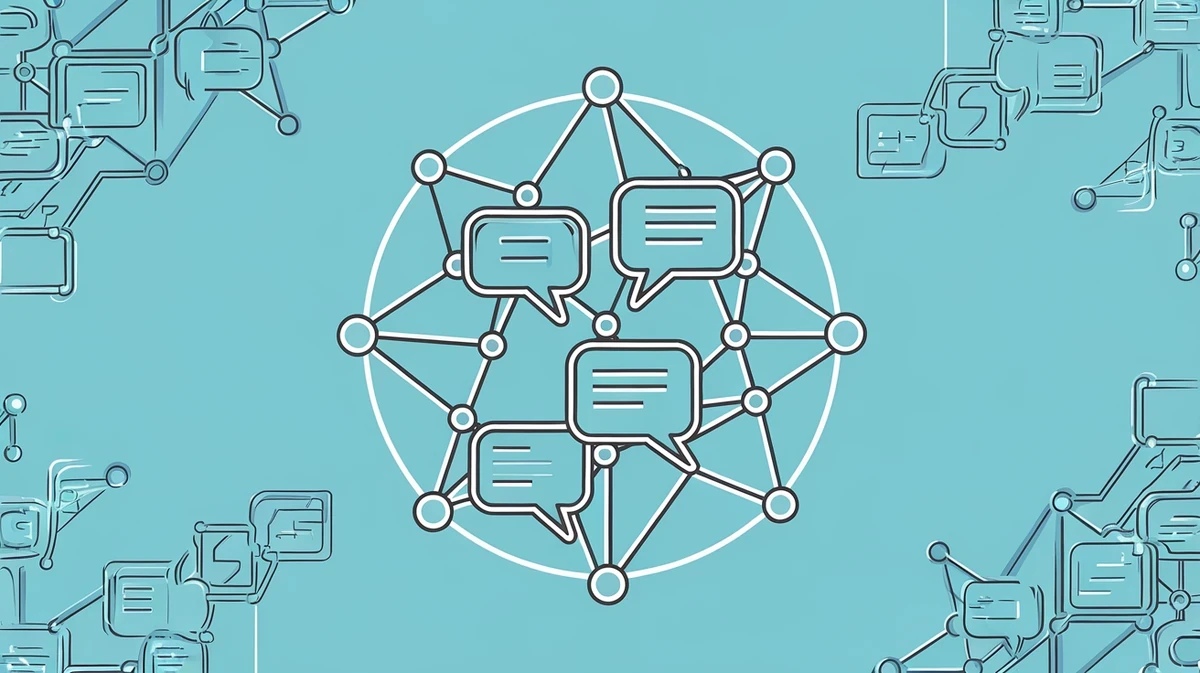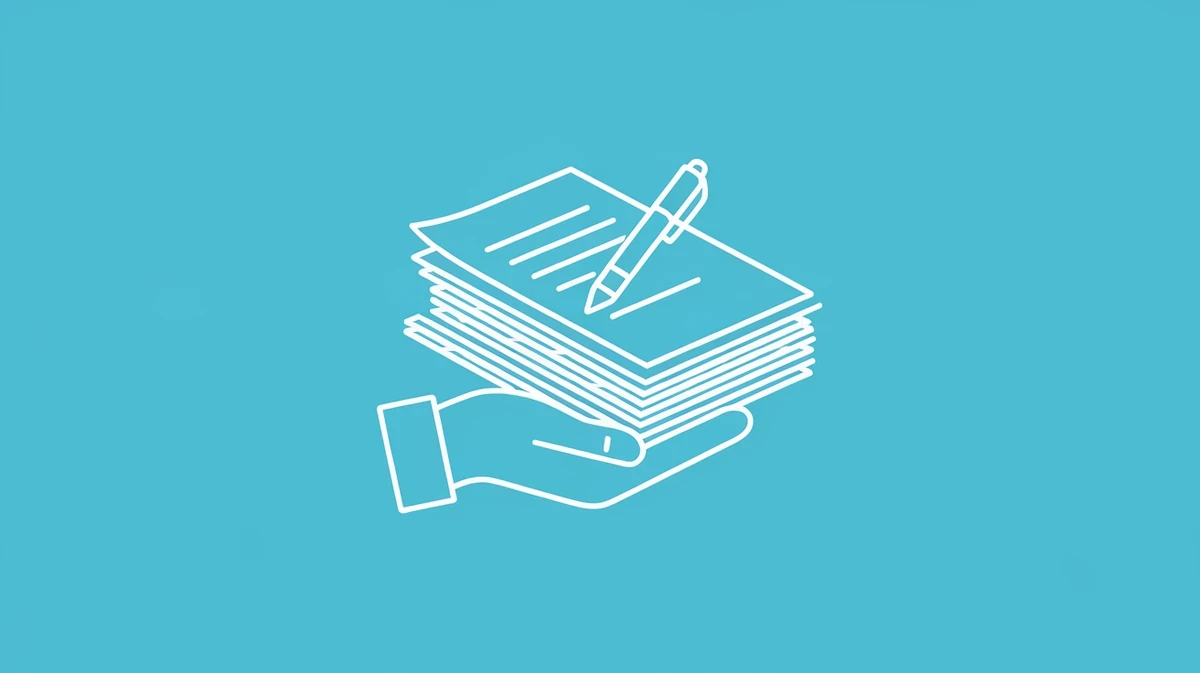件名:【[顧客名]様】[商品・サービス名]に関するクレームのエスカレーション
株式会社[会社名]
[上長の名前]様
お世話になっております。
[会社名]、[部署名]の[担当者名]です。
[顧客名]様より、[発生日時]に[商品・サービス名]に関するクレームのご連絡がありました。
内容としましては、[クレーム内容の要約]というものでございます。
私の方で、[試みた対応]を行いましたが、[現状]という状況でございます。
[顧客名]様は[顧客の様子]というご様子で、[エスカレーションに至った理由]のため、私では対応が困難と判断いたしました。
つきましては、今後の対応について、ご指示をいただきたく存じます。
お忙しいところ大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
クレーム対応、お疲れ様です。
顧客からのクレームは、対応を間違えると更なるトラブルに発展しかねない、本当に難しい問題ですよね。
特に、自分だけでは解決できないと判断し、上長や関連部署へエスカレーションする際には、正確かつ迅速な情報伝達が不可欠です。
今回は、そんな時に役立つ「クレームエスカレーション通知メール」の作成術を、基本構成から例文、注意点まで徹底解説します。
この記事を読めば、エスカレーションメールで何をどう書けば良いか迷うことなく、スムーズな連携でクレーム対応を進めることができるはずです。
まずは、エスカレーションメールの基本構成から見ていきましょう。
クレームエスカレーション通知メールの基本構成

クレームエスカレーションメールは、上長や関連部署に状況を正確に伝え、迅速な対応を促すための重要なツールです。
基本構成をしっかりと押さえ、スムーズな情報伝達を心がけましょう。
ここでは、件名、宛名、本文それぞれのポイントを詳しく解説していきます。
件名で内容を明確に伝えるポイント
エスカレーションメールの件名は、まず「何について」のメールなのかを明確に示すことが重要です。
担当者は日々多くのメールに対応しているので、件名を見ただけで内容を理解できるように工夫しましょう。
例えば、「〇〇様からのクレームに関するエスカレーション」のように、顧客名とクレーム内容を具体的に記載することで、受け取った側も迅速に対応を始めることができます。
また、「【重要】」や「【至急】」といった言葉を必要に応じて加えることで、メールの緊急度を伝えることも有効です。
件名を見ただけで、メールの重要度や緊急度が伝わるように工夫しましょう。
簡潔かつ具体的に記載することが大切です。
宛名の書き方と担当者への配慮
宛名を書く際は、まず誰に宛ててメールを送るのかを明確にする必要があります。
役職と氏名を正確に記載することはもちろん、担当者が複数いる場合は、全員の名前を記載しましょう。
特に、上長に送る場合は、敬称を忘れずに。
「〇〇部長」や「〇〇様」のように、丁寧な言葉遣いを心がけてください。
また、メールを受け取る担当者の立場や状況を考慮した配慮も大切です。
例えば、非常に忙しい担当者にメールを送る際は、件名に緊急度を明記するだけでなく、本文もできる限り簡潔にまとめるなどの配慮をしましょう。
相手への思いやりが、円滑なコミュニケーションにつながります。
本文で状況を正確に記述する方法
エスカレーションメールの本文では、クレームの状況を正確かつ具体的に記述することが重要です。
まず、顧客情報やクレーム内容を簡潔にまとめ、次に、発生日時や具体的な状況を詳細に記載します。
対応状況や現在の進捗も忘れずに伝えましょう。
また、エスカレーションに至った理由を明確にすることも大切です。
例えば「〇〇の理由により、私では対応が困難と判断いたしました」のように、具体的な理由を記述することで、上長や関連部署も状況を理解しやすくなります。
事実を基に、客観的に状況を伝えましょう。
上長報告に最適なエスカレーションメール例文集

ここでは、上長への報告に役立つエスカレーションメールの例文を、具体的な状況別に紹介します。
それぞれの例文は、緊急度が高い場合、技術的な問題が絡む場合、顧客の感情的な不満が強い場合を想定しています。
これらの例文を参考に、状況に応じた適切なエスカレーションメールを作成してください。
緊急度の高いクレームを報告する例文
緊急度の高いクレームは、迅速な対応が求められます。
顧客の不満が大きく、放置すると企業イメージを損なう可能性があるため、速やかに上長に報告し、指示を仰ぎましょう。
緊急クレーム報告の例文
件名:【緊急】[顧客名]様からのクレームに関するご報告
[上長名]様
いつもお世話になっております。[担当者名]です。
先ほど、[顧客名]様より[商品・サービス名]に関する重大なクレームがございました。内容は[クレーム内容の要約]です。
[顧客名]様は大変ご立腹されており、早急な対応を求めていらっしゃいます。
至急、[対応案]の対応が必要と考えられます。つきましては、今後の対応についてご指示をいただきたく、ご相談させていただけないでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
この例文は、件名に「緊急」と明記することで、メールの重要度を伝えています。
また、クレーム内容の要約を記載し、上長が状況を把握しやすいように配慮しました。
具体的な対応案を提示することで、スムーズな意思決定を促します。
技術的な問題を伴うクレームを報告する例文
技術的な問題が原因のクレームは、専門知識が必要となる場合があります。
そのため、技術部門との連携が不可欠です。
上長への報告と同時に、関連部署への情報共有も忘れずに行いましょう。
技術クレーム報告の例文
件名:[顧客名]様からの技術的なクレームに関するご報告
[上長名]様
いつもお世話になっております。[担当者名]です。
[顧客名]様より、[商品・サービス名]の[具体的な問題点]に関する技術的なクレームがございました。
こちらで[試した対応策]を試みましたが、改善が見られませんでした。
つきましては、技術部門の協力を得て、早急な原因究明と対応が必要と考えられます。今後の対応について、ご指示をいただきたく存じます。
お忙しいところ大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
この例文では、問題の具体的な内容と、既に行った対応策を明確に記述しています。
これにより、上長は問題の深刻度を判断しやすくなります。
また、技術部門との連携が必要であることを示唆することで、スムーズな対応を促します。
顧客の感情的な不満が強い場合の例文
顧客が感情的に不満を抱えている場合は、丁寧な対応が求められます。
まずは顧客の感情を落ち着かせ、状況を正確に把握することが重要です。
上長には、状況の詳細を報告し、今後の対応について指示を仰ぎましょう。
感情的な不満クレーム報告の例文
件名:【要対応】[顧客名]様からの感情的なご不満に関するご報告
[上長名]様
いつもお世話になっております。[担当者名]です。
[顧客名]様より、[商品・サービス名]に関するご不満のお申し出がございました。
内容としては、[不満の具体的な内容]で、[顧客名]様は大変お怒りのご様子です。
私の方で、[試みた対応]を行いましたが、ご納得いただけていない状況です。
今後の対応として、[提案する対応策]を検討しておりますが、上長のご指示をいただきたくご報告いたしました。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
この例文では、顧客の感情的な状態を「大変お怒りのご様子」と明記し、緊急性を示唆しています。
また、既に行った対応と、今後の対応策を提案することで、上長の意思決定をサポートします。
クレームエスカレーションメール作成3つの注意点

1. 事実と意見を区別して記述する
クレームエスカレーションメールを作成する際、最も重要なことの一つは、事実と意見を明確に区別して記述することです。
事実とは、実際に起こった事柄や確認されたデータなど、客観的に証明できる情報のことです。
一方、意見とは、担当者の主観的な解釈や判断、推測に基づくものです。
これらを混同してしまうと、状況の把握が曖昧になり、適切な対応が遅れる可能性があります。
たとえば、「お客様が非常に怒っている」という表現は、感情的な意見です。
代わりに、
「お客様は〇〇について、〇〇と発言され、強い不満を示されている」
のように、具体的な言動を記述することで、事実に基づいた正確な状況を伝えられます。
また、クレームの内容を時系列に整理し、何がいつ起こったのかを明確にすることも重要です。
2. 感情的な表現は避け客観的に記述する
クレームエスカレーションメールでは、感情的な表現は避けるべきです。
担当者が個人的な感情を交えて記述してしまうと、読み手が客観的な判断を下すのが難しくなります。
また、感情的な言葉は、事態をさらに悪化させる可能性もあります。
クレーム対応は、冷静かつプロフェッショナルな態度で行うことが求められます。
「お客様が理不尽だ」というような主観的な表現は避け、
「お客様のご意見は〇〇であり、当社としては〇〇と判断しています」
のように、事実を基にした客観的な記述を心がけましょう。
また、たとえお客様の言動に不快感を覚えたとしても、その感情をメールに含めることは避けるべきです。
事実に基づいた正確な情報伝達を徹底することが、スムーズなエスカレーションにつながります。
3. 具体的な改善策や提案を含める
クレームエスカレーションメールは、単に問題を報告するだけでなく、解決に向けた具体的な提案や改善策を含めることが望ましいです。
担当者がこれまでの対応で考えたことや、現状を打開するためのアイデアを示すことで、上長や関連部署が迅速かつ適切な判断を下すための材料となります。
例えば、
「今回のクレームの原因は〇〇であると考えられます。再発防止のためには、〇〇の改善が必要ではないでしょうか」
といった具体的な提案は、問題解決への建設的なアプローチとなります。
また、過去の類似事例や関連情報を共有することも、対応策を検討する上で役立ちます。
可能な範囲で具体的な提案をすることで、エスカレーションをより効果的なものにすることができます。
エスカレーションをスムーズに行うための社内連携

関連部署への情報共有を徹底する
クレーム対応を円滑に進めるためには、関連部署との連携が不可欠です。
特に、エスカレーションが必要になった場合は、速やかに情報を共有し、協力体制を築くことが重要になります。
情報共有の遅れは、対応の遅延や顧客の不満を増大させる原因になりかねません。
具体的には、クレームの内容、顧客の状況、これまでの対応履歴などを関係部署に正確に伝えましょう。
また、情報共有の際には、共有範囲を明確にし、機密情報が適切に扱われるように注意する必要があります。
エスカレーション基準を明確にする
エスカレーションをスムーズに行うためには、どのような場合にエスカレーションが必要かを明確にする必要があります。
エスカレーションの基準があいまいだと、担当者が判断に迷い、対応が遅れてしまう可能性があります。
例えば、
- 「顧客の感情が激高している場合」
- 「技術的な問題が複雑で担当者レベルでは解決できない場合」
- 「過去に同様のクレームが発生している場合」
など、具体的な基準を定めましょう。
これらの基準を社内で共有し、担当者全員が同じ認識を持つことで、スムーズなエスカレーションが可能になります。
定期的な情報共有で連携を強化する
クレーム対応に関する情報を定期的に共有することで、部署間の連携を強化できます。
例えば、過去のクレーム事例や対応策、改善事例などを共有する場を設けると良いでしょう。
これにより、各担当者が様々なケースに対応できるようになり、エスカレーションが必要になった際にも、よりスムーズに連携が取れるようになります。
また、情報共有の場では、お互いの課題や困っていることを共有し、改善策を検討することも重要です。
部署間のコミュニケーションを活発化させることで、組織全体のクレーム対応能力が向上します。
『代筆さん』の活用でエスカレーションを効率化
クレーム対応において、エスカレーションメールは正確かつ迅速に情報を伝えるために非常に重要な役割を担っています。
どんなに内容の整理や表現を工夫しても、的確なメールを作成するには、それなりの時間と労力がかかります。
特に、状況を客観的に伝えつつ、事実と意見を区別し、上長や関連部署に適切に状況を報告することは簡単ではありません。
そんなときに便利なのが、AI文章作成支援ツール『代筆さん』です。
『代筆さん』はシンプルな指示を入力するだけで、ビジネスマナーに沿った自然な文章を、AIが瞬時に生成してくれる便利なWebサービスです。
クレーム対応のエスカレーションメール作成でも、事実の正確な伝達や丁寧な敬語表現、必要な情報の整理が苦手な方でも手軽に質の高いメールが作成できます。
例えば、「顧客からのクレーム内容を具体的にまとめたい」「感情的になっている顧客の状況を冷静に報告したい」といった目的を伝えれば、それに応じた文面を提案してくれます。
加えて、社内の規定や商品の詳細情報を登録すれば、より自社に合わせた文章のカスタマイズも可能です。
また、よく使う文章は定型文として登録できるため、同様のクレーム対応が発生した際もワンクリックで呼び出せ、作成時間を大幅に短縮できます。
もちろん、AIが作成する文章は完璧ではないため、最終的にはご自身で内容を確認し、必要に応じて修正を行うことが大切です。
それでも、ゼロから文章を考える負担が軽減されることで、クレームの本質的な対応や解決策の検討に集中できる環境が整うでしょう。
『代筆さん』は無料プランから利用を始められ、有料プランも比較的リーズナブルに用意されています。
クレーム対応で迅速かつ正確なエスカレーションメールの作成にお悩みの方は、一度試してみてはいかがでしょうか。
まとめ:効果的なエスカレーションでクレーム対応を強化するために

エスカレーションメールは、クレーム対応の要となる重要なコミュニケーション手段です。
- 件名で内容を明確に伝える
- 状況を正確に記述する
- 「事実」と「意見」を区別する
これらのポイントを意識することで、上長や関連部署への情報伝達がスムーズになり、より迅速かつ適切な対応へと繋がります。
もし、あなたがエスカレーションメールの作成にまだ不安を感じているなら、まずは自社の状況に合わせたテンプレートを作成してみましょう。
テンプレートを準備しておくことで、いざという時にも焦らずに対応できますよ。
また、クレーム対応の中でエスカレーションメールの作成に時間がかかってしまい悩んでいるという方は、『代筆さん』の活用をおすすめします。
忙しい状況でも、必要な情報を漏らさず丁寧に伝える文章が短時間で手に入るため、業務の効率化につながるでしょう。
迅速な対応だけでなく、正確でわかりやすい情報共有がクレーム解決の鍵となります。
日頃からコミュニケーションの質を意識し、チーム全体の連携を強化していきましょう。
今すぐAIでメールを作成してみよう!
伝えたいことを入力するだけで、プロ級のビジネスメールが完成します