
組織で共有すべき!クレーム対応マニュアル作成のポイント徹底解説
 AIメール作成ツール 代筆さん
2025-07-19
AIメール作成ツール 代筆さん
2025-07-19
「またクレームの電話だ…」
「どう対応したらいいんだろう…」
あなたは、お客様からのクレーム対応に、日々頭を悩ませていませんか?
実は私も、以前はクレーム対応が本当に苦手で、電話が鳴るたびにドキドキしていました。
担当者によって対応がバラバラだったり、うまく説明できずにかえってお客様を怒らせてしまったり…。
そんな経験、あなたにもありませんか?
クレームは、どんなビジネスにおいても避けて通れないものです。
しかし、その対応次第で、お客様の信頼を失うこともあれば、逆にファンになっていただけるチャンスにもなり得ます。
今回は、そんなクレーム対応の負担を減らし、組織全体の対応力を底上げするための「クレーム対応マニュアル」作成のポイントを、私の経験も交えながら詳しくご紹介します。
この記事を読めば、あなたも自信を持ってクレーム対応に臨めるようになるでしょう。
なぜクレーム対応マニュアルが必要なのか?

そもそも、なぜわざわざマニュアルを作る必要があるのでしょうか?
「経験豊富なベテランに任せておけば大丈夫」なんて思っていませんか?
でも、それは少し危険な考え方かもしれません。
マニュアルがないと、実は多くの問題が発生する恐れがあるのです。
対応の属人化を防ぎ、品質を均一化する
マニュアルがないと、クレーム対応は個々の担当者の経験やスキルに依存してしまいます。
これがいわゆる「属人化」という状態です。
ベテラン社員ならうまく対応できることでも、新人や経験の浅い担当者だと、どうしていいかわからず戸惑ってしまうことも少なくありません。
その結果、担当者によって対応の質にバラつきが出てしまい、「あの時は丁寧だったのに、今回はひどい対応だった」といった、さらなる不満を生む原因にもなりかねません。
マニュアルがあれば、誰が対応しても一定の品質を保つことができ、お客様に安心感を与えることができます。
これは、特に人手不足が叫ばれる今の日本企業にとっては、非常に重要なポイントと言えるでしょう。
新入社員や担当者変更時の教育コストを削減する
新しいスタッフが入社したり、担当者が変わったりするたびに、クレーム対応の方法を一から教えるのは大変ですよね。
口頭での説明だけでは細かいニュアンスが伝わりにくかったりして、教える側にも負担がかかります。
しかしマニュアルがあれば、基本的な対応方針や手順が明文化されているため、新任者でもスムーズに業務を覚えることができます。
これは教育担当者の負担軽減だけでなく、新任者が早期に戦力となるためにも大きなメリットです。
日本の企業では、ジョブローテーションなどで担当者が変わることも多いですから、マニュアルの存在は教育の効率化に直結します。
従業員の精神的負担を軽減する
クレーム対応は、精神的に大きな負担がかかる業務の一つです。
お客様の怒りや不満を直接受け止めるわけですから、ストレスを感じない人はいませんよね。
特に、対応方法がわからなかったり、自分の対応が正しかったのか不安になったりすると、その負担はさらに増大します。
マニュアルがあれば、「こういう場合はこう対応する」という明確な指針があるため、担当者は安心して対応に臨むことができます。
「マニュアル通りに対応した」という事実は、心理的な支えにもなります。
これは従業員のメンタルヘルスを守り、離職を防ぐ上でも非常に重要です。
長時間労働が問題視される中で、少しでも従業員の負担を減らす工夫は大切ですね。
顧客満足度向上と企業イメージを守る
クレームは、お客様からの貴重なフィードバックです。
適切に対応できれば、問題を解決できるだけでなく、お客様の不満を満足に変え、むしろ企業のファンになっていただける可能性すらあります。
逆に、不適切な対応をしてしまうと、顧客満足度が低下するだけでなく、SNSなどで悪い評判が広がり、企業イメージを大きく損なうことにもなりかねません。
マニュアルに基づいた一貫性のある丁寧な対応は、お客様からの信頼を得て、長期的な関係性を築くための基盤となります。
企業の信頼を守るためにも、マニュアル整備は不可欠と言えるでしょう。
効果的なクレーム対応マニュアル作成の5つのステップ
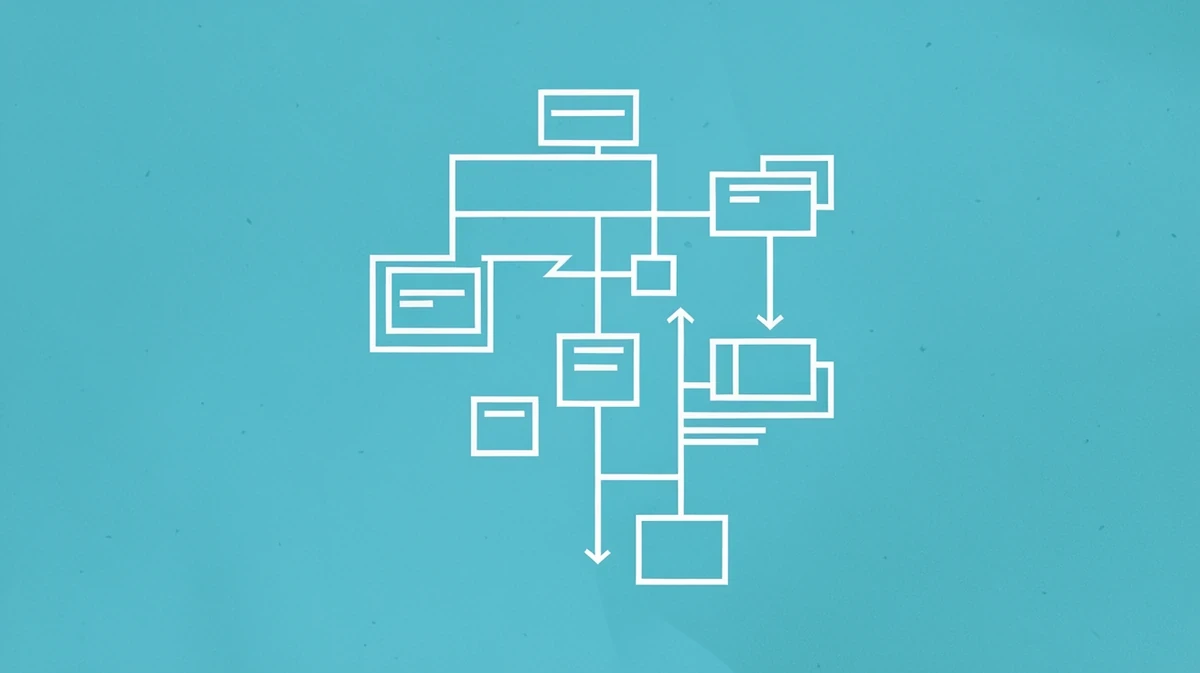
では、実際にどのようなマニュアルを作成すれば良いのでしょうか?
ただ手順を書き連ねるだけでは、いざという時に役立たない「使えないマニュアル」になってしまう可能性もあります。
ここでは、本当に役立つマニュアルを作成するための5つのステップをご紹介します。
ステップ1:クレームの種類と発生状況を分析する
まずは、あなたの組織で実際にどのようなクレームが発生しているのかを把握することから始めましょう。
過去のクレーム記録や担当者へのヒアリングを通じて、以下のような情報を集めます。
- よくあるクレームの内容: 商品の不具合、サービスの質、接客態度、説明不足など、具体的にどんな内容が多いか。
- 発生しやすい部署や状況: どの部署で、どんなタイミング(購入時、問い合わせ時、利用後など)でクレームが発生しやすいか。
- お客様の属性: クレームを申し立てるお客様に、何か共通する特徴はあるか。
この分析によって、マニュアルで重点的にカバーすべき内容や、特に注意すべきポイントが見えてきます。
やみくもに作るのではなく、現状をしっかり把握することが、効果的なマニュアル作成の第一歩です。
ステップ2:対応方針と基本姿勢を明確にする
次に、クレームに対して組織としてどのように向き合うか、基本的な考え方や姿勢を明確に定めます。
これはマニュアル全体の土台となる、非常に重要な部分です。
例えば、以下のような項目を具体的に言語化しましょう。
- お客様への共感: まずはお客様の気持ちに寄り添い、不快な思いをさせてしまったことを真摯に受け止める姿勢を示す。
- 傾聴の姿勢: お客様の話を最後まで丁寧に聞き、言い分を正確に理解する。
- 迅速かつ誠実な対応: たらい回しにせず、できる限り早く、誠意をもって対応する。
- 丁寧な言葉遣い: 状況に応じた適切な敬語を使い、お客様に失礼のないようにする。
日本のビジネスコミュニケーションでは、特に丁寧さや相手への配慮が重視されますよね。
この基本方針をマニュアルの冒頭に明記し、全従業員で共有することが大切です。
ステップ3:具体的な対応フローを定める
基本方針が決まったら、クレーム発生から解決までの具体的な流れ(フロー)を段階ごとに定めます。
誰が、いつ、何をするのかを明確にすることで、スムーズな対応が可能になります。
一般的なフローとしては、以下のようなものが考えられます。
- 初期対応(一次受け): 最初にクレームを受けた担当者が行うべきこと(お詫び、傾聴、状況確認、担当部署への連携など)。
- 担当者への引き継ぎ: 専門部署や担当者へ、正確かつ迅速に情報を伝達する方法。
- 事実確認と原因究明: クレーム内容の事実関係を確認し、原因を特定する手順。
- 解決策の検討と提示: お客様の状況や要望を踏まえ、適切な解決策(修理、交換、返金、代替案など)を検討し、提示する方法。
- 合意形成とクロージング: お客様に解決策を納得いただき、対応を完了するまでのプロセス。
- 事後対応(報告・記録): 対応内容を記録し、関係部署や上司に報告するルール。
特に、日本のビジネス文化である「報告・連絡・相談(ほうれんそう)」は、クレーム対応においても非常に重要です。
どの段階で誰に報告・相談すべきかをフローに明記しておきましょう。
ステップ4:状況別の対応例(トークスクリプト)を用意する
具体的な対応フローに加えて、よくあるクレームの状況に応じた対応例やトークスクリプトを用意しておくと、担当者はさらに安心して対応できます。
例えば、以下のようなケース別に、具体的な言い回しや注意点を記載します。
- 商品に関するクレーム: 不良品、異物混入、期待外れなど。
- サービスに関するクレーム: 説明不足、手続きの遅延、約束不履行など。
- 接客態度に関するクレーム: 言葉遣い、表情、対応の遅さなど。
- 理不尽な要求や過度な要求への対応: どこまで対応し、どこからは毅然と断るか。
- 感情的なお客様への対応: 冷静に対応するための心構えや言葉遣い。
また、対応チャネル(対面、電話、メール、チャットなど)によっても注意点が異なります。
特にメール対応では、件名の書き方、書き出しと結びの定型表現、CC・BCCの適切な使い方など、日本のメール文化に合わせたマナーも記載しておくと良いでしょう。
「言ってはいけないNGワード集」なども用意しておくと、失敗を防ぐのに役立ちます。
ステップ5:エスカレーションルールを決める
すべてのクレームを担当者レベルで解決できるわけではありません。
中には、担当者の権限を超えたり、専門的な判断が必要だったり、対応が長期化したりするケースもあります。
そのような場合に、問題を上位者や専門部署にスムーズに引き継ぐためのルール(エスカレーションルール)を明確に定めておくことが重要です。
- エスカレーションする基準: どのような場合に上位者や専門部署に相談・報告すべきか(例:返金要求額が一定以上、法的問題に発展しそう、お客様が激高しているなど)。
- 報告・相談する相手: 誰に(直属の上司、専門部署の担当者など)連絡すべきか。
- 報告・相談の方法: どのような情報(経緯、お客様の要望、担当者の見解など)を、どのように(口頭、メール、報告書など)伝えるか。
このルールが曖昧だと、対応が遅れたり、担当者が一人で抱え込んでしまったりする原因になります。
迅速かつ適切な判断のためにも、明確な基準と手順を定めておきましょう。
マニュアルを形骸化させないための運用ポイント

せっかく素晴らしいマニュアルを作成しても、それが活用されなければ意味がありませんよね。
「マニュアルはあるけど、誰も見ていない」「内容が古くて現状に合っていない」なんてことにならないように、作成後の運用にも力を入れることが大切です。
定期的な見直しと更新を行う
クレームの内容や発生状況は、市場環境の変化、新商品・サービスの導入、社会情勢などによって常に変化します。
そのため、マニュアルも一度作ったら終わりではなく、定期的に内容を見直し、最新の情報に合わせて更新していく必要があります。
最低でも年に1回、できれば半年に1回程度の見直しを行うのが理想的です。
新たに対応事例として加えるべきクレームはなかったか、既存の対応フローに改善点はないかなどを検討し、常に「使えるマニュアル」であり続けるように、定期的にメンテナンスしましょう。
研修やロールプレイングで習熟度を高める
マニュアルを読んだだけでは、いざという時にスムーズに対応できないこともあります。
内容をしっかりと理解して実践できるようになるためには、定期的な研修やロールプレイングを取り入れるのが効果的です。
- マニュアル読み合わせ会: 新しい担当者向けや、定期的な復習のために、マニュアルの内容を一緒に確認する機会を設ける。
- ケーススタディ: 過去の事例や想定されるクレームケースをもとに、どのように対応すべきかグループで討議する。
- ロールプレイング: 実際にお客様役と担当者役に分かれて、クレーム対応のシミュレーションを行う。
こうした実践的なトレーニングを通じて、マニュアルの内容を「知識」から「スキル」へと昇華させることができます。
成功事例や改善点を共有する文化を作る
クレーム対応は、うまくいった事例も、改善が必要だった事例も、組織全体にとって貴重な学びの機会です。
個々の担当者が経験したことを、積極的に共有し合う文化を作りましょう。
「あの対応でお客様に喜んでもらえた」「この言い方は避けた方がよかった」といった具体的な経験談は、他の担当者にとっても非常に参考になります。
定例会議で共有する時間を設けたり、社内のSNSなどで気軽に情報交換できるようにしたりするのも良い方法です。
成功体験は自信につながり、失敗体験は次の改善につながります。
組織全体で学び合い、対応力を高めていく意識が大切です。
アクセスしやすい場所に保管・共有する
マニュアルは、必要な時に、誰でも、すぐに参照できる状態にしておくことが重要です。
分厚いファイルに綴じられて書庫に眠っている…なんてことでは意味がありません。
社内の共有フォルダやポータルサイト、グループウェアなど、従業員が普段からアクセスしやすい場所に電子データで保管するのがおすすめです。
検索機能を使えば、必要な情報をすぐに見つけ出すこともできます。
常に最新版が共有されるように、更新管理のルールも決めておきましょう。
AIを活用したクレーム対応の効率化

最近では、AI(人工知能)の技術を活用して、クレーム対応を含むカスタマーサポート業務を効率化しようという動きが活発になっています。
AIは、私たちの業務をどのようにサポートしてくれるのでしょうか?
メール対応におけるAIの可能性
特に、メールでのクレーム対応においては、AIが大きな助けとなる可能性があります。
「丁寧な謝罪文を考えなきゃ…」「失礼のないように構成を整えないと…」
メール作成って、意外と時間と気を使いますよね。
そんな悩みを解決するのが、『代筆さん』です。
代筆さんは、簡単な指示や要点を伝えるだけで、AIが状況に応じたビジネスメールを作成してくれるWebサービスです。
例えば、お客様からのクレームメールの内容と、伝えたい返信の要点(お詫び、原因調査中であること、今後の対応など)を指示するだけで、AIが丁寧で適切な構成の返信メール案を作成してくれます。
相手の言語に合わせてメッセージを作成することもできるので、海外のお客様からのクレームにも対応しやすいです。
また、よく使う謝罪文や対応パターンの指示を保存しておけば、類似のクレームに対して毎回ゼロから文章を考える手間が省け、迅速かつ一貫性のある対応が可能になります。
もちろん、AIが作成した文章は、最終的に人間が確認し、必要に応じて修正することが大切ですが、ベースとなる文章があるだけで、メール作成の負担は大幅に軽減されるはずです。
忙しいあなたのメール作成をサポートする、心強い味方となるでしょう。
AIチャットボットによる一次対応の自動化
Webサイトなどでの問い合わせ窓口として、AIチャットボットを導入する企業も増えています。
チャットボットは、よくある質問や定型的な問い合わせに対して、24時間365日、自動で応答することができます。
「営業時間外だけど、すぐに回答がほしい」といったお客様のニーズに応えられるのは大きなメリットです。
簡単な質問であればチャットボットが解決してくれるため、人間のオペレーターは、より複雑な問題や個別性の高いクレーム対応に集中することができます。
これにより、業務全体の効率化と顧客満足度の向上が期待できます。
AI利用時の注意点と人間の役割
AIは非常に便利なツールですが、万能ではありません。
AIは、過去の膨大なデータから学習して、人間らしい自然な文章を作成したり、共感を示すような表現を使ったりすることは得意です。
しかし、AIには人間のような感情や倫理観はありません。
そのため、非常にデリケートなクレームや、お客様の深い感情に寄り添う必要がある場面では、やはり人間のきめ細やかな対応が不可欠です。
また、AIは時に間違った情報や不適切な回答を生成することもあります。
AIが生成した回答を鵜呑みにせず、必ず人間が内容を確認して最終的な判断を下す必要があります。
AIはあくまでもサポートツールであり、人間の仕事を完全に代替するものではありません。
AIの得意なこと(定型業務の自動化、情報検索、文章作成支援など)はAIに任せ、人間は人間にしかできないこと(共感、複雑な問題解決、最終判断など)に集中する。
このように、AIと人間がそれぞれの強みを活かして協力することで、より質の高いクレーム対応が実現できるのではないでしょうか。
まとめ:信頼される組織を作るためのクレーム対応

今回は、組織で共有すべきクレーム対応マニュアルの作成ポイントと、その運用、さらにAIを活用した効率化についてお話ししてきました。
クレーム対応は、決して楽な仕事ではありません。
しかし、実用的でわかりやすいマニュアルを準備し、組織全体で適切に対応できる体制を築くことは、顧客満足度の向上、従業員の負担軽減、そして企業の信頼を守る上で非常に重要です。
マニュアル作成は、クレーム分析から始まり、基本方針、対応フロー、トークスクリプト、エスカレーションルールを明確に定めるステップで進めます。
そして、作ったマニュアルを形骸化させないためには、定期的な見直し・更新、研修、情報共有、アクセスしやすい環境づくりが欠かせません。
近年では、メール作成などをサポートするツールも登場しています。例えば、『代筆さん』を活用すれば、クレームメールへの返信作成にかかる時間を短縮し、より丁寧で一貫性のあるコミュニケーションを実現する手助けとなるでしょう。
クレームはピンチではなく、組織を成長させるチャンスです。
この記事を参考に、あなたの組織に合った効果的なクレーム対応マニュアルを作成・運用し、お客様からも従業員からも信頼される、より良い組織づくりを目指してくださいね。
今すぐAIでメールを作成してみよう!
伝えたいことを入力するだけで、プロ級のビジネスメールが完成します
