
人事評価スケジュール 従業員向け定期評価案内メール作成のコツ
 AIメール作成ツール 代筆さん
2025-08-03
AIメール作成ツール 代筆さん
2025-08-03
件名:【重要】[年度]度 人事評価スケジュールのご案内
株式会社[会社名]
[社員名]様
お世話になっております。
[会社名]、人事部の[担当者名]です。
平素は格別のご尽力、誠にありがとうございます。
さて、[年度]度の定期人事評価を下記の通り実施いたします。
つきましては、ご多忙の折とは存じますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
■評価期間
[開始日]~[終了日]
■対象者
[部署名] 所属の全従業員
■評価方法
- [評価システム名]にログイン
- 自己評価シートの記入([提出期限]まで)
- 一次評価者による評価
- 二次評価者による評価
※評価シートの記入方法については、添付のマニュアルをご参照ください。
■スケジュール
- 自己評価提出期限:[提出期限]
- 一次評価期間:[開始日]~[中間日]
- 二次評価期間:[中間日]~[終了日]
- フィードバック面談:[面談期間]
※フィードバック面談の日程は、後日改めてご連絡いたします。
■評価結果に関するお問い合わせ窓口
人事部 [担当者名]
電話番号:[電話番号]
メールアドレス:[メールアドレス]
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
人事担当者の皆さん、こんにちは。
定期評価の時期が近づいてきましたね。
「今年も、どうやって従業員にスケジュールを伝えよう…」と頭を悩ませていませんか?
でも、ご安心ください。
今回は、評価スケジュール通知の重要性から、具体的なメールの書き方、さらに円滑に進めるための注意点まで、まるっとご紹介します。
この記事を読めば、従業員が「なるほど。」と納得し、前向きに評価に取り組んでくれるような案内メールが書けるようになりますよ。
ぜひ、最後までお付き合いくださいね。
従業員への定期評価スケジュール通知の重要性

従業員への定期評価が重要な理由
定期評価のスケジュールを従業員にきちんと伝えることは、組織全体の成長に不可欠です。
なぜなら、評価は単なる人事手続きではなく、従業員一人ひとりの成長を促し、組織全体のパフォーマンスを向上させるための大切な機会だからです。
スケジュールを事前に周知することで、従業員は評価に向けて準備を始めることができます。
自己評価をしたり、目標達成度を振り返ったり、自分の成長を考える時間を持つことができるでしょう。
これにより、評価に対する当事者意識が高まり、より建設的な評価プロセスにつながります。
従業員の不安解決にも効果あり
また、評価スケジュールを明確にすることは、従業員の不安を解消する上でも重要です。
「いつ評価されるんだろう?」「どうやって評価されるんだろう?」といった疑問や不安を抱えたままでは、評価に対するモチベーションも下がってしまいます。
評価スケジュールを事前に共有することで、従業員は安心して業務に集中できるようになります。
さらに、評価プロセスに対する透明性が高まり、組織への信頼感も向上するでしょう。
さらに、定期評価のスケジュール通知は、人事部と従業員間のコミュニケーションを円滑にする効果もあります。
スケジュールを共有する過程で、評価に関する質問を受け付けたり、評価制度について説明したりする機会を持つことで、相互理解が深まります。
結果として、従業員は評価を「一方的に決められるもの」ではなく「一緒に成長するための機会」として捉えることができるようになるでしょう。
このように、定期評価のスケジュール通知は、従業員の成長と組織の発展を両立させるための重要な第一歩なのです。
次は、具体的な案内メールの構成について詳しく見ていきましょう。
定期評価案内メールの基本構成と必須項目

定期評価の案内メールは、従業員が評価プロセスを理解し、安心して評価に臨むための重要なコミュニケーションツールです。
メールの構成と必須項目を明確にすることで、評価への疑問や不安を解消し、スムーズな評価の実施につながります。
このセクションでは、案内メールの基本構成と、必ず含めるべき項目について詳しく解説します。
評価期間と対象者 明確な記載
まず、評価期間と対象者を明確に記載することが重要です。
これにより、従業員は自分がいつ、どの評価対象期間の評価を受けるのかを正確に把握できます。
曖昧な表現は避け、具体的な日付や部署名、役職などを記載しましょう。
評価対象となる従業員が、自分に関係のある情報だと認識できるようにする必要があります。
例文 評価期間と対象者の記載例
件名:2024年度[評価期間]の定期評価実施のお知らせ
[従業員名]様
平素は格別のご尽力、誠にありがとうございます。
この度、2024年度[評価期間]の定期評価を下記の通り実施いたします。
対象者:[部署名]所属の全従業員
評価期間:[開始日]~[終了日]
ご多忙中恐縮ですが、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
評価方法と手順の丁寧な説明
評価方法と手順を丁寧に説明することも、従業員の理解を深める上で不可欠です。
評価シートの記入方法、自己評価の有無、提出期限など、具体的な手順を説明しましょう。
また、評価に使用するツールやシステムがある場合は、その利用方法も併せて案内することが望ましいです。
従業員が迷うことなく評価プロセスを進められるよう、分かりやすい説明を心がけましょう。
例文 評価方法と手順の説明例
件名:2024年度[評価期間]の定期評価実施のお知らせ
[従業員名]様
平素は格別のご尽力、誠にありがとうございます。
今回の定期評価は以下の手順で実施いたします。
- [評価システム名]にログイン
- 自己評価シートの記入([提出期限]まで)
- 一次評価者による評価
- 二次評価者による評価
評価シートの記入方法については、添付のマニュアルをご参照ください。
ご不明な点がございましたら、人事部までお問い合わせください。
この例では、評価の手順をステップごとに説明し、従業員がどのように評価プロセスを進めるべきかを明確にしています。
評価フィードバックの時期と方法
評価フィードバックの時期と方法についても、事前に明確に伝える必要があります。
これにより、従業員はいつ、どのようにフィードバックを受けられるのかを把握し、結果に対する心構えができます。
面談形式でのフィードバックなのか、書面での通知なのかなど、具体的な方法を記載しましょう。
また、フィードバック内容に関する質問受付についても、事前に案内しておくとより丁寧です。
例文 評価フィードバック時期と方法の説明例
件名:2024年度[評価期間]の定期評価実施のお知らせ
[従業員名]様
平素は格別のご尽力、誠にありがとうございます。
評価結果のフィードバックは、[フィードバック実施期間]に個別面談にて行います。
面談日程については、後日改めてご連絡いたします。
評価結果に関するご質問は、[受付期間]までに人事部[担当者名]までご連絡ください。
今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
ここでは、フィードバックの方法(個別面談)と時期([フィードバック実施期間])、質問受付の期間と担当者を明記しています。
従業員が納得する評価フィードバックの伝え方

ここまで、評価フィードバックの時期と方法を明確に伝えることの重要性について解説しました。
続いては、さらに一歩踏み込み、従業員が評価結果を納得し、成長につなげるためのフィードバック方法について掘り下げて説明します。
評価結果を伝える際は、ただ事実を述べるだけでなく、従業員のモチベーションを高め、今後の成長を促すような伝え方を心がけることが大切です。
具体的な事例を挙げてフィードバック
抽象的な表現ではなく、具体的な事例を挙げてフィードバックを行うことで、従業員は自身の行動を客観的に理解しやすくなります。
例えば、「〇〇さんの企画書はいつも素晴らしい」という抽象的なフィードバックではなく、
「先日の〇〇プロジェクトの企画書では、市場調査のデータに基づいた具体的な提案がされており、非常に参考になった」
といった具体的なフィードバックを心がけましょう。
これにより、従業員は自身のどの行動が評価されたのか、より明確に理解できます。
具体例を提示する際のポイント
- 具体的な行動や成果を特定する
- 行動がもたらした結果を説明する
- ポジティブな点と改善点をバランスよく伝える
改善点と成長を促す言葉を選ぶ
フィードバックを行う際は、改善点を指摘するだけでなく、どのようにすれば成長できるのかを具体的に示すことが重要です。
「〇〇さんの資料は少しわかりにくい」という指摘だけでは、従業員はどう改善すれば良いのかが分かりません。
代わりに、
「〇〇さんの資料は、もう少し図やグラフを用いて視覚的に情報を整理すると、さらに分かりやすくなると思います」
といった具体的なアドバイスと合わせて伝えましょう。
これにより、従業員は次に何をすべきか明確になり、成長への意欲を高めることができます。
成長を促すフィードバックのポイント
- 改善点を具体的に指摘する
- 成長のための具体的なアドバイスをする
- ポジティブな言葉を使い、自信を持たせる
一方的な評価にならない双方向の対話
評価フィードバックは、一方的に評価結果を伝える場ではありません。
従業員が自身の評価について意見や質問を述べられる双方向の対話の場と捉えましょう。
評価に対する従業員の疑問や不安に耳を傾け、丁寧に答えることで、評価への理解と納得を深めることができます。
また、従業員からのフィードバックを今後の人事評価制度の改善につなげることも可能です。
双方向の対話を促すポイント
- 従業員の意見や質問を丁寧に聞く
- 評価の根拠を明確に説明する
- 今後の成長に向けた目標設定を一緒に行う
次は、これまでの内容を踏まえ、実際に従業員へ送付する人事評価スケジュール周知メールのテンプレート例を紹介します。
人事評価スケジュール周知メールのテンプレート例

件名と冒頭文の書き方
人事評価スケジュールを周知するメールは、従業員が内容をすぐに理解できるように、件名と冒頭文で目的を明確に伝えることが重要です。
件名では「人事評価」というキーワードを使い、メールの目的が評価スケジュールに関するものであると明示します。
冒頭文では、挨拶とともに、評価実施の目的と協力のお願いを簡潔に述べましょう。
例文1 件名と冒頭文の例
件名:【重要】[年度]度 人事評価スケジュールのご案内
[社員名]様
いつも業務にご尽力いただき、ありがとうございます。
この度、[年度]度人事評価を下記スケジュールにて実施いたします。
皆様にはお忙しいところ恐縮ですが、ご理解とご協力をお願いいたします。
この例文では、件名で「重要」と明記することで、メールの重要度を伝え、従業員の注意を引くようにしています。
また、冒頭文では、感謝の言葉とともに、評価実施の目的と協力を依頼する言葉を添えることで、丁寧な印象を与えます。
本文構成のポイント
メール本文では、評価スケジュール、評価方法、フィードバック時期など、従業員が知りたい情報を分かりやすく整理して記載することが大切です。
箇条書きや表を用いるなど、情報を視覚的に整理することで、読みやすさが向上します。
また、評価に関する質問受付窓口や担当者を明記することで、従業員の疑問や不安を解消し、スムーズな評価実施につながります。
例文2 本文構成の例
件名:【重要】[年度]度 人事評価スケジュールのご案内
[社員名]様
いつも業務にご尽力いただき、ありがとうございます。
この度、[年度]度人事評価を下記スケジュールにて実施いたします。
皆様にはお忙しいところ恐縮ですが、ご理解とご協力をお願いいたします。
■評価期間
[開始日]~[終了日]
■対象者
全社員
■評価方法
[評価方法]
■スケジュール
- 自己評価提出期限:[提出期限]
- 一次評価:[評価期間]
- 二次評価:[評価期間]
- フィードバック面談:[面談期間]
■評価に関するお問い合わせ窓口
人事部 [担当者名]
電話番号:[電話番号]
メールアドレス:[メールアドレス]
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
この例文では、評価期間、対象者、評価方法、スケジュールを明確に記載しています。
さらに、問い合わせ窓口を明記することで、従業員が安心して評価に臨めるように配慮しています。
人事評価スケジュールを円滑に進めるための注意点
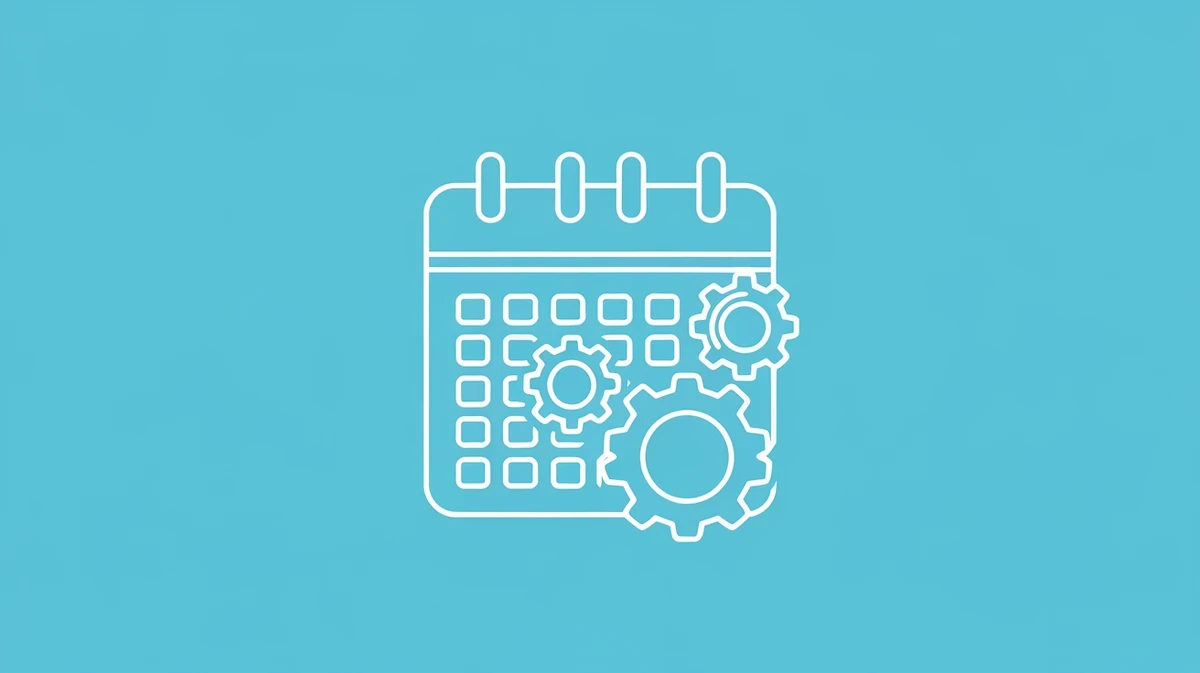
人事評価スケジュールをスムーズに進めるためには、事前の準備と丁寧な対応が不可欠です。
従業員が安心して評価に臨み、その結果を成長につなげられるように、以下の点に注意しましょう。
評価者トレーニングの実施
評価者による評価のばらつきを防ぐため、評価者トレーニングを実施しましょう。
評価基準や評価項目の理解を深め、客観的かつ公平な評価ができるように研修を行います。
トレーニングでは、具体的な事例を用いた演習を取り入れると、より実践的な学びにつながります。
また、評価者間の認識のずれをなくすため、定期的な情報共有や意見交換の場を設けることも有効です。
評価に対する質問受付体制
評価期間中は、従業員からの質問や疑問に迅速に対応できる体制を整えましょう。
質問窓口を明確にし、メールやチャットツールなど、複数の連絡手段を用意することで、従業員が気軽に相談できるようにします。
よくある質問はFAQとしてまとめ、社内ポータルサイトなどで公開すると、問い合わせ対応の効率化にもつながります。
評価に対する不安や疑問を解消することで、従業員は安心して評価に臨むことができ、評価結果への納得度も高まります。
評価内容の守秘義務徹底
従業員の評価結果は、非常にデリケートな個人情報です。
評価内容が外部に漏洩することのないよう、厳重な管理体制を徹底しましょう。
評価シートの取り扱い、評価結果の保管方法、共有範囲などを明確に定め、関係者全員に周知します。
個人情報保護に関する研修を実施し、守秘義務の重要性を再認識させましょう。
従業員からの信頼を得るためにも、情報管理の徹底は必要不可欠です。
人事担当者必見!評価スケジュール案内を『代筆さん』で効率化
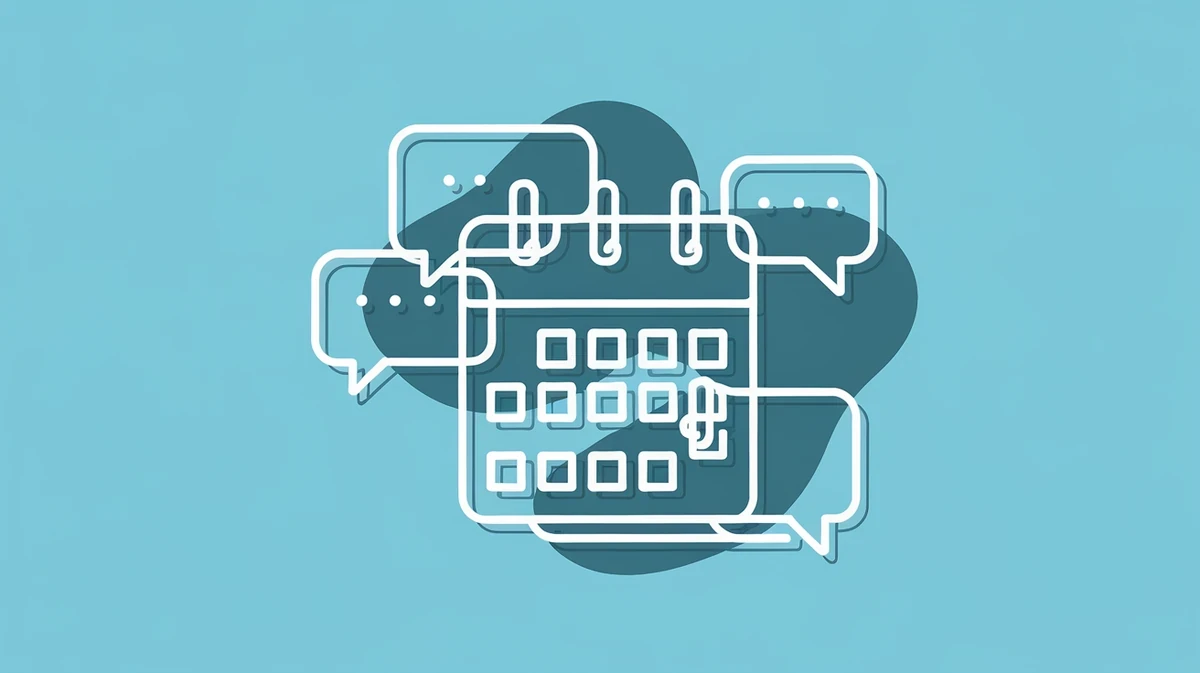
従業員への配慮と組織全体への影響を考慮した評価案内メールを作成することが重要だとわかっていても、適切な文面を整えるには相応の準備と時間を要します。
評価期間や手順の明確な説明、従業員が安心できる表現選び、質問受付窓口の案内など、配慮すべき要素が多岐にわたるため、思っている以上に負担の大きい作業かもしれません。
そんなときに役立つのが、AI文章作成支援ツール『代筆さん』です。
『代筆さん』は、評価スケジュールの詳細など伝えたい要点を簡単に入力するだけで、人事業務にふさわしい丁寧で分かりやすいメール文を自動で提案してくれます。
さらに、文体の調整機能により、あなたの組織の雰囲気や評価制度の性質に合わせたトーンでの作成が可能です。
例えば、全社員向けの公式な通知にふさわしいフォーマルな文面や、部署内での親しみやすい案内に適したやや柔らかい表現など、状況に応じて使い分けられます。
定型文の保存機能も備えているため、年次評価や四半期評価で繰り返し使用する基本的な文面をワンクリックで呼び出すことができ、毎回の入力作業を大幅に短縮できます。
なお、AIが生成する文章は非常に便利ではあるものの、必ずしも100%完璧な内容になるとは限りません。
最終的な表現や評価制度との整合性については、ご自身で内容を確認し、必要に応じて調整することが前提となります。
しかし、一から文面を考える手間が省けることで、評価制度の改善検討や従業員フォローなど、本来注力すべき人事業務に集中できるようになるのは大きなメリットです。
『代筆さん』には無料プランも用意されており、まずは気軽に試すことが可能です。
本格的に活用したい場合は、比較的リーズナブルな価格帯の有料プランに移行することもできます。
人事評価案内メールの作成負担を減らし、従業員への丁寧な対応を効率化したい方は、ぜひ一度『代筆さん』を活用してみてはいかがでしょうか。
まとめ:定期評価スケジュール理解と信頼構築のために

評価案内メールは、単なる業務連絡ではなく、従業員との信頼関係を築く大切なコミュニケーションの一環です。
- 評価期間、対象者、方法を明確に伝える
- 具体的な事例に基づいたフィードバックをする
- 評価者へのトレーニングと質問受付体制を整える
これらのポイントをしっかりと押さえることで、従業員は評価プロセスへの理解を深め、会社への信頼感を高めることができます。
評価期間や方法について、従業員にとって分かりにくい点はないか、改善できる部分はないか、もう一度確認してみることをおすすめします。
小さな見直しが、よりスムーズな評価プロセスにつながるはずです。
もし、「人事評価スケジュールの案内メール、何を書けばいいか毎回迷う…」という感じている方は、『代筆さん』の活用を検討してみてください。
伝えたい内容を箇条書きで入力するだけで、従業員に配慮した、読みやすく丁寧な文面を自動生成してくれます。
一文一文に込める丁寧さは、組織全体の評価に対する印象や納得感にもつながっていきます。
従業員一人ひとりが納得感を持って評価を受けられるように、そして、それぞれの成長につながるような評価制度となるよう、心から応援しています。
今すぐAIでメールを作成してみよう!
伝えたいことを入力するだけで、プロ級のビジネスメールが完成します
