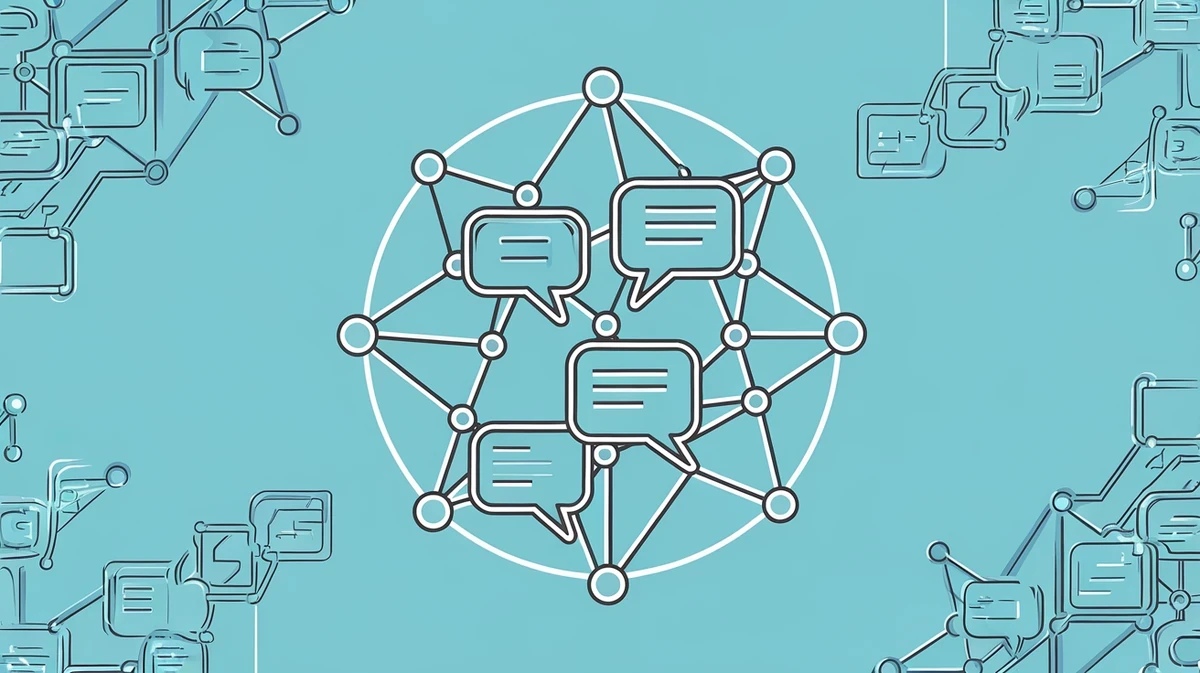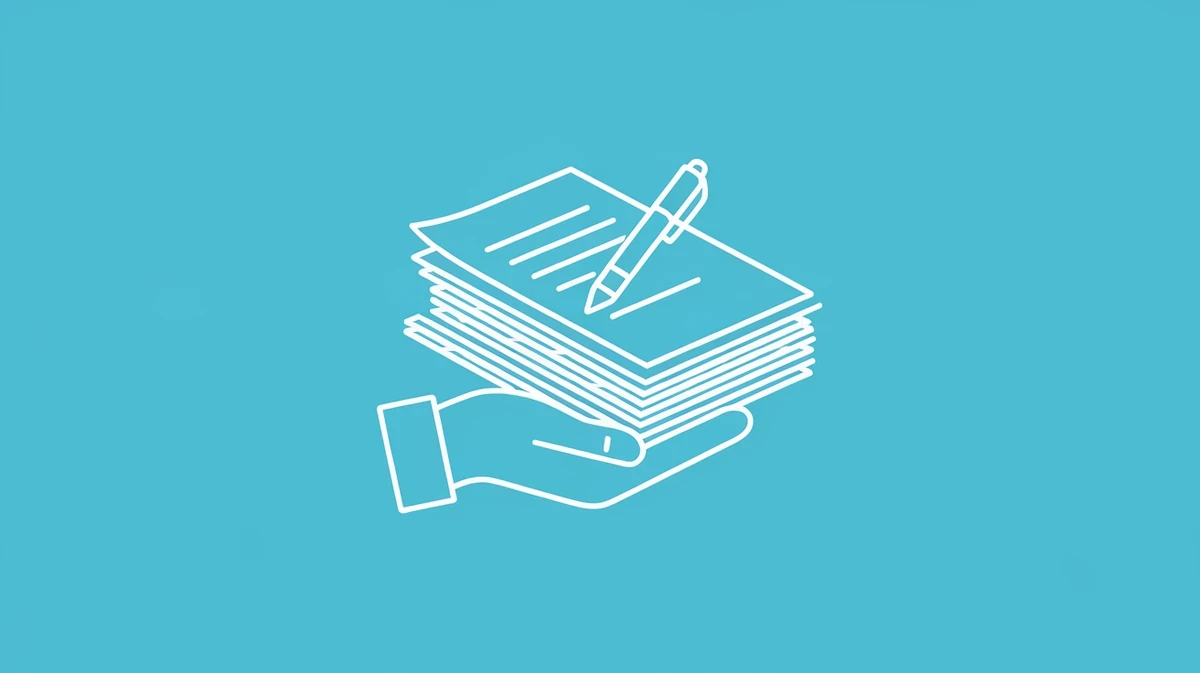件名:【[研修名]】研修後のフォローアップ:業務での実践に向けて
株式会社[会社名]
[宛名]様
お世話になっております。
[会社名]、[部署名]の[名前]です。
先日は[研修名]にご参加いただき、誠にありがとうございました。
[宛名]様の積極的なご参加のおかげで、大変有意義な研修となりました。
研修で学んだ[具体的な研修内容]について、[宛名]様の今後の業務でどのように活用できるか、ぜひ検討いただけたらと思います。
つきましては、研修内容の理解を深めていただくため、下記の点についてご協力をお願いできますでしょうか。
- 研修資料の再確認
研修内容を振り返り、不明な点があればお気軽にご質問ください。 2. 業務での実践計画の作成
研修で得た知識やスキルを、実際の業務でどのように活用できるか具体的な計画を立ててみましょう。 3. 簡単なアンケートへのご回答
今後の研修の質向上のため、[アンケートURL] よりご協力いただけますと幸いです。回答期限は[回答期限]までとさせていただきます。
ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
[宛名]様の今後のご活躍を心より応援しております。
引き続きよろしくお願いいたします。
研修後のフォローアップ、ちゃんとできていますか?
せっかく時間とお金をかけた研修も、その後のフォローがなければ効果は半減…もったいないですよね。
「研修内容、ちゃんと理解してもらえたかな?」「学んだことを業務で活かしてくれているかな?」そんな不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、研修後のフォローアップメールの重要性から、具体的な例文、効果を最大化するコツまで、あなたの悩みを解決する情報が満載です。
この記事を読めば、研修効果をグッと高め、参加者の成長を後押しできるはず。
さあ、一緒に研修効果を最大化するフォローアップ戦略を学びましょう。
まずは、フォローアップメールの重要性と目的から見ていきましょう。
研修後フォローアップメールの重要性と目的

なぜフォローアップメールが重要なのか
研修後のフォローアップメールは、単なるお礼の連絡ではありません。
研修で学んだ内容を参加者の記憶に定着させ、行動変容を促すための重要なステップです。
研修後、時間が経つにつれて、どうしても記憶は薄れてしまいます。
フォローアップメールは、研修内容を振り返るきっかけを与え、学習効果を持続させる効果があるのです。
また、参加者とのコミュニケーションを継続することで、研修に対するモチベーションを維持し、今後の業務への意欲を高めることにも繋がります。
さらに、メールでのやり取りを通して、参加者の疑問や不安を解消し、研修内容の理解を深めることができます。
つまり、フォローアップメールは、研修効果を最大化するための必須ツールと言えるでしょう。
フォローアップメールで達成する目的
フォローアップメールには、大きく分けて3つの目的があります。
1. 研修内容の定着と理解度向上
研修で学んだ知識やスキルを、参加者がしっかりと理解し、自分のものにできるようにサポートします。
メールを通じて、研修内容の復習を促したり、理解度を確認したりすることで、知識の定着を図ります。
2. 業務への活用促進
研修で得た学びを、実際の業務でどのように活用できるのかを具体的に伝え、参加者の行動変容を促します。
研修内容と業務を結びつけることで、参加者の業務効率や成果向上に繋げることが可能です。
3. 参加者のモチベーション維持と向上
研修後も参加者とのコミュニケーションを継続し、研修への関心を持続させます。
フォローアップメールは、参加者にとって研修が終わりではなく、成長の始まりであることを意識づける効果があります。
これらの目的を意識してフォローアップメールを作成することで、研修効果を最大限に引き出すことができるでしょう。
次の章では、効果的なフォローアップメールを作成するための具体的なポイントを解説していきます。
効果的なフォローアップメールを書くための3つのポイント

研修後のフォローアップメールは、参加者の理解度を高め、研修内容を業務に活かしてもらうために非常に重要です。
ここでは、効果的なフォローアップメールを作成するための3つのポイントを解説します。
1. 件名で興味を引きつける
メールを開封してもらうためには、件名で興味を引くことが大切です。
研修内容を想起させつつ、具体的な行動を促すような件名を心がけましょう。
例えば、以下のような件名が考えられます。
- 「[研修名]の振り返り:業務での活用に向けて」
- 「[研修名]で学んだことを実践。理解度チェックのお願い」
- 「[研修名]で得た知識を定着させるためのフォローアップ」
件名を見ただけでメールの内容を想像でき、かつ自分にとって有益な情報だと感じてもらえるように工夫しましょう。
2. 本文で参加者の行動を促す
メールの本文では、研修内容の振り返りを促し、具体的な行動につなげるように意識しましょう。
まずは、研修への参加のお礼を述べ、研修内容のポイントを簡潔にまとめます。
次に、理解度を確認するための質問や、業務での実践を促すような具体的な課題を提示します。
例えば、以下のような行動を促すことができます。
- 研修資料の再確認
- 理解度確認テストへの回答
- 業務での実践計画の作成
- 疑問点や不明点の質問
参加者が「次に何をすべきか」を明確に理解できるように、具体的な指示を心がけましょう。
3. 返信しやすいメール構成にする
参加者が気軽に返信できるように、メールの構成を工夫することも重要です。
長文のメールは読むのが負担になるため、簡潔で分かりやすい文章を心がけましょう。
また、質問や意見をしやすいように、メールの最後に返信を促す一文を添えましょう。
具体的には、以下のような点を意識しましょう。
- 箇条書きや段落分けを活用する
- 質問しやすいように、具体的な質問を提示する
- 返信期限を設定する(任意)
- 「ご不明な点はお気軽にご連絡ください」といった一文を添える
これらのポイントを踏まえ、参加者がスムーズにメールに返信し、フォローアップの効果を最大限に引き出せるようにしましょう。
フォローアップメールの具体的な例文とテンプレート

研修後のフォローアップメールは、参加者の理解を深め、行動を促すための重要なツールです。
ここでは、具体的な例文とテンプレートを3つのケースに分けてご紹介します。
研修後のお礼、理解度確認、そして業務への活用促進という、それぞれの目的に合わせたメールを作成する際の参考にしてください。
研修後のお礼メール例文
研修後、まず送るべきはお礼のメールです。
参加者への感謝の気持ちを伝え、研修で得た学びを振り返るきっかけを与えましょう。
丁寧な言葉遣いを心がけ、好印象を与えることが大切です。
研修後のお礼メール例文
件名:[研修名]にご参加いただきありがとうございました
[参加者名]様
先日は[研修名]にご参加いただき、誠にありがとうございました。
[研修内容]について、[参加者名]様の前向きなご姿勢が大変印象的でした。
今回の研修で学んだことが、[参加者名]様の今後の業務の一助となれば幸いです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
[送信者名]
この例文では、研修への参加のお礼とともに、具体的な研修内容に触れることで、参加者への配慮を示しています。
また、今後の業務への活用を期待する言葉で結び、ポジティブな印象を与えます。
理解度確認を促すメール例文
研修内容の理解度を確認することは、研修の効果を測る上で非常に重要です。
理解度確認を促すメールでは、参加者が研修内容を振り返り、不明点を解消する機会を提供しましょう。
理解度確認を促すメール例文
件名:[研修名]の内容に関するアンケートご協力のお願い
[参加者名]様
先日は[研修名]にご参加いただき、ありがとうございました。
研修内容の理解度を深めていただくため、簡単なアンケートにご協力をお願いいたします。
回答期限は[回答期限]までです。ご多忙中恐縮ですが、ご協力いただけますと幸いです。
アンケートはこちら:[アンケートURL]
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
[送信者名]
この例文では、アンケートへの協力を依頼することで、参加者に研修内容の振り返りを促しています。
回答期限を明記することで、参加者の行動を促し、回答率の向上を目指します。
業務への活用を促すメール例文
研修で得た知識やスキルを業務で活用してもらうためには、具体的な行動を促すメールが必要です。
研修内容と業務との関連性を示し、具体的な行動計画を立てるサポートをしましょう。
業務への活用を促すメール例文
件名:[研修名]で学んだことの業務への活用について
[参加者名]様
先日は[研修名]にご参加いただき、誠にありがとうございました。
研修で学んだ[具体的な研修内容]について、[業務内容]でどのように活用できるか、ぜひ検討してみてください。
もし活用方法について不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
[送信者名]
この例文では、研修内容と業務との関連性を具体的に示し、参加者が研修内容を業務に活かすことを促しています。
質問を歓迎する姿勢を示すことで、参加者の不安を解消し、積極的な行動を促します。
フォローアップメールを送る際の注意点

研修後のフォローアップメールは、参加者の理解を深め、行動を促すための重要なツールです。
しかし、送り方によっては逆効果になることもあります。
ここでは、フォローアップメールを送る際に注意すべき3つのポイントを解説します。
送信タイミングを考慮する
フォローアップメールを送るタイミングは、研修の効果を左右する重要な要素です。
研修直後に送るのが良いとは限りません。
研修直後
研修内容の記憶が新しいうちに送ることで、内容の定着を促せます。
ただし、参加者がまだ研修の疲れを引きずっている可能性もあるため、メールの内容は簡潔にしましょう。
数日後
研修内容を振り返る時間を与え、業務への活用を促すには、数日後に送るのが効果的です。
参加者が研修内容を実際に業務で試す機会を設けてから、フォローアップメールを送ることで、より具体的な質問やフィードバックを得られるでしょう。
1週間後
研修内容の定着度を確認したり、参加者の疑問点や課題を把握するために、1週間後にフォローアップメールを送るのも有効です。
このタイミングでは、アンケートへの協力や個別面談の案内などを盛り込むと良いでしょう。
研修内容や参加者の状況に応じて、最適な送信タイミングを見極めることが大切です。
一方的な押し付けにならないようにする
フォローアップメールは、あくまで参加者の理解を深め、自発的な行動を促すためのものです。
一方的に研修内容を押し付けるようなメールにならないように注意しましょう。
命令口調を避ける
「~してください」「~しなければならない」といった命令口調は避け、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
参加者の状況を考慮する
参加者が研修内容を理解するのに時間がかかる場合もあります。
一方的に「理解できましたか」と問い詰めるのではなく、「何か疑問点はありませんか」「サポートが必要な場合は遠慮なくお申し付けください」といった、相手に寄り添う言葉を使いましょう。
フィードバックを求める
参加者からのフィードバックは、今後の研修内容を改善するための貴重な情報源です。
積極的にフィードバックを求める姿勢を示すことで、参加者も安心して意見を伝えやすくなります。
参加者への配慮を忘れない
フォローアップメールを送る際には、参加者への配慮を忘れないようにしましょう。
- 丁寧な言葉遣い: 丁寧な言葉遣いを心がけ、失礼のないようにメールを作成しましょう。
- 読みやすい文章: 長文にならないように、簡潔で読みやすい文章を心がけましょう。
- 返信しやすい構成: 参加者が返信しやすいように、メールの最後に質問や意見を求める箇所を設けましょう。
- 個別の対応: 可能であれば、参加者一人ひとりの状況に合わせて、個別のメッセージを添えると、より効果的なフォローアップになります。
これらの注意点を守り、参加者にとって有益なフォローアップメールを作成しましょう。
次は、研修効果を最大化するためのアフターフォローのコツについて解説します。
研修効果を最大化するアフターフォローのコツ

アンケートで研修効果を測定する
研修後のフォローアップで、アンケートを実施することは非常に効果的です。
アンケートを通じて、参加者の満足度や研修内容の理解度を数値で把握できます。
これにより、研修の改善点を見つけ、次回の研修に活かすことができます。
研修後アンケートのお願い例文
件名:【[研修名]】研修後のアンケートご協力のお願い
[参加者名]様
先日は[研修名]にご参加いただき、誠にありがとうございました。
今回の研修が皆様の業務にどのように役立つか、今後の研修内容をより良くするために、アンケートにご協力をお願いいたします。
ご回答は[回答期限]までにお願いいたします。
[アンケートURL]
ご多忙のところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
上記の例文のように、アンケートへの協力を依頼するメールを送りましょう。
アンケートでは、研修内容の満足度、理解度、業務への活用意欲などを尋ねる項目を設けると良いでしょう。
個別面談で理解度を深める
アンケートに加えて、個別面談を実施することも効果的なアフターフォローの方法です。
面談では、参加者一人ひとりの理解度をより深く把握できます。
また、研修内容に関する疑問や不安を解消する機会を提供することもできます。
個別面談のお願い例文
件名:【[研修名]】研修後の個別面談のご案内
[参加者名]様
先日は[研修名]にご参加いただき、誠にありがとうございました。
研修内容の理解度をさらに深めるため、個別面談を実施させていただきたくご案内いたします。
面談では、研修内容に関する疑問や業務での活用方法について、個別にご相談いただけます。
ご都合の良い日時を[選択肢]からお選びいただき、[担当者名]までご返信ください。
ご多忙のところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
個別面談では、参加者の状況に合わせて柔軟に対応することが大切です。
質問に丁寧に答えるだけでなく、具体的な事例を交えながら説明することで、参加者の理解を深めることができます。
また、面談後には、参加者ごとにフォローアップ内容を記録しておくと、今後の研修改善に役立ちます。
『代筆さん』で実現する効果的な研修後フォローアップメールの作成
参加者の学習理解を深めるフォローアップメールの重要性は理解していても、一人ひとりの状況に配慮した丁寧な文面を作成するには相応の時間を要します。
特に研修後のフォローアップメールは、参加者の理解度を確認したり業務への活用を促したりする重要な役割があるため、適切な敬語や読みやすい構成を心がけながら作成するのは意外と労力がかかるものです。
そんな時に活用したいのが、AI文章作成支援ツールの『代筆さん』です。
『代筆さん』は、「研修後のフォローアップメールを丁寧に作成したい」「理解度確認のメールを送りたい」といった要望を簡単に入力するだけで、ビジネスマナーに配慮した自然な文章を瞬時に提案してくれます。
研修後フォローアップメールを作成する際も、件名から本文、返信を促す箇所まで、一貫したトーンで整えられた文面が完成します。
研修参加者への感謝の気持ちを込めつつ、理解度確認のアンケート依頼や業務での実践を促す内容など、目的に応じた最適な表現を自動で選択してくれるのも魅力です。
また、フォーマルからカジュアルまで文体の調整も可能で、研修の内容や参加者の立場に合わせた適切なトーンのメールを作成できます。
なお、AIの提案が必ずしも完璧とは限らないため、最終的には人の手による確認が必要です。
しかし、ゼロから研修後フォローアップメールの文面を考える手間が省けることで、「参加者に本当に伝わる内容になっているか?」といった重要な確認作業に集中できるのは、大きなメリットといえるでしょう。
『代筆さん』には無料で試せるプランが用意されており、有料プランも手の届きやすい価格帯で提供されています。
研修効果を最大化するフォローアップメールを効率的に作成したい方は、ぜひ『代筆さん』の活用を検討してみてください。
まとめ:研修効果を最大化するフォローアップ戦略

研修後のフォローアップは、研修効果を最大化するために不可欠です。
- 効果的なメール作成:研修内容を参加者に思い出させ、次の行動につなげるために、わかりやすく温かみのある文章を作成します。
- 適切なフォローアップ:参加者の状況や理解度に応じて、タイミング良く必要な情報やサポートを提供します。
- 継続的な効果測定:アンケートや面談などで研修の成果を定期的に確認し、改善点を明確にします。
まずは研修内容を振り返り、具体的なアクションプランを立ててみましょう。
その際、研修の記憶が鮮明なうちに理解度を確認し、必要に応じて追加のサポートや改善策を組み込むことで、学びの定着がより確かなものになります。
また、研修後のフォローアップメールを、スムーズかつ丁寧に作成したいと感じている方は、『代筆さん』の活用がおすすめです。
件名から本文、返信依頼まで、研修内容に沿った自然な文章を短時間で整えることができ、参加者への印象アップにもつながります。
相手の立場や状況に配慮しながら、タイミングよく心のこもったメッセージを届けることで、信頼関係の構築も実現できます。
小さな積み重ねこそが、組織全体の成長を後押しする力となるでしょう。
今すぐAIでメールを作成してみよう!
伝えたいことを入力するだけで、プロ級のビジネスメールが完成します