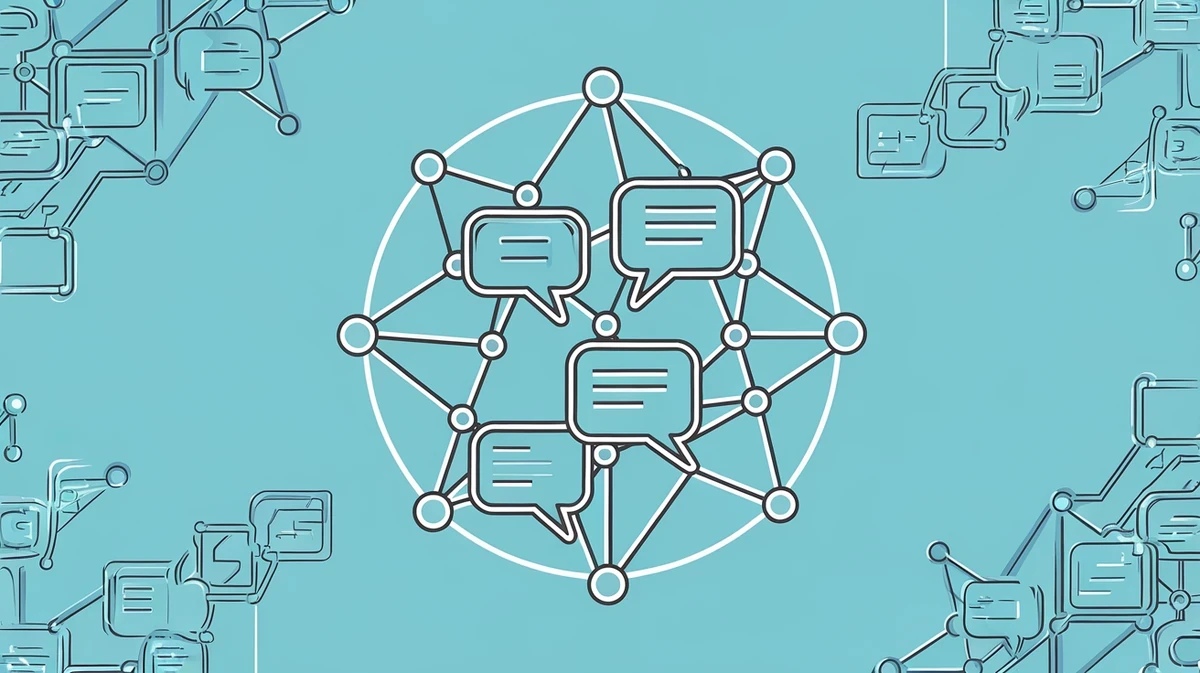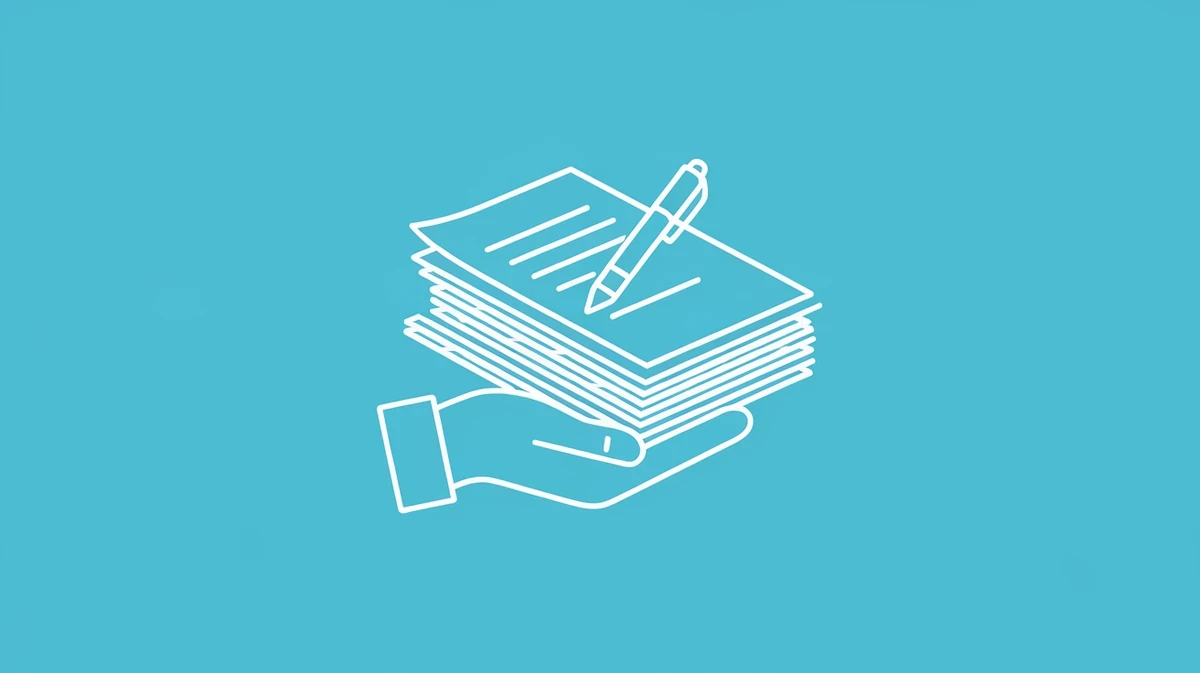件名:[商品名]に関するお詫びと再発防止策のご報告
株式会社[会社名]
[顧客名]様
いつもお世話になっております。
株式会社[会社名]、[部署名]の[担当者名]です。
先日は、弊社[商品名]において[具体的な問題点]が発生し、多大なるご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
ご指摘いただきました[具体的な問題点]につきまして、社内で詳細な原因調査を行いました結果、[原因]が判明いたしました。
今回の件では、[問題発生時の具体的な状況]において、[原因]が重なり、お客様にご不快な思いをさせてしまいましたこと、重ねてお詫び申し上げます。
つきましては、今回の事態を重く受け止め、再発防止のため、下記の通り対策を実施いたします。
- [対策1]:[具体的な対策内容]
- [対策2]:[具体的な対策内容]
- [対策3]:[具体的な対策内容]
上記対策につきましては、[具体的なスケジュール]までに完了し、進捗状況は[報告方法]にて[報告頻度]でご報告させていただきます。
今後は二度とこのようなご迷惑をおかけすることのないよう、全社をあげて改善に努めてまいります。
この度の不手際により、ご迷惑をおかけしましたこと、重ねてお詫び申し上げます。
今後とも、弊社[会社名]をよろしくお願いいたします。
[会社名]
[部署名]
[担当者名]
[連絡先]
クレーム対応、大変ですよね。
お客様からのご指摘は、私たちを成長させてくれる貴重な機会です。
ただ、対応を間違えると、お客様との信頼関係を損なう可能性も。
特に、再発防止策を報告するメールは、今後の関係を左右する重要なコミュニケーションです。
この記事では、お客様に「誠意が伝わる」報告書メールの書き方を徹底解説。
基本構成から、具体的な例文、営業担当者が知っておくべき対応のコツまで、あなたの「困った」を「安心」に変える情報が満載です。
読み終える頃には、クレーム対応が「怖いもの」ではなく、「顧客との絆を深めるチャンス」に変わるはず。
さあ、一緒に学んでいきましょう。
クレーム対応報告書メールの基本構成と重要ポイント

クレーム対応の報告書メールは、ただ事実を伝えるだけでなく、お客様の信頼を取り戻し、今後の関係を良好にするための重要なツールです。
そのため、メールの構成と各要素におけるポイントをしっかりと押さえておく必要があります。
メールに記載するべき内容
まず、メールの基本構成として、件名、宛名、お詫びと感謝の言葉、報告内容、そして今後の対応について明確に記載することが大切です。
さらに、お客様への配慮を忘れずに、丁寧かつ誠意のこもった文章を心がけましょう。
この基本構成をしっかりと守ることで、お客様からの信頼を回復し、より良い関係を築くための第一歩を踏み出せます。
では、件名と宛名の書き方について詳しく見ていきましょう。
件名と宛名の書き方:顧客に配慮した丁寧な表現
メールの件名は、お客様が最初に目にする部分です。
そのため、一目で内容が理解できるように簡潔かつ具体的に記述する必要があります。
例えば、「〇〇に関するお詫びとご報告」のように、クレームの内容とお詫びに関するメールであることが明確にわかるようにしましょう。
また、件名にはお客様を不安にさせるような表現は避け、丁寧な言葉遣いを心がけることが重要です。
次に宛名ですが、「〇〇株式会社 [顧客名]様」のように、会社名と個人名を正確に記載します。
もし、担当者が複数いる場合は、部署名も加えて、誰宛のメールかを明確にすることが大切です。
さらに、お客様の名前を間違えることのないように、送信前には必ず確認するようにしましょう。
丁寧な件名と宛名は、お客様への誠意を示す第一歩となります。
再発防止策を具体的に示す報告書メールの書き方
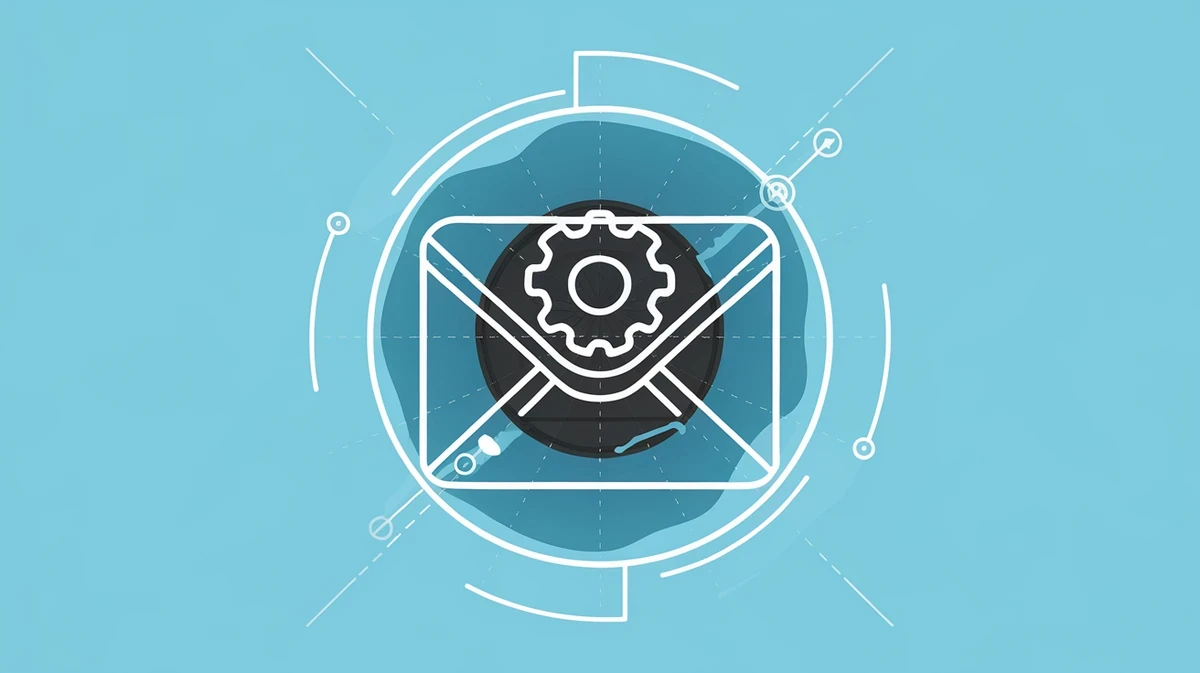
問題点の特定と原因分析:事実に基づいた客観的な記述
クレーム対応における報告書メールでは、単にお詫びを述べるだけでなく、問題点を明確にし、その原因を分析することが重要です。
顧客は、なぜ問題が発生したのか、そして今後同じことが起こらないようにどのような対策が取られるのかを知りたいと思っています。
そのため、感情的な表現は避け、事実に基づいた客観的な記述を心がけましょう。
具体的には、以下のような点に注意して記述します。
- 発生した問題の詳細を具体的に記述する
- 問題が発生した日時、場所、状況などを明確にする
- 問題の原因を特定し、なぜその原因が発生したのかを分析する
- 分析結果は、できる限り客観的なデータや証拠に基づいて記述する
例えば、
[商品名]の[具体的な問題点]について、[発生日時]に[発生場所]にて発生いたしました。
原因を調査したところ、[原因]が判明いたしました。
のように、具体的に記述することで、顧客への誠実な姿勢を示すことができます。
具体的な改善策の提示:実行可能な対策を明示
原因分析が終わったら、次に重要なのが具体的な改善策の提示です。
単に「改善に努めます」と述べるだけでなく、具体的な対策を提示することで、顧客は企業が真摯に問題に取り組んでいると理解できます。
改善策は、実行可能で、かつ効果が見込めるものを提示することが大切です。
以下に、改善策を提示する際のポイントをまとめました。
- 原因分析の結果に基づいた、具体的な改善策を提示する
- 改善策の内容は、数値目標や具体的な行動計画を伴うものが望ましい
- 改善策を実行するスケジュールを提示する
- 改善策の実施状況を定期的に報告することを約束する
例えば、
[具体的な問題点]を改善するために、[改善策1]、[改善策2]を実施いたします。
[改善策1]については[具体的なスケジュール]までに完了し、[改善策2]については[具体的なスケジュール]までに完了する予定です。
のように、具体的な改善策とスケジュールを示すことが重要です。
今後の対応方針の説明:再発防止への取り組みを示す
最後に、今後の対応方針を説明し、再発防止への取り組みを明確に示すことが重要です。
顧客は、同じ問題が二度と起こらないことを強く望んでいます。
そのため、再発防止に向けた具体的な取り組みを説明することで、顧客の不安を解消し、信頼回復につなげることができます。
具体的には、以下のような点に注意して記述します。
- 再発防止に向けた具体的な取り組みを明示する
- 今後の業務プロセスや体制の見直しについて説明する
- 従業員への教育や研修について言及する
- 定期的なモニタリングやチェック体制について言及する
例えば、
今回の件を教訓に、今後は[具体的な再発防止策]を実施し、二度とこのようなことがないように努めてまいります。
また、[今後の取り組み]についても徹底し、再発防止に努めてまいります。
のように、具体的な再発防止策を示すことが重要です。
顧客関係を改善する報告書メールの例文とテンプレート
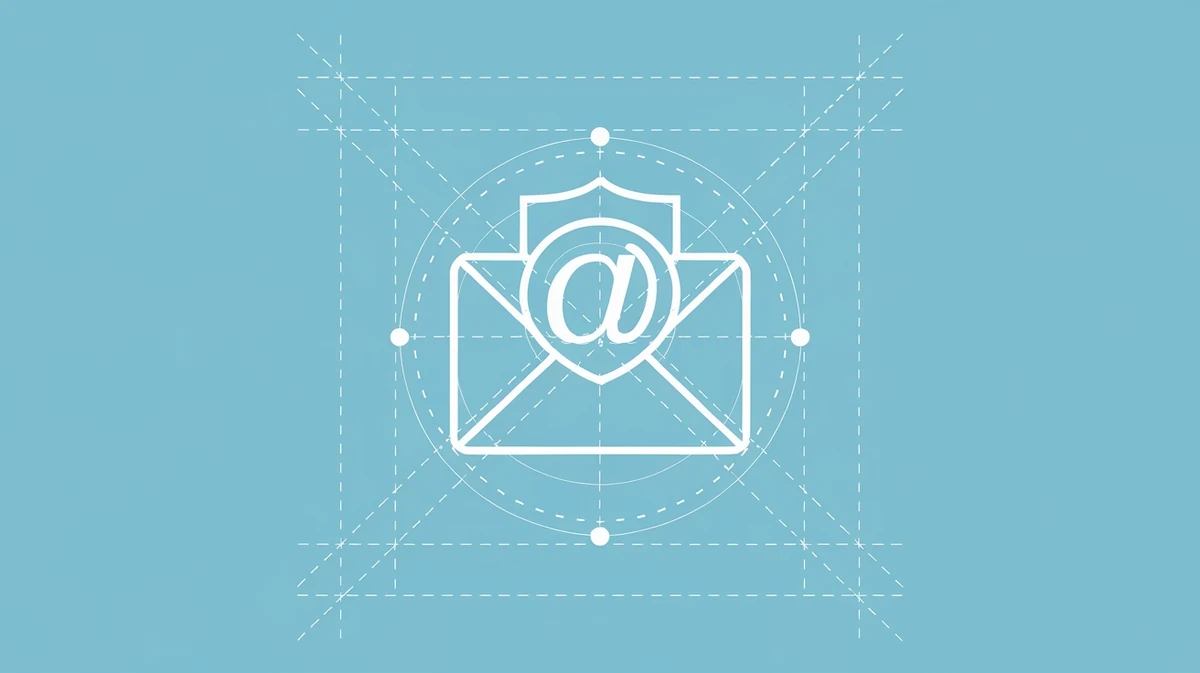
状況に応じた謝罪メールの使い分け:丁寧な文例集
クレームの内容や顧客の状況によって、謝罪メールの書き方は柔軟に変える必要があります。
ここでは、いくつかのケースを想定し、具体的な文例と使い分けのポイントを解説します。
状況に応じた適切な謝罪メールを送ることで、顧客の不満を和らげ、信頼回復へと繋げることが可能です。
例文1:軽微なミスに対する謝罪メール
件名:[商品名]に関するお詫び
[顧客名]様
平素より、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度は、[商品名]の[具体的なミス]につきまして、ご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。
今後はこのようなことがないよう、品質管理体制をより一層強化して参ります。
引き続き、弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
この例文は、軽微なミスや手違いがあった際に使用します。
迅速な謝罪と、今後の改善を約束することで、顧客の信頼を損なわないように努めましょう。
例文2:サービスに関する不手際に対する謝罪メール
件名:[サービス名]に関するお詫び
[顧客名]様
いつも[会社名]をご利用いただき、誠にありがとうございます。
先日は、[サービス名]において、[具体的な不手際]が発生し、大変ご迷惑をおかけいたしました。深くお詫び申し上げます。
ご指摘いただいた点を真摯に受け止め、サービス品質の向上に努めて参ります。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
サービスに関する不手際があった場合は、具体的な状況を説明し、謝罪の意を示すことが重要です。
顧客の不満点を理解し、改善策を講じる姿勢を示しましょう。
例文3:重大なミスに対する謝罪メール
件名:[商品名/サービス名]に関する重大なお詫び
[顧客名]様
この度は、[商品名/サービス名]に関しまして、[具体的な重大なミス]という重大な不手際がありましたこと、深くお詫び申し上げます。
お客様にご迷惑をおかけしましたこと、重ねて深くお詫び申し上げます。
今回の事態を厳粛に受け止め、再発防止に向けて全力を尽くして参ります。
今後とも、弊社をご指導ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。
重大なミスがあった場合は、誠意を込めて謝罪することが重要です。
再発防止策を具体的に提示し、顧客の信頼回復に努めましょう。
再発防止策報告メールのテンプレート:すぐに使える例文
再発防止策を報告するメールは、顧客に安心感を与えるために、具体的な内容と丁寧な言葉遣いを心がけることが大切です。
ここでは、すぐに使えるテンプレートと例文を紹介します。
例文4:再発防止策報告メールテンプレート
件名:[件名]に関する再発防止策のご報告
[顧客名]様
先日は、[具体的な問題点]に関しまして、ご迷惑をおかけしましたことを改めてお詫び申し上げます。
ご指摘いただきました[具体的な問題点]につきまして、社内で徹底的な原因究明を行いました結果、[原因分析]が判明いたしました。
つきましては、今回の事態を重く受け止め、再発防止のため下記の対策を実施いたします。
- [対策1]
- [対策2]
- [対策3]
今後は二度とこのようなご迷惑をおかけすることのないよう、全社をあげて改善に努めてまいります。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
このテンプレートは、問題点の原因分析と具体的な対策を提示する際に有効です。
顧客に安心感を与えるために、具体的な対策内容を明記しましょう。
例文5:再発防止策報告メールの例文(具体的な対策を提示)
件名:[商品名]に関する再発防止策のご報告
[顧客名]様
先日は、[商品名]の[問題点]につきまして、ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。
頂戴いたしましたご指摘に基づき、原因を調査いたしましたところ、[原因]であることが判明いたしました。
この原因を踏まえ、再発防止策として以下の対策を実施いたします。
- [商品名]の[部品名]の品質検査を強化いたします。
- 従業員への研修を徹底し、[業務内容]に関する意識向上を図ります。
- [作業工程]の見直しを行い、二重チェック体制を導入いたします。
今後とも、お客様にご満足いただける製品をお届けできるよう努めてまいります。
引き続き、弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
この例文では、具体的な商品名を挙げて、原因と対策を詳細に説明しています。
顧客の不安を解消し、信頼回復に繋がるように丁寧な説明を心がけましょう。
営業担当者が知っておくべきクレーム対応のコツ

顧客の怒りを鎮める初期対応:共感を示す重要性
クレーム対応の初期段階で最も重要なのは、顧客の怒りを鎮めることです。
お客様は不満や怒りを抱えて連絡してきているため、まずはその感情に寄り添う姿勢が大切です。
具体的には、お客様の話を遮らずに最後までしっかりと聞き、共感の言葉を伝えることから始めましょう。
「ご迷惑をおかけして申し訳ございません」といった謝罪の言葉とともに、「お気持ちお察しいたします」などの共感を示す言葉を添えることで、お客様は「自分の気持ちを理解してもらえた」と感じ、冷静さを取り戻しやすくなります。
お客様の感情を否定したり、言い訳をしたりすることは絶対に避けましょう。
まずは、お客様の気持ちを受け止め、共感を示すことが、その後の円滑な問題解決につながります。
状況の正確な把握:事実確認の徹底
お客様の怒りが少し落ち着いたら、次に重要なのは状況の正確な把握です。
クレームの内容を詳しくヒアリングし、事実関係をしっかりと確認しましょう。
お客様の話を鵜呑みにするのではなく、客観的な視点を持って、事実に基づいた原因分析を行うことが大切です。
例えば、「いつ」「どこで」「何が」起こったのかを具体的に聞き出すことが重要です。
また、お客様が提示した証拠や資料なども確認し、多角的な視点から状況を把握するように努めましょう。
曖昧な情報のまま対応を進めてしまうと、後々トラブルに発展する可能性もあるため、事実確認は徹底して行うべきです。
クレーム対応報告書で顧客との信頼関係を再構築する

クレーム対応は、顧客との信頼関係を損なうリスクがある一方で、適切に対応すれば、むしろ信頼を深めるチャンスにもなり得ます。
特に、再発防止策を盛り込んだ報告書は、その後の関係構築において重要な役割を果たします。
クレーム対応報告書で顧客に真摯な姿勢を伝える
クレーム対応報告書は、単に問題を解決したという事実を伝えるだけでなく、企業が顧客の意見を真摯に受け止め、改善に努めている姿勢を示すものです。
顧客は、自分の声がきちんと届き、それに基づいて具体的な対策が講じられたことを知ることで、企業に対する安心感と信頼感を抱きます。
報告書を作成する際には、顧客が抱いている不満や不安を理解し、共感する姿勢を示すことが大切です。
例えば、お詫びの言葉を添えるだけでなく、問題発生の原因や再発防止策を具体的に説明することで、顧客は企業が誠実に対応していると感じるでしょう。
報告書送付のタイミングも重要
また、報告書を送付するタイミングも重要です。
問題解決後、できるだけ早く報告書を送ることで、顧客は迅速な対応に満足し、企業の信頼性を高く評価するでしょう。
対応が遅れると、顧客の不満が増大し、関係悪化につながる可能性があります。
内容の注意点
報告書の内容だけでなく、文面や言葉遣いにも配慮しましょう。
丁寧で誠実な言葉を選ぶことで、顧客に良い印象を与え、関係修復につなげることができます。
また、報告書は、顧客が読みやすいように、構成を整理し、専門用語を避け、簡潔な文章で書くように心がけましょう。
さらに、報告書を送付した後も、顧客へのフォローアップを忘れずに行いましょう。
例えば、電話やメールで状況を確認したり、再発防止策の実施状況を定期的に報告したりすることで、顧客は企業が継続的に努力していることを感じ、信頼関係がより強固になるでしょう。
『代筆さん』でクレームの再発防止策メールもスムーズに
再発防止策を明確に伝えることの重要性は理解していても、原因分析や改善内容を適切な言葉に落とし込むには相応の時間と配慮が求められます。
特に、クレーム対応後の報告書やメールでは、誠意ある表現や相手への気遣いが欠かせません。
そこで役立つのが、AI文章作成支援ツール『代筆さん』です。
伝えたい内容を簡単な言葉で指示するだけで、ビジネスマナーを踏まえた丁寧な文面を、AIがスピーディーに生成してくれます。
再発防止策の説明文や謝罪表現など、書き慣れない文面でも安心して作成に取り組むことが可能です。
『代筆さん』には、社内規定や業務用語を事前登録できる機能もあり、自社に合った文面を自動で提案してくれます。
文体の調整もワンクリックで対応できるため、相手や場面に合わせた表現に迷う時間を大幅に削減できます。
さらに、よく使う定型文を保存しておけば、次回からは数クリックで呼び出して再利用できるのも大きな魅力です。
もちろん、AIによる提案が常に完ぺきとは限りませんので、最終的にはご自身の目で確認し、必要に応じて調整することが前提となります。
しかし、クレームの原因や再発防止策を一から文章化する負担が軽減されることで、謝罪文の質を保ちつつ迅速な対応が可能になります。
『代筆さん』は無料プランで手軽に始められるうえ、有料プランも比較的低価格なので、業務負担の軽減に向けて導入しやすいのもポイントです。
誠実さを大切にしながらも、効率よく対応したい方にとって、『代筆さん』は心強いサポート役となるでしょう。
まとめ:再発防止策の報告で顧客満足度を高めるために

クレーム対応後の信頼回復を実現するためには、報告書メールにおいて誠意と具体性の両立が欠かせません。
- 事実に基づいた原因分析と具体的な改善策の提示
- 顧客への誠意ある謝罪と感謝の表明
- 再発防止に向けた具体的な取り組みの説明
これらの要素をしっかりと報告書に盛り込むことで、顧客からの信頼回復に繋げることができます。
さらに、顧客満足度を向上させるために、報告書を送る際には、まずお電話で直接お詫びの気持ちを伝え、報告書の内容を簡単に説明することを心がけてみてください。
そうすることで、メールだけでは伝わりにくい誠意や熱意をより効果的に伝えられるでしょう。
「クレーム対応をどのように行ったか、上手くまとめられない」「再発防止策をどう伝えれば納得してもらえるのか分からない」とお悩みの方は、『代筆さん』の活用を検討してみてください。
伝えたい情報を入力するだけで、謝罪文や改善策の説明を、相手に伝わりやすいビジネス文書として整えてくれます。
丁寧で一貫性のある対応を続けることが、信頼の再構築につながります。
たとえ一度ミスがあったとしても、真摯な姿勢で向き合えば、顧客との関係はより強固なものになるはずです。
より良い顧客関係を築き、ビジネスをさらに発展させていきましょう。
今すぐAIでメールを作成してみよう!
伝えたいことを入力するだけで、プロ級のビジネスメールが完成します