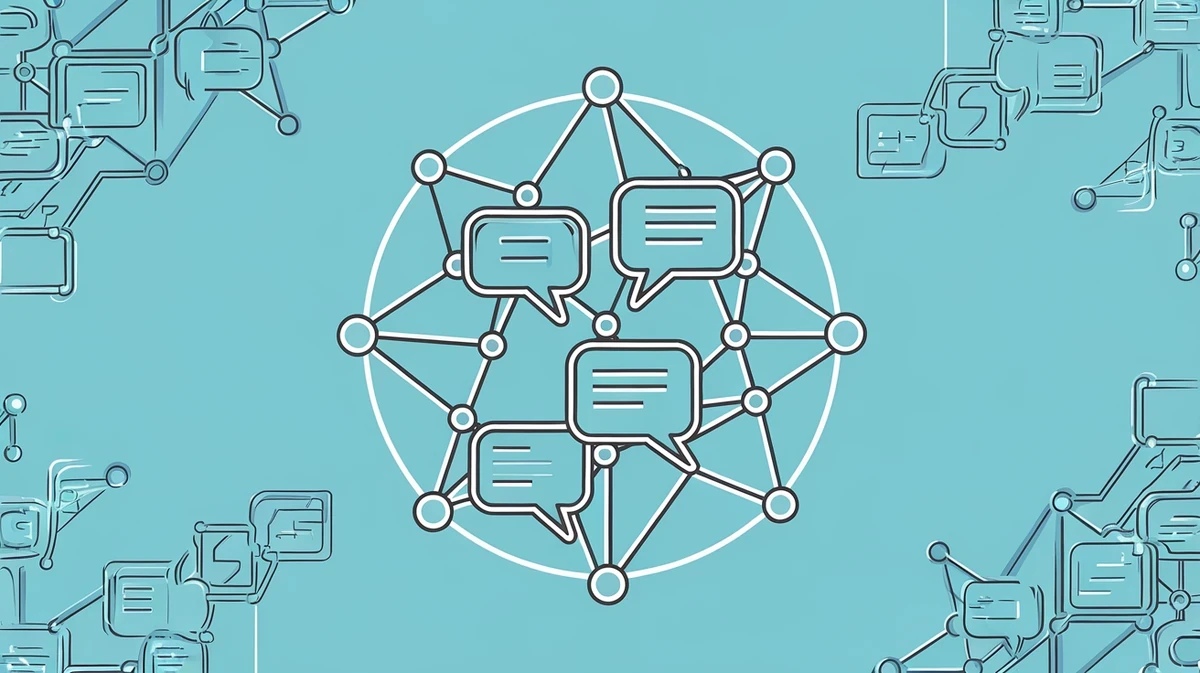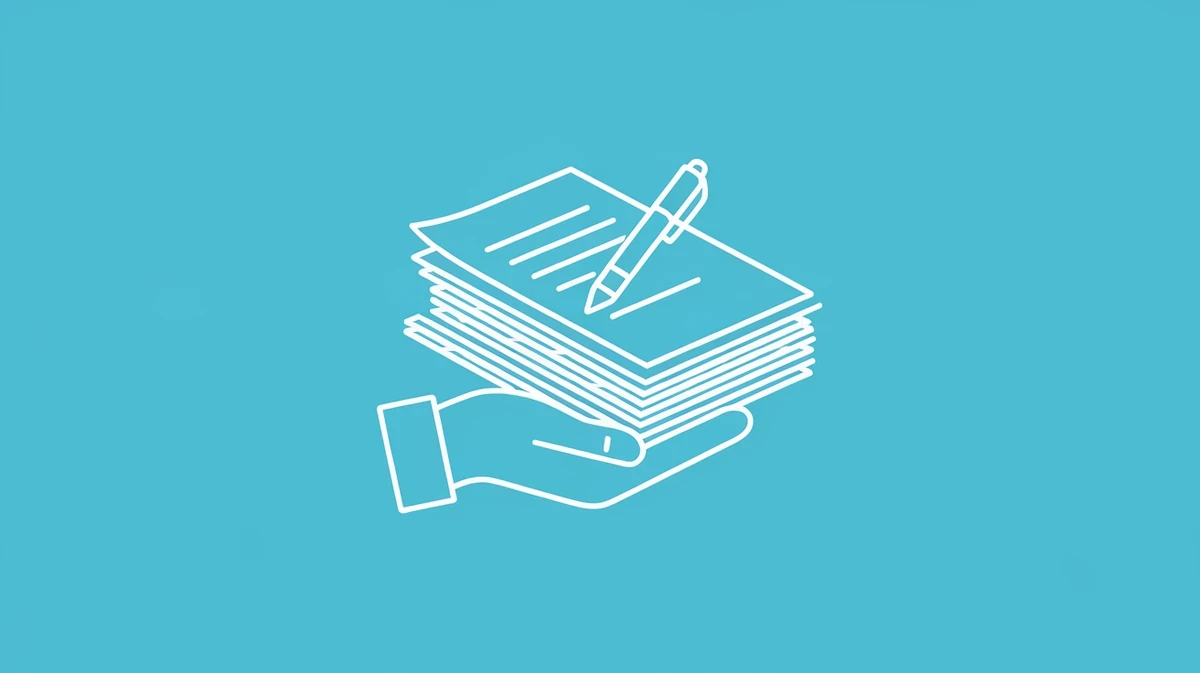件名:退職のご連絡と手続きに関するご案内
株式会社[会社名]
[部署名] [役職] [氏名]様
お世話になっております。
[会社名]、[部署名]の[名前]です。
この度、一身上の都合により、誠に勝手ながら、[退職希望日]をもちまして退職させていただきたく、ご連絡いたしました。
在職中は大変お世話になり、心より感謝申し上げます。
つきましては、[退職希望日]を退職希望日とし、最終出勤日は[最終出勤日]とさせていただきたく、お願い申し上げます。
退職までの間、残された業務を精一杯努めさせていただきます。
後任への引き継ぎなど、ご指示いただけましたら幸いです。
退職にあたり、以下の点についてご案内いたします。
- 退職届のご提出について
退職届のご提出方法については、別途ご指示をいただければ幸いです。
提出期限や提出先について、ご教示いただけますと助かります。 2. 必要書類について
退職手続きに必要な書類(雇用保険被保険者証、年金手帳、源泉徴収票、離職票など)について、
受け取り方法や時期について、改めてご案内いただければ幸いです。
また、提出が必要な書類についても併せてご指示ください。 3. 返却物について
会社から貸与されているもの(社員証、健康保険証、社用PCなど)の返却方法について、
別途ご指示いただければ幸いです。
退職日まで短い期間ではございますが、責任をもって業務に取り組む所存です。
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
[名前]
退職って、なんだかちょっと寂しいけど、新しいスタートへのワクワクもいっぱいですよね。
でも、退職の手続きって、何から始めたらいいかちょっと迷うことも。
そんなときは、この記事を参考にメールで連絡することからはじめてみませんか?
今回は、退職手続きをスムーズに進めるためのメール作成のコツを、ステップごとにご紹介します。
退職メールの基本から、必要な書類、返却物、スケジュールまで、退職に関するあらゆる疑問がスッキリ解決。
ぜひ最後まで読んで、あなたの退職を最高の形で締めくくりましょう。
退職手続きメールの基本構成と必須項目3つのポイント

退職の意思を伝えるメールは、あなたの会社での最後の印象を左右するとっても大切なもの。
だからこそ、基本をしっかり押さえて、失礼のない、かつスムーズな退職につなげたいですよね。
ここでは、退職手続きメールの基本構成と、必ず含めるべき必須項目について解説します。
これを読めば、もうメール作成で悩むことはありません。
1. 件名と宛名の書き方
まずはメールの顔となる「件名」と「宛名」から。
件名は、一目で内容がわかるように簡潔に書くのがポイントです。
「退職のご連絡」や「退職のご挨拶」のように、ストレートに伝えるのがおすすめです。
宛名は、会社の上司や人事担当者など、誰に送るのかをしっかり確認しましょう。
役職名も忘れずに記入してくださいね。
例文 件名と宛名
件名:退職のご連絡
[部署名] [役職] [氏名]様
この例文では、件名で「退職のご連絡」とストレートに伝え、宛名では部署名、役職、氏名を明記することで、誰宛のメールか一目でわかるようにしています。
宛名は、通常、会社の上長や人事担当者など、退職手続きを進める上で重要な役割を担う人に送ります。
誰に送るべきか迷う場合は、事前に上司に確認しましょう。
2. 退職の意思を明確に伝える
メールの冒頭では、退職の意思をはっきりと伝えましょう。
「退職したいと考えております」のように、曖昧な表現は避けて、「退職させていただきます」と断定的な表現を使うのがおすすめです。
退職の意思を伝える際は、感謝の気持ちを添えると、より丁寧な印象になります。
例文 退職の意思を伝える
[宛先]様
いつもお世話になっております。[氏名]です。
この度、一身上の都合により、誠に勝手ながら、[退職希望日]をもちまして退職させていただきたく、ご連絡いたしました。
在職中は大変お世話になり、心より感謝申し上げます。
この例文では、退職の意思を明確に伝えるとともに、日頃の感謝の気持ちを伝えています。
退職の理由を具体的に書く必要はありませんが、「一身上の都合」と記載しておくと丁寧です。
退職の意思を伝える際は、簡潔に、かつ明確に伝えることが大切です。
長々と書くと、かえって伝わりにくくなることがあります。
感謝の気持ちを添えることで、円満な退職につながるでしょう。
3. 退職希望日と最終出勤日の明記
退職希望日と最終出勤日は、会社との調整が必要な重要な情報です。
就業規則を確認し、退職希望日の〇ヶ月前までに申し出る必要があるかを確認しましょう。
メールには、希望する退職日と、実際に会社で仕事をする最後の日を明確に記載します。
例文 退職希望日と最終出勤日
つきましては、[退職希望日]を退職希望日とし、最終出勤日は[最終出勤日]とさせていただきたく、お願い申し上げます。
退職までの間、残された業務を精一杯努めさせていただきます。
後任への引き継ぎなど、ご指示いただけましたら幸いです。
この例文では、退職希望日と最終出勤日を明確に記載し、退職までの業務への責任感を示しています。
また、後任への引き継ぎについても触れ、円滑な退職を目指す姿勢を表しています。
退職希望日と最終出勤日を伝える際は、具体的な日付を明記することが重要です。
また、退職までの期間、責任を持って業務に取り組む姿勢を示すことで、会社からの信頼を得ることができます。
退職手続きに必要な書類と提出方法

退職の意思が固まったら、次は具体的な手続きを進める必要があります。
このセクションでは、退職に必要な書類とその提出方法について詳しく解説します。
スムーズな退職のために、必要な情報をしっかりと確認しましょう。
退職届の提出方法と注意点
退職の意思を会社に正式に伝えるための書類が退職届です。
多くの場合、退職日の1ヶ月前、遅くとも2週間前には提出することが推奨されます。
提出期限は会社の就業規則によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
退職届の提出方法に関するメール例文
退職届の提出方法を問い合わせる際のメール例文です。
人事担当者や直属の上司に、提出先や提出方法を確認する際に利用できます。
件名:退職届の提出について
[人事担当者名]様
お世話になっております。[氏名]です。
先日は退職の意思をお伝えいたしましたが、退職届の提出方法について確認させて頂きたく、ご連絡いたしました。
退職届は、どちらにご提出すればよろしいでしょうか。また、提出期限についても併せてご教示頂けますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
退職届は、書面で提出するのが一般的です。
手書きでもパソコンで作成しても構いませんが、会社の規定がある場合はそれに従いましょう。
退職届には、退職日、所属部署、氏名などを記載します。
提出前にコピーを取り、自身でも保管しておくと良いでしょう。
また、退職届を提出する際には、上司に直接手渡すのが基本です。
もし、上司が不在の場合は、人事担当者に提出しても問題ありません。
その際には、必ず提出した証拠として、受領印を押してもらうか、控えを受け取るようにしましょう。
その他必要書類一覧と入手先
退職手続きには、退職届以外にも必要な書類があります。
これらの書類は、退職後の手続きや生活に大きく関わってくるため、忘れずに準備しましょう。
雇用保険被保険者証
雇用保険に加入していることを証明する書類です。
ハローワークでの手続きに必要になります。
通常、会社から渡されますが、紛失した場合は再発行の手続きが必要です。
年金手帳
年金に関する重要な書類です。
国民年金や厚生年金の手続きに必要になります。
退職後、自分で保管する必要があります。
源泉徴収票
1年間の所得を証明する書類です。
確定申告や転職先の年末調整に必要になります。
退職後、1ヶ月以内に会社から送付されます。
離職票
雇用保険の失業給付を受ける際に必要な書類です。
会社がハローワークに手続きを行い、後日郵送されます。
これらの書類は、退職手続きを進める上で非常に重要です。
紛失したり、手続きが遅れたりすると、必要な給付が受けられない可能性もあります。
書類が揃っているか、不備はないか、必ず確認するようにしましょう。
もし、書類の入手方法や手続きについて不明な点があれば、人事担当者に問い合わせましょう。
書類提出時の確認事項
書類を提出する際には、いくつかの注意点があります。
スムーズに手続きを進めるために、以下の点を確認しましょう。
提出期限
各書類には提出期限が定められている場合があります。
期限を過ぎると手続きが遅れる可能性があるため、早めに提出しましょう。
提出先
書類によって提出先が異なる場合があります。
人事部、総務部など、指定された部署に提出しましょう。
記載内容の確認
誤った情報や不備があると、手続きが滞る可能性があります。
提出前に記載内容をよく確認しましょう。
控えの保管
提出した書類の控えは、念のため保管しておきましょう。
後日、問い合わせや確認が必要になる場合に役立ちます。
書類提出時の確認事項に関するメール例文
書類提出時の確認事項に関するメール例文です。
提出書類の確認や提出方法について、担当者に問い合わせる際に利用できます。
件名:退職手続きに関する書類提出について
[人事担当者名]様
お世話になっております。[氏名]です。
先日は退職のご連絡ありがとうございました。
退職手続きに必要な書類についてですが、提出期限と提出先について改めて確認させてください。
また、記載内容や提出書類について何か注意すべき点があれば、ご教示頂けますでしょうか。
お忙しいところ大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
これらの確認事項をしっかりと把握し、準備を万全に整えてから書類を提出しましょう。
不明な点は必ず人事担当者に問い合わせ、スムーズな退職手続きを目指しましょう。
次の見出しでは、退職に伴う返却物と受取物について解説します。
退職に伴う返却物と受取物リスト

会社へ返却するもの
退職時には、会社から貸与されていたものを返却する必要があります。
返却物は、会社の資産であるため、忘れずに返却しましょう。
以下に、一般的な返却物のリストを記載します。
- 社員証
- 健康保険証
- 社章
- 会社のパソコンやスマートフォン
- 社用車や鍵
- 制服や作業着
- 業務に関する書類やデータ
- その他会社から貸与されたもの
返却物のリストは会社によって異なる場合があります。
退職前に人事担当者や上司に確認し、リストに漏れがないようにしましょう。
返却時には、返却リストを作成し、双方で確認するとスムーズです。
返却漏れがあると、後日連絡が来て、対応が必要になる場合があります。
退職の手続きをスムーズに進めるためにも、返却物の確認は確実に行いましょう。
会社から受け取るもの
退職時には、会社から受け取るものもいくつかあります。
これらの書類は、退職後の手続きや生活に必要になるため、必ず受け取るようにしましょう。
以下に、一般的な受取物のリストを記載します。
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
- 退職証明書
- 給与明細(最終月分)
- その他会社から支給される書類
これらの書類は、退職後の生活や再就職に必要になる重要なものです。
受け取り漏れがないよう、必ず人事担当者や上司に確認しましょう。
退職後に書類が送付される場合は、送付先住所を間違えないように注意してください。
また、書類の内容に不明な点があれば、必ず会社に問い合わせましょう。
受け取る書類についても、リストを作成して、漏れがないかチェックすると確実です。
退職までのスケジュールと引き継ぎのポイント

退職日までの具体的なスケジュール例
退職の意思を伝えたら、退職日までのスケジュールを立てましょう。
まず、会社規定の退職日を必ず確認してください。
一般的には、退職希望日の1ヶ月前には申し出る必要があります。
余裕をもって行動することが大切です。
以下に具体的なスケジュール例を紹介します。
1. 退職意思の伝達
退職希望日の1ヶ月~2ヶ月前に、直属の上司に退職の意思を伝えます。
口頭で伝えるのが基本ですが、後日メールで伝える場合もあります。
2. 退職日の決定
上司と相談し、最終的な退職日を決定します。
引き継ぎ期間なども考慮して、無理のないスケジュールを組みましょう。
3. 退職届の提出
会社の規定に従い、退職届を提出します。
提出期限や提出先を必ず確認しましょう。
4. 業務の引き継ぎ準備
後任者への引き継ぎ資料を作成します。
引き継ぎ期間を考慮して、計画的に準備を進めましょう。
5. 引き継ぎの実施
後任者に対し、業務内容や進捗状況を丁寧に説明します。
質疑応答の時間を設け、疑問点を解消しましょう。
6. 最終出勤日の挨拶
お世話になった方々に感謝の気持ちを伝えましょう。
退職後も良好な関係を築けるように、丁寧に挨拶をしましょう。
業務引継ぎを円滑に進めるコツ
業務引継ぎは、後任者がスムーズに業務を遂行できるように行う必要があります。
以下のポイントを参考に、引継ぎを行いましょう。
引継ぎ資料の作成
業務内容、手順、注意点などをまとめた資料を作成します。
口頭だけでなく、文章で残すことで、後任者の理解を助けます。
過去の資料も合わせて渡すと、より理解が深まります。
引継ぎ期間の設定
後任者が十分に理解できるよう、余裕を持った期間を設定しましょう。
引継ぎ期間中は、後任者の質問に丁寧に対応しましょう。
担当者とのコミュニケーション
後任者と密にコミュニケーションを取り、進捗状況を共有します。
疑問点や不安な点を早期に解消できるように努めましょう。
定期的に進捗状況を確認する時間を設けましょう。
引継ぎ後のフォロー
退職後も、しばらくの間は後任者のサポートをすると良いでしょう。
連絡先を伝えておくと、安心して業務に取り組めます。
退職後も協力的な姿勢を見せることが大切です。
最終出勤日の挨拶について
最終出勤日は、お世話になった方々へ感謝の気持ちを伝える大切な日です。
以下の点を参考に、気持ちの良い挨拶をしましょう。
挨拶のタイミング
退社時間前に、部署全体、または関係者へ挨拶をします。
業務時間中に挨拶する場合は、業務の妨げにならないように配慮しましょう。
挨拶のタイミングは、企業の文化や部署の慣習を考慮しましょう。
挨拶の内容
感謝の気持ち、在籍中の思い出、今後の抱負などを簡潔に伝えます。
個人的な感情ではなく、感謝の気持ちを伝えることが重要です。
職場への感謝の言葉を添え、円満な退職を心がけましょう。
挨拶の形式
全体への挨拶は、朝礼や終礼の時間を活用すると良いでしょう。
個別の挨拶は、直接会って伝えるのが基本です。
メールで挨拶する場合は、感謝の気持ちを丁寧に伝えましょう。
退職後の連絡先を伝えておくと、良好な関係を維持できます。
『代筆さん』でスピーディーに退職手続きメールを作成
退職に関する連絡メールでは、感謝の気持ちや必要事項を過不足なく伝えることが大切だと理解していても、文面を整えるには相応の時間と配慮が必要です。
とくに、敬語の使い分けや文脈の自然さに自信が持てない場合、メールの作成に思いのほか時間がかかってしまうこともあります。
そんなときに活用したいのが、AI文章作成支援ツール『代筆さん』です。
『代筆さん』は、伝えたい内容を簡単な言葉で入力するだけで、退職連絡のような繊細な場面でも失礼のない自然な文面を提案してくれます。
退職希望日や返却物、必要書類の確認といった複数の要素を、読みやすい構成にまとめるのも得意です。
さらに、『代筆さん』にはフォーマルな文体への自動変換機能や、よく使う定型文を登録してワンクリックで呼び出せる便利な機能も搭載されています。
これにより、繰り返し発生する社内外への連絡もスムーズに対応できるようになります。
もちろん、AIが生成する文章は必ずしも完ぺきではありません。
最終的な文面はご自身の目で確認し、必要に応じて調整することが前提ですが、ゼロから一文ずつ考える手間が大幅に軽減されるのは大きなメリットです。
『代筆さん』には無料プランもあり、まずは気軽に試すことが可能です。
業務量や利用頻度に応じて、比較的安価な有料プランへ移行することもできるため、導入のハードルも低めです。
退職メールの作成で手が止まってしまったときは、『代筆さん』を使ってみるのも有効な手段となるでしょう。
まとめ:スムーズな退職手続きを実現するために

退職時のメール対応を丁寧に行うことは、最後まで信頼を保ち、円満な退職につなげるための大切なステップです。
- 退職の意思を明確に伝える
- 退職希望日と最終出勤日を明記する
- 必要な書類と提出方法を確認する
これらのポイントを押さえ、退職手続きメールを作成することで、会社とのやり取りを円滑に進めることができます。
退職の手続きは、人によっては少し複雑に感じるかもしれません。
しかし、焦らず一つずつ確認することで、必ずスムーズに進めることができます。
もし、退職に関するメールの文面をどう書けばよいか迷っている方は、『代筆さん』の活用を検討してみてください。
伝えたい内容を入力するだけで、丁寧でわかりやすい退職手続きメールを素早く作成できます。
退職という新たなスタートを、気持ちよく迎えるための第一歩です。
あなたの次のステージでのご活躍を応援しています。
今すぐAIでメールを作成してみよう!
伝えたいことを入力するだけで、プロ級のビジネスメールが完成します