
プロジェクトリスク報告メール3つのポイントと例文・テンプレート
 AIメール作成ツール 代筆さん
2025-07-01
AIメール作成ツール 代筆さん
2025-07-01
件名:【[プロジェクト名]】[システム名]におけるシステム障害発生のご報告
株式会社[会社名]
[宛名]様
お世話になっております。
[会社名]、[部署名]の[名前]です。
この度、[プロジェクト名]において、[システム名]でシステム障害が発生しましたことをご報告いたします。
発生日時:[発生日時]
発生場所:[システム名]
障害内容:[具体的な障害内容]
影響範囲:[影響範囲]
現状:
現在、[復旧担当者]が中心となり、[復旧作業内容]を進めております。
進捗があり次第、改めてご報告いたします。
今後の対応:
再発防止のため、[対策内容]を検討しております。
ご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
プロジェクトのピンチをチャンスに変える。
リスク報告メールの書き方、教えます。
「プロジェクト、順調に進んでる。」と思っていても、急なトラブルはつきものですよね。
そんな時、焦らず、冷静に関係者へ状況を伝え、解決へと導くのが、リスク報告メールの腕の見せ所です。
この記事では、リスク報告メールを書く前に確認すべきポイントから、具体的な書き方、注意点、そして効率化のためのテンプレート活用まで、あなたのプロジェクトを成功に導くためのノウハウをギュッと詰め込みました。
この記事を読めば、もうリスク発生時にも慌てることはありません。
具体的なステップと例文で、あなたも今日からリスク報告を的確に行えるようになりますよ。
さあ、一緒に見ていきましょう。
リスク報告メールを書く前に確認すべき3つのポイント

報告メールの目的を明確にする
リスク報告メールを書く前に、まず「なぜこのメールを書くのか?」という目的をはっきりさせましょう。
目的が曖昧だと、メールの内容もぼやけてしまい、相手に正確な情報が伝わりません。
「状況を共有する」「迅速な対応を求める」「意思決定を促す」など、具体的な目的を定めることで、メールの方向性が定まります。
目的を定めることで、誰に、何を、どのように伝えたいのかが明確になり、より効果的なリスク報告メールを作成できます。
報告メールの目的例
- プロジェクトの遅延を報告し、追加リソースの必要性を訴える。
- 発生した技術的な問題を共有し、専門家の意見を求める。
- 予算超過の見込みを伝え、予算の見直しを検討してもらう。
関係者への迅速な共有体制を整える
リスクが発生した際、誰に、いつ、どのように報告するかを事前に決めておくことが大切です。
関係者への情報共有が遅れると、問題が深刻化する恐れがあります。
そのため、リスク発生時の報告フローを明確にし、担当者や連絡先をリスト化しておきましょう。
関係者全員が迅速に情報を共有できる体制を整えることで、早期の問題解決につながります。
情報共有体制例
- プロジェクトマネージャー:リスク発生状況の全体把握と関係者への情報伝達
- チームリーダー:チーム内での情報共有と対策立案
- 担当者:詳細な状況報告と具体的な対策実行
リスクの程度と影響範囲を把握する
リスク報告メールを作成する上で、リスクの程度と影響範囲を正確に把握することも非常に重要です。
リスクがプロジェクト全体に及ぼす影響を正しく評価することで、必要な対策を講じることができます。
リスクの程度を「高・中・低」の3段階で評価したり、影響範囲を「スケジュール」「コスト」「品質」など具体的に示すことで、関係者へリスクの深刻さを的確に伝えることができます。
リスク評価の例
リスクの程度
- 高:プロジェクトの成否に直接影響する可能性が高い
- 中:プロジェクトに遅延やコスト増の可能性がある
- 低:プロジェクトへの影響は小さい
影響範囲
- スケジュール:納期遅延の可能性
- コスト:予算超過の可能性
- 品質:成果物の品質低下の可能性
- その他:関係者への影響など
プロジェクトリスク報告メールの基本構成と書き方

プロジェクトのリスクを報告するメールは、迅速かつ正確な情報伝達が不可欠です。
ここでは、効果的なリスク報告メールを作成するための基本構成と書き方について解説します。
件名、本文、今後の対応策という3つの要素に分け、具体的なポイントを見ていきましょう。
件名でリスク内容を簡潔に伝える
メールの件名は、受信者が内容を瞬時に把握するために非常に重要です。
リスクの内容を具体的に、かつ簡潔に記述することで、メールの優先度を判断しやすくします。
例えば、「【〇〇プロジェクト】システム障害発生のお知らせ」のように、プロジェクト名とリスクの種類を明記しましょう。
例文1:システム障害発生の報告
件名:【[プロジェクト名]】[システム名]システム障害発生のお知らせ
[関係者]様
いつもお世話になっております。[あなたの名前]です。
〇月〇日〇時頃より、[システム名]においてシステム障害が発生しております。
現在、原因を調査中です。進捗があり次第、改めてご報告いたします。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
この例文では、件名にプロジェクト名、システム名、そしてシステム障害というリスクの内容を明確に記述しています。
これにより、受信者はメールを開封する前に、どのようなリスクが発生しているのかを把握できます。
例文2:納期遅延の可能性報告
件名:【[プロジェクト名]】[タスク名] 納期遅延の可能性について
[関係者]様
いつもお世話になっております。[あなたの名前]です。
現在、[タスク名]の進捗に遅れが生じており、納期遅延の可能性が出てきました。
詳細については、今後の進捗状況を見ながら、改めてご報告いたします。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
この例文では、納期遅延の可能性というリスクを件名で伝え、受信者に状況を認識させることができます。
具体的なタスク名を記述することで、より詳細な情報を伝えられます。
本文でリスク発生状況と影響を具体的に記述する
メールの本文では、リスクが発生した状況とその影響を具体的に記述する必要があります。
いつ、どこで、何が起こったのかを明確に伝え、リスクがプロジェクトにどのような影響を与えるかを具体的に説明しましょう。
例文3:システム障害の詳細報告
件名:【[プロジェクト名]】[システム名]システム障害発生のお知らせ
[関係者]様
いつもお世話になっております。[あなたの名前]です。
先ほどご報告しましたシステム障害について、詳細を報告します。
〇月〇日〇時頃、[システム名]において、[具体的な障害内容]が発生しました。
現在、[影響範囲]に影響が出ており、[業務内容]に支障が出ています。
現在、復旧作業を行っており、進捗があり次第、改めてご報告いたします。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
この例文では、システム障害が発生した日時、具体的な障害内容、影響範囲、そして業務への支障を明確に記述しています。
これにより、受信者はリスクの深刻さを理解しやすくなります。
例文4:納期遅延の詳細報告
件名:【[プロジェクト名]】[タスク名] 納期遅延の可能性について
[関係者]様
いつもお世話になっております。[あなたの名前]です。
先にご連絡しました[タスク名]の遅延の可能性について、詳細を報告します。
現在、[遅延理由]により、[タスク名]の進捗が遅れており、[具体的な影響]が出ています。
このままでは、[納期]までに完了することが難しい状況です。
今後の対応については、別途ご相談させてください。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
この例文では、遅延の理由、具体的な影響、そして納期への影響を明確に記述しています。
これにより、受信者はリスクの全体像を把握し、適切な対応を検討することができます。
今後の対応と対策案を提示する
リスクを報告するメールでは、今後の対応と対策案を提示することが重要です。
どのような対応をとるのか、どのようにリスクを軽減するのかを具体的に示しましょう。
これにより、関係者は安心感を得られ、協力体制を築きやすくなります。
例文5:システム障害の復旧対応策
件名:【[プロジェクト名]】[システム名]システム障害発生のお知らせ
[関係者]様
いつもお世話になっております。[あなたの名前]です。
先にご報告したシステム障害について、今後の対応策をお知らせします。
現在、[復旧担当者]が中心となり、[復旧作業内容]を進めております。
また、再発防止のため、[対策内容]を検討しております。
進捗状況については、随時ご報告いたします。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
この例文では、誰が復旧作業を担当しているのか、どのような作業が行われているのか、そして再発防止策について明確に記述しています。
これにより、受信者は今後の対応策を把握し、安心感を得ることができます。
例文6:納期遅延の対策案
件名:【[プロジェクト名]】[タスク名] 納期遅延の可能性について
[関係者]様
いつもお世話になっております。[あなたの名前]です。
先にご報告した[タスク名]の遅延の可能性について、今後の対策案を提案します。
現在、[対策内容1]を実施しており、[対策内容2]も検討中です。
また、[関係部署]と連携し、[協力内容]を進めております。
納期遅延を最小限に抑えるため、尽力いたします。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
この例文では、具体的な対策案、関係部署との連携、そして納期遅延を最小限に抑えるための努力を明記しています。
これにより、受信者は今後の対策を把握し、プロジェクトの進捗に対する不安を軽減できます。
リスク報告メールで避けるべき5つの注意点
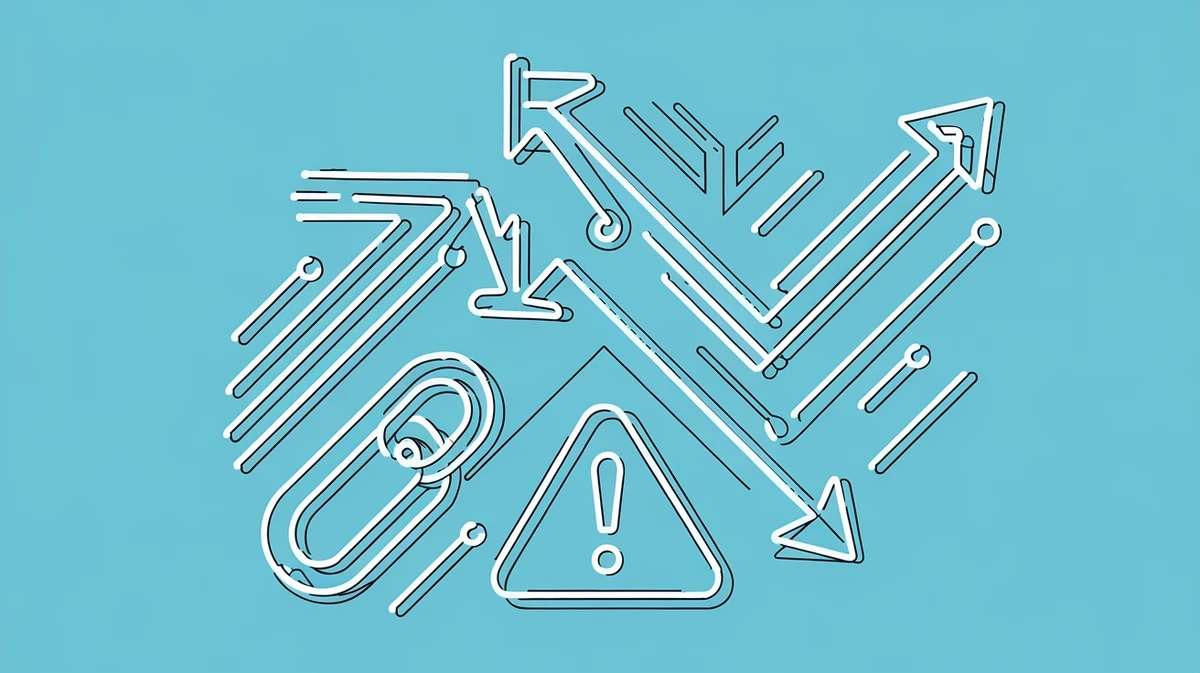
リスク報告メールは、プロジェクトの円滑な進行のために不可欠なコミュニケーション手段です。
しかし、不適切な表現や内容が含まれていると、誤解を招いたり、対応が遅れる原因にもなりかねません。
ここでは、リスク報告メールを作成する際に特に注意すべき5つのポイントについて解説します。
感情的な表現は避ける
リスクが発生した状況下では、焦りや不安を感じるのは自然なことです。
しかし、報告メールに感情的な表現を用いるのは避けましょう。
個人的な感情や不満をメールに書き込むと、客観性が失われ、冷静な判断を妨げる可能性があります。
事実を淡々と伝えることを心がけ、落ち着いた文面で報告することが重要です。
例文:感情的な表現の悪い例
件名:【至急】[プロジェクト名]における重大な遅延発生について
[担当者名]様
大変申し訳ございません!またしても[問題点]が発生し、プロジェクトが完全にストップしてしまいました!
このままでは、納期に間に合わないことは明白です。一体どうすれば良いのでしょうか!
責任者として、非常に頭を抱えています。
至急、対応策を指示してください。
この例では、「申し訳ございません」「頭を抱えています」など、感情的な言葉が多用されています。
また、「一体どうすれば良いのでしょうか。」といった責任転嫁とも取れる表現は避けるべきです。
例文:感情的な表現を避けた良い例
件名:【[プロジェクト名]】[問題点]発生による遅延の可能性について
[担当者名]様
[プロジェクト名]において、[問題点]が発生し、[具体的な状況]となっているため、[納期]への影響が懸念されます。
現在、[対応策]を検討しており、[期日]までには詳細な対応計画をご報告いたします。
何かご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
こちらの例では、事実に基づいた状況説明を行い、冷静かつ客観的なトーンで記述しています。
責任の所在を曖昧にしない
リスク報告メールでは、誰が、いつ、何をしたのかを明確に記述する必要があります。
責任の所在を曖昧にすると、問題解決の遅延や、関係者間の不信感につながる可能性があります。
「誰かが」「何かのせいで」といったあいまいな表現は避け、具体的な担当者や行動を記載するようにしましょう。
例文:責任の所在が曖昧な悪い例
件名:[プロジェクト名]の遅延について
[担当者名]様
[プロジェクト名]の作業が遅れています。
何らかの理由で、[タスク名]の進捗が大幅に遅れており、納期に間に合わない可能性があります。
原因を調査し、対応策を検討します。
この例では、誰が遅延の原因を作ったのか、具体的な状況が不明確です。
「何らかの理由」といった曖昧な表現は、責任の所在を不明確にしてしまいます。
例文:責任の所在を明確にした良い例
件名:[プロジェクト名]における[タスク名]遅延のご報告
[担当者名]様
[プロジェクト名]の[タスク名]において、[担当者名]の担当範囲で、[具体的な理由]により遅延が発生しております。
[具体的な影響]が発生しており、[納期]に影響する可能性がございます。
現在、[担当者名]と協力し、[対応策]を検討しております。
この例では、具体的な担当者名と遅延理由を明記することで、責任の所在を明確にしています。
事実と推測を区別する
リスク報告メールでは、事実と推測を明確に区別することが重要です。
推測に基づく情報や憶測を事実として報告してしまうと、誤った判断や混乱を招く可能性があります。
「~と思われる」「~かもしれない」といった推測表現を使う場合は、それが推測であることを明記し、事実と混同しないように注意しましょう。
例文:事実と推測が混同した悪い例
件名:[プロジェクト名]における[問題点]発生の可能性について
[担当者名]様
[問題点]が発生したと思われます。おそらく[原因]が原因でしょう。
このままでは、[影響]が及ぶ可能性があります。
早急に対策を講じる必要があります。
この例では、「思われます」「おそらく」といった推測に基づいた表現が多用されており、事実と推測の区別が曖昧です。
例文:事実と推測を区別した良い例
件名:[プロジェクト名]における[問題点]発生の可能性について
[担当者名]様
[プロジェクト名]において、[問題点]が発生したことを確認しました。
現時点では、[具体的な事実]が確認できており、[考えられる原因]は[推測される原因]です。
このまま放置すると、[影響]が及ぶ可能性があります。
現在、原因究明と対策立案を進めております。
こちらの例では、「確認しました」「現時点では」といった表現で事実を述べ、推測される原因は「[考えられる原因]は[推測される原因]」と明記することで区別しています。
専門用語や略語を多用しない
リスク報告メールは、プロジェクトに関わる全ての関係者が理解できる内容で作成する必要があります。
専門用語や業界特有の略語を多用すると、関係者間で認識の齟齬が生じる可能性があります。
専門用語や略語を使う場合は、注釈を加えたり、簡単な言葉で言い換えるなど、誰にでも理解できるような工夫をしましょう。
例文:専門用語を多用した悪い例
件名:[プロジェクト名]における[専門用語]の問題について
[担当者名]様
[プロジェクト名]で、[専門用語]に関する問題が発生しました。
[略語]の[数値]が規定値をオーバーしており、[専門用語]の調整が必要です。
早急な対応をお願いいたします。
この例では、専門用語や略語が多用され、内容を理解するのが困難です。
例文:専門用語を避けた良い例
件名:[プロジェクト名]における[問題点]について
[担当者名]様
[プロジェクト名]で、[問題点]が発生いたしました。
[具体的な数値]が基準値を超過しており、[対応策]が必要な状況です。
ご多忙中恐縮ですが、早急なご対応をお願いいたします。
この例では、専門用語を避け、分かりやすい言葉で説明しています。
報告内容の誤字脱字をなくす
リスク報告メールは、迅速な対応を求められる場面で利用されることが多いため、誤字脱字がないか十分な確認が必要です。
誤字脱字が多いメールは、内容の信頼性を損なうだけでなく、相手に不信感を与えてしまう可能性もあります。
送信前に必ず複数回のチェックを行い、正確な情報を伝えるように心がけましょう。
これらの注意点を守ることで、リスク報告メールの質が向上し、プロジェクトの円滑な進行に貢献することができます。
リスク報告を効率化するテンプレートの活用例

リスク報告は、プロジェクトを円滑に進める上で欠かせない業務です。
しかし、毎回ゼロからメールを作成するのは時間も手間もかかります。
そこで役立つのがテンプレートです。
テンプレートを活用することで、報告内容の品質を一定に保ちつつ、効率的にリスク情報を共有できます。
テンプレートの項目をカスタマイズする方法
テンプレートは、そのまま使うだけでなく、プロジェクトやチームの状況に合わせてカスタマイズすることが重要です。
ここでは、テンプレートの項目をどのようにカスタマイズするか、具体的な方法を解説します。
まず、基本的なテンプレートには、以下の項目が含まれていることが多いです。
- 件名: リスクの内容を簡潔に示す
- 宛先: 報告メールを送る関係者
- 報告者: 誰が報告しているかを明記
- 発生日: リスクが発生した日時
- リスク内容: 具体的に何が起こったか
- 影響範囲: プロジェクトへの影響度合い
- 対応状況: 現在までにとった対応
- 今後の対策: 今後の方針や計画
- 添付資料: 必要に応じて関連資料を添付
これらの項目を基本とし、プロジェクトの特性や、報告先のニーズに合わせて項目を追加・修正します。
例えば、大規模プロジェクトでは、リスクのカテゴリー(技術、スケジュール、コストなど)を分類する項目を追加すると、より整理された報告が可能です。
また、進捗状況を追跡するための項目を追加することで、リスク管理の効率を向上させることもできます。
例文:リスク報告テンプレート(カスタマイズ例)
件名:【[プロジェクト名]】[リスクカテゴリー]:[リスク内容]に関する報告
[プロジェクトマネージャー]様
関係者の皆様
お世話になっております。[報告者名]です。
[プロジェクト名]において、下記のリスクが発生いたしましたのでご報告いたします。
発生日:[発生日]
発生場所:[発生場所]
リスクカテゴリー:[リスクカテゴリー]
リスク内容:[リスク内容]
影響範囲:[影響範囲]
現在の対応状況:[対応状況]
今後の対策:[今後の対策]
添付資料:[添付資料名]
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
[報告者名]
この例文は、基本的な項目に加えて「発生場所」や「リスクカテゴリー」を追加した例です。
このように、必要に応じて項目を増減させることで、より実用的なテンプレートを作成できます。
リスク内容に合わせたテンプレートの使い分け
プロジェクトで発生するリスクは多岐にわたるため、リスク内容に合わせてテンプレートを使い分けることも効果的です。
例えば、技術的な問題、スケジュール遅延、予算超過など、異なるリスクに対してそれぞれ専用のテンプレートを用意します。
これにより、報告者は適切な項目を埋めるだけで、必要な情報を効率的に伝えられるようになります。
例えば、技術的な問題が発生した場合は、問題の詳細な説明、技術的な影響範囲、代替案などを記述する項目を設けます。
一方、スケジュール遅延に関する報告では、遅延の原因、スケジュールへの影響度、リカバリープランなどを詳細に記述する項目を設けるといった具合です。
例文:技術リスク報告テンプレート
件名:【[プロジェクト名]】技術リスク:[リスク内容]に関する報告
[プロジェクトマネージャー]様
関係者の皆様
お世話になっております。[報告者名]です。
[プロジェクト名]において、下記のような技術リスクが発生いたしました。
発生日:[発生日]
リスク内容:[リスク内容]
技術的な影響範囲:[技術的な影響範囲]
考えられる代替案:[代替案]
現在の対応状況:[対応状況]
今後の対策:[今後の対策]
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
[報告者名]
この例では、技術的なリスクに特化した項目を追加しています。
例文:スケジュール遅延報告テンプレート
件名:【[プロジェクト名]】スケジュール遅延に関するご報告
[プロジェクトマネージャー]様
関係者の皆様
お世話になっております。[報告者名]です。
[プロジェクト名]のスケジュールに遅延が発生しておりますのでご報告いたします。
発生日:[発生日]
遅延の原因:[遅延の原因]
スケジュールへの影響:[スケジュールへの影響]
リカバリープラン:[リカバリープラン]
今後の対策:[今後の対策]
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
[報告者名]
こちらはスケジュール遅延に特化したテンプレートです。
このようにリスクの種類に合わせてテンプレートを使い分けることで、より的確な情報伝達が可能となります。
テンプレート利用時の注意点
テンプレートは非常に便利なツールですが、利用する際にはいくつかの注意点があります。
- 形式的な報告にならないように注意する: テンプレートを使うことで、報告が形式的になりがちです。単に項目を埋めるだけでなく、リスクの状況や影響を具体的に記述することが重要です。
- 状況に合わせて柔軟に対応する: テンプレートはあくまでも基本であり、状況によっては項目を修正したり、追加情報を加えたりする必要があります。
- 定期的な見直しを行う: プロジェクトの進捗や状況に合わせて、テンプレートの内容を定期的に見直すことが重要です。古いテンプレートを使い続けると、実情に合わない報告になってしまう可能性があります。
テンプレートを効果的に活用することで、リスク報告の質を高め、プロジェクトの成功に繋げることができます。
しかし、テンプレートに頼りすぎず、状況に応じた柔軟な対応を心がけることが大切です。
『代筆さん』でリスク報告メールの作成を効率化
リスクの程度や影響範囲を的確に伝えることが重要だと分かっていても、読み手に誤解を与えず、かつ丁寧にまとめるのは簡単ではありません。
特に、件名や本文の構成を考えたり、言い回しに悩んだりと、文章を整える作業には意外と時間を要します。
そんな場面で心強い味方になってくれるのが、AIを活用したメール作成支援ツール『代筆さん』です。
『代筆さん』は、リスク報告メールを含むあらゆるビジネス文章を、目的や状況に応じて自然な日本語で提案してくれるWebサービスです。
日本語で簡単に指示を出すだけで、丁寧かつ的確な文章を瞬時に生成してくれるため、報告内容の精度を保ちながら、作成にかかる時間を大幅に削減できます。
また、定型文の登録や文体の切り替え機能も搭載されており、「急ぎだけど、丁寧さも欠かせない」といったビジネスシーンにも柔軟に対応可能です。
AIが作成した文章は、自分の目で確認・調整する必要がありますが、ゼロから考える手間が省ける分、内容の確認や表現の最終調整に集中できます。
『代筆さん』には無料プランがあり、有料プランも比較的リーズナブルなので、まずは気軽に使い心地を試してみてはいかがでしょうか。
プロジェクトリスク報告メールのように、正確さと配慮の両立が求められる場面でも、『代筆さん』が頼れる存在になるはずです。
まとめ:プロジェクトリスクを適切に共有し、トラブルを防ごう

プロジェクトリスクの報告は、迅速かつ客観的に状況を伝えることが、トラブル防止と成功への鍵です。
- リスクの内容を正確に把握し、関係者へ迅速に共有する
- リスク報告メールでは、事実に基づいた客観的な情報を記述する
- テンプレートを活用し、報告業務を効率化する
これらのポイントを踏まえ、リスク発生時にはまず落ち着いて、今回ご紹介した内容を参考にメールを作成してみてください。
もし、急ぎの対応が求められる中で、丁寧な言葉を考える余裕がないと感じることがあれば、ぜひ『代筆さん』の活用を検討してみてください。
プロジェクトリスクに関する状況説明や影響範囲の記述など、複雑な内容でも、目的に合わせて自然な文章をスムーズに整えてくれます。
迅速かつ正確な情報共有は、プロジェクトを成功に導くための重要な一歩です。
リスク発生時にも落ち着いて行動し、プロジェクトを前向きに進めていきましょう。
AIメール作成ツールでプロ級のビジネスメールを、たった数秒で作成!
AIメール作成ツール「代筆さん」で、面倒なメール作成から解放されませんか?
時間節約、品質向上、ストレス軽減 すべてを一度に実現します。
- 適切な言葉遣いと構成で、印象アップ
- ビジネスシーンに応じた多彩なテンプレート
- AIメール作成ツールによる文章の自動校正と改善提案
