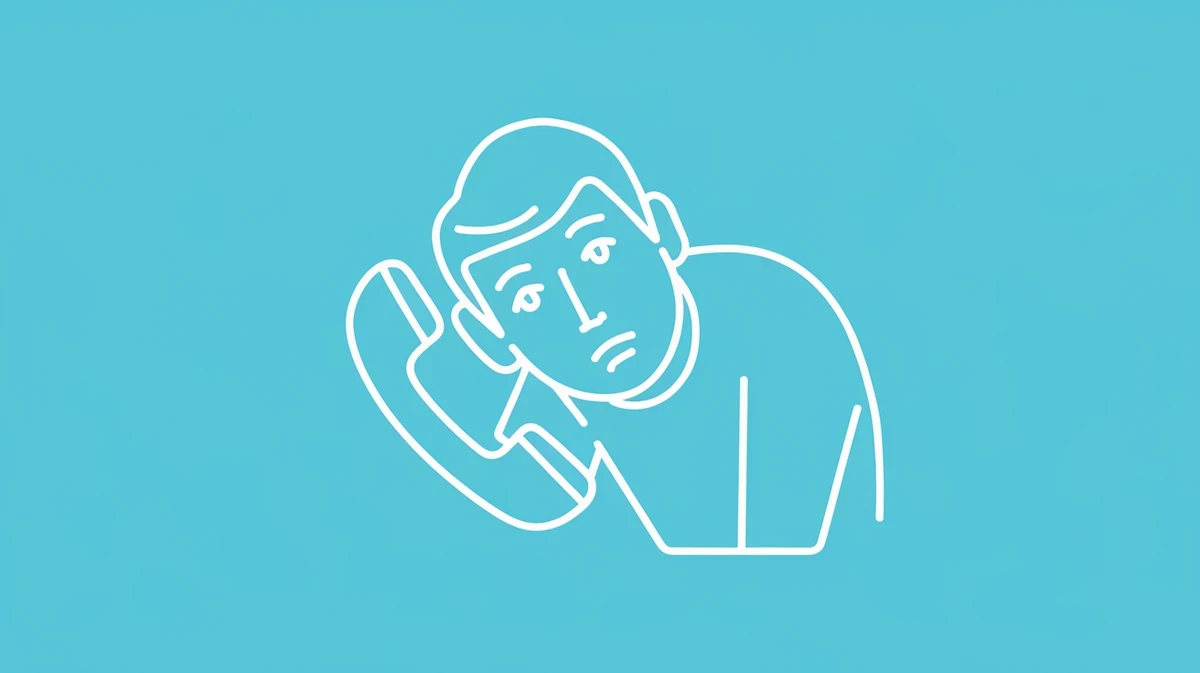
クレーム対応で差をつける!最強の話し方テクニックで顧客満足度を劇的アップ
 AIメール作成ツール 代筆さん
2025-07-19
AIメール作成ツール 代筆さん
2025-07-19
「お客様からのクレーム、どう対応したらいいか分からなくて、いつも憂鬱…」
そんな悩みを抱えていませんか?
実は私も、以前はクレーム対応が本当に苦手でした。
電話が鳴るたびにドキドキしたり、相手の剣幕に圧倒されてしまったり…。
でも、ある「話し方」のコツを知ってから、クレーム対応への考え方がガラッと変わったんです。
今回は、あなたも自信を持ってクレーム対応できるようになる、最強の話し方テクニックをご紹介します。
なぜクレーム対応で「話し方」が重要なのか?

クレーム対応は、とても神経を使う非常に大変な業務です。
できれば避けたい…と思うのが正直な気持ちかもしれません。
でも、実はクレーム対応こそ、企業の真価が問われる場面なんです。
そして、その成否を大きく左右するのが「話し方」です。
第一印象でその後の展開が決まる
クレームを伝えてくるお客様は、何かしらの不満や怒りを感じています。
その最初のコンタクトで、あなたがどんな話し方をするか。
それが、その後の対応全体の流れを決めると言っても過言ではありません。
ぶっきらぼうな話し方や、面倒くさそうな態度は、火に油を注ぐようなものです。
反対に、丁寧で落ち着いた話し方は、お客様の興奮を少しずつ鎮める効果があります。
まさに「はじめが肝心」なんですね。
言葉一つで相手の感情は大きく変わる
「言葉は刃物にもなる」と言いますが、クレーム対応では特にそのことを意識する必要があります。
不用意な一言が、お客様の怒りを増幅させてしまうことも少なくありません。
例えば、「それはお客様の勘違いでは?」なんて言ってしまうと、相手はカチンときますよね。
一方で、「ご不快な思いをさせてしまい、申し訳ございません」という一言があるだけで、お客様は「話を聞いてくれそうだ」と感じるかもしれません。
使う言葉を選ぶだけで、相手の心証は大きく変わります。
信頼回復への第一歩は「聞く姿勢」から
クレーム対応の目的は、単に問題を解決するだけではありません。
失いかけたお客様の信頼を取り戻す、あるいは、さらに強い信頼関係を築くチャンスでもあります。
そのために最も大切なのが、「あなたの話をきちんと聞いていますよ」という姿勢を示すことです。
真摯に耳を傾ける話し方は、お客様に「この人は自分の状況を理解しようとしてくれている」と感じさせます。
これが信頼回復への第一歩になるのです。
日本のビジネス文化と丁寧な言葉遣い
日本のビジネスシーンでは、特に丁寧な言葉遣いや敬語が重視されますよね。
クレーム対応の場面では、その重要性がさらに増します。
正しい敬語を使えているか、相手に失礼な印象を与えていないか、不安になることもあるかもしれません。
しかし、過度に堅苦しくなる必要はありません。
大切なのは、相手への敬意を払い、誠実に対応しようとする気持ちを「話し方」で示すことです。
少し意識するだけで、あなたの対応は格段に良くなるはずですよ。
クレーム対応・最強の話し方 5つのステップ
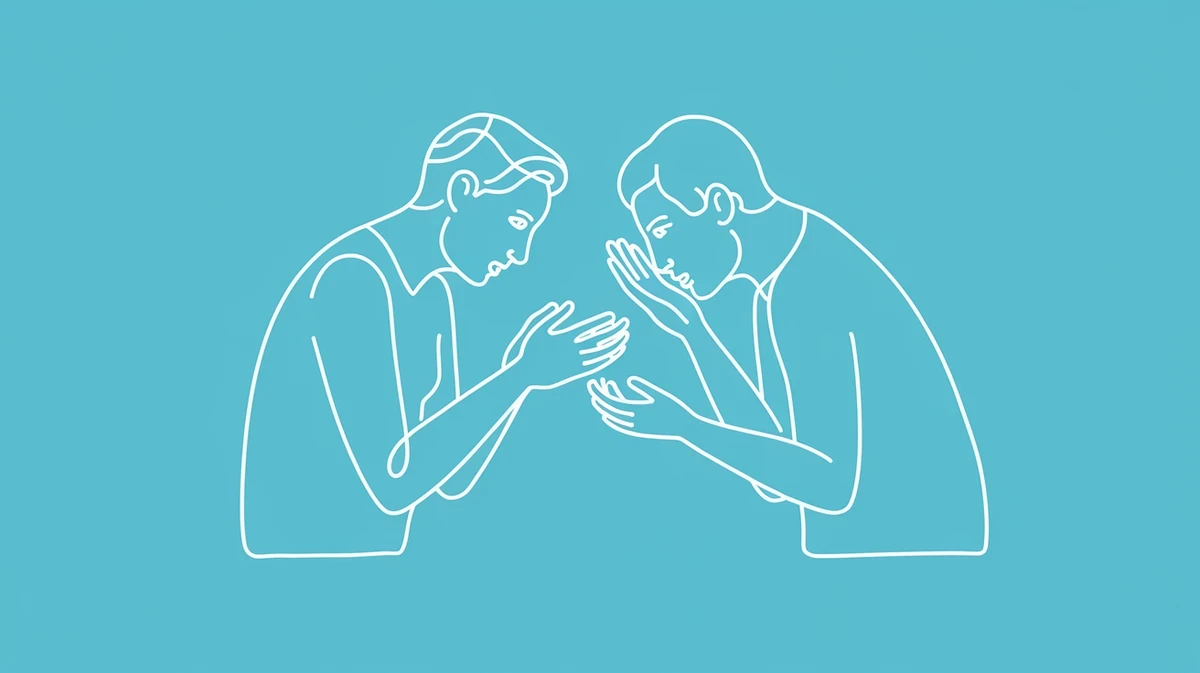
では、具体的にどのように話せば良いのでしょうか?
クレーム対応をスムーズに進めるための「最強の話し方」を、5つのステップに分けてご紹介します。
この流れを意識するだけで、きっと落ち着いて対応できるようになりますよ。
ステップ1:まずは徹底的に「聞く」 - 傾聴の重要性
お客様が話し始めたら、まずは最後まで、じっくりと話を聞くことに集中しましょう。
これがクレーム対応の基本中の基本、「傾聴」です。
相手が何に怒り、何を求めているのかを正確に理解することが目的です。
相槌とうなずきで聞いている姿勢を示す
相手の話に合わせて、「はい」「ええ」といった短い相槌を打ちましょう。
電話であれば、時折「さようでございますか」といった言葉を挟むのも良いですね。
対面であれば、軽くうなずきながら聞くことで、「あなたの話を真剣に聞いています」というメッセージが伝わります。
ただし、大げさな相槌や頻繁すぎるうなずきは、かえって不誠実な印象を与える可能性があるので注意が必要です。
相手の話を遮らない
お客様が感情的になっていると、つい口を挟みたくなってしまうかもしれません。
しかし、そこはぐっとこらえましょう。
相手が話している途中で遮ってしまうと、「話を聞く気がないのか!」と、さらに怒りを買ってしまう可能性があります。
言いたいことがあっても、まずは相手が話し終えるのを待つことが大切です。
メモを取りながら事実を整理する
お客様の話を聞きながら、重要なポイントをメモに取りましょう。
「いつ」「どこで」「何があったのか」といった具体的な情報を記録することで、後で事実確認をする際に役立ちます。
また、メモを取る姿勢は、相手に「きちんと対応しようとしてくれている」という印象を与える効果もあります。
電話対応であれば、「恐れ入ります、念のためメモを取らせていただいてもよろしいでしょうか?」と一言断ると、より丁寧です。
ステップ2:相手の気持ちに寄り添う - 共感の言葉
お客様の話を一通り聞いたら、次はその気持ちに寄り添う言葉を伝えましょう。
問題解決の前に、まずは相手の感情を受け止めることが重要です。
「お気持ちお察しします」「ご不便をおかけし申し訳ありません」
お客様が感じている不満や怒りに対して、理解を示す言葉を伝えます。
「そのようなことがあり、大変ご不快な思いをされたことと存じます。誠に申し訳ございません」
「〇〇の件でご不便をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます」
こうした共感の言葉は、お客様の心を和らげる効果があります。
ただし、事実確認が済んでいない段階での安易な謝罪は避け、あくまで「お客様の気持ち」に対して寄り添う姿勢を示すことがポイントです。
オウム返しで理解を示す
お客様が訴えた内容の一部を繰り返す、「オウム返し」も有効なテクニックです。
例えば、「〇〇ができなくて、本当に困った」と言われたら、「〇〇ができず、大変お困りになったのですね」と返すイメージです。
これは、相手の話を正確に理解していることを示すとともに、「ちゃんと聞いてくれている」という安心感を与えることができます。
感情的な言葉を受け止める(ただし同意ではない)
お客様が感情的な言葉を使ったとしても、冷静に受け止めましょう。
「〇〇なんて、ひどいじゃないか!」と言われた場合でも、「ひどい、とお感じになられたのですね」というように、相手の感情表現をそのまま受け止める形で返します。
これは、相手の感情に「同意」するのではなく、あくまで「そういう風に感じているのですね」と認識していることを示すものです。
感情に感情で返さないことが、冷静な対応の秘訣です。
ステップ3:冷静に事実を確認する - 質問の技術
共感を示し、お客様が少し落ち着いてきたら、次は問題の事実確認を進めます。
ここで大切なのは、客観的かつ具体的に情報を集めるための「質問力」です。
「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」「どのように」
いわゆる「5W1H」を意識して質問することで、状況を正確に把握することができます。
「恐れ入ります、もう少し詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか。そちらの件は、いつ頃のことでしょうか?」
「差し支えなければ、どちらの店舗での出来事か教えていただけますでしょうか?」
というように、具体的で分かりやすい質問を心がけましょう。
オープン・クエスチョンとクローズド・クエスチョンを使い分ける
質問には、相手に自由に答えてもらう「オープン・クエスチョン」(例:「その時の状況を詳しく教えていただけますか?」)と、「はい」か「いいえ」で答えられる「クローズド・クエスチョン」(例:「〇〇はお試しいただけましたでしょうか?」)があります。
状況に応じてこれらを使い分けることで、効率的に情報を収集できます。
最初はオープン・クエスチョンで全体像を掴み、具体的な点を確認する際にクローズド・クエスチョンを使う、といった流れが一般的です。
推測ではなく事実ベースで話を進める
事実確認の段階では、憶測や推測で話を進めないことが重要です。
「おそらく〇〇だったのではないでしょうか?」といった曖昧な言い方は避け、「〇〇ということでよろしいでしょうか?」と、一つ一つ丁寧に確認を取りながら進めましょう。
もし不明な点があれば、「確認いたしますので、少々お待ちいただけますでしょうか」と正直に伝え、正確な情報に基づいて対応することが信頼につながります。
ステップ4:誠意をもって謝罪する - 謝罪のポイント
事実確認の結果、自社に非があることが明確になった場合は、誠意をもって謝罪します。
謝罪の仕方一つで、お客様の受け止め方は大きく変わります。
何に対して謝罪するのかを明確にする
漠然と「申し訳ありません」と繰り返すのではなく、「何に対して」謝罪しているのかを具体的に伝えましょう。
「この度は、私どもの製品の不具合により、〇〇様にご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます」
「スタッフの不手際により、お客様にご不快な思いをさせてしまいましたこと、誠に申し訳ございませんでした」
このように、謝罪の対象を明確にすることで、誠意が伝わりやすくなります。
安易な全面謝罪は避ける(場合による)
明らかに自社に非がある場合は別ですが、事実関係がはっきりしない段階や、お客様の要求が過大である場合に、安易に「すべて当社の責任です」といった全面的な謝罪をするのは避けるべきです。
まずは、「ご不快な思いをさせてしまったこと」や「ご迷惑をおかけしている状況」に対して謝罪し、事実確認を進める中で、責任の所在に応じた適切な謝罪を行うことが重要です。
改善への意志を示す
謝罪と合わせて、今後の改善に向けた意志を示すことも大切です。
「今回の件を真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります」
「ご指摘いただいた点を改善し、よりご満足いただけるよう努めてまいります」
こうした言葉は、お客様に「この会社はちゃんと考えてくれているんだな」という印象を与え、信頼回復につながることがあります。
ステップ5:具体的な解決策を提示する - 提案力
最後に、お客様が抱えている問題を解決するための具体的な方法を提示します。
ここでの「提案力」が、クレーム対応のゴールを左右します。
できること、できないことを明確に伝える
お客様の要求に対して、会社として対応できる範囲と、できない範囲を正直に、かつ明確に伝える必要があります。
期待を持たせるような曖昧な言い方は避け、「〇〇については対応可能ですが、△△については申し訳ございませんが対応いたしかねます」といった形で、はっきりと伝えましょう。
できない理由も、可能な範囲で丁寧に説明することが大切です。
代替案を提示する柔軟性
お客様の要求に完全に応えられない場合でも、それで終わりではありません。
「〇〇はできかねますが、代わりに△△という方法はいかがでしょうか?」といった代替案を提示することで、解決に向けて努力している姿勢を示すことができます。
少しでもお客様の不満を解消できるよう、柔軟な発想で代替案を考えることが重要です。
期限や今後の流れを説明する
解決策を提示する際には、それがいつまでに実施されるのか、今後の手続きはどうなるのか、といった具体的なスケジュールや流れも合わせて説明しましょう。
「〇〇につきましては、3営業日以内に改めてご連絡いたします」
「交換品は、明日発送の手配をいたします」
具体的な見通しを示すことで、お客様は安心感を得ることができます。
さらに効果を高める!話し方の応用テクニック

基本的な5つのステップに加えて、さらにクレーム対応の効果を高めるための応用テクニックをいくつかご紹介します。
ちょっとした工夫で、お客様の印象は大きく変わりますよ。
クッション言葉で柔らかい印象に
本題に入る前や、相手にとって聞き入れにくいことを伝える際に、「クッション言葉」を挟むと、表現が和らぎ、丁寧な印象を与えることができます。
これは日本のビジネスコミュニケーションでは特に有効です。
「恐れ入りますが」「申し訳ございませんが」「差し支えなければ」
これらの言葉を枕詞として使うことで、唐突な印象を避けることができます。
「恐れ入りますが、もう少し詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか?」
「申し訳ございませんが、そちらのご要望にはお応えいたしかねます」
「差し支えなければ、お客様のお名前とご連絡先を伺ってもよろしいでしょうか?」
これらの言葉を自然に使えるようになると、コミュニケーションがよりスムーズになります。
ミラーリングで親近感を演出
ミラーリングとは、相手の話し方や仕草をさりげなく真似る心理学的なテクニックです。
人は自分と似ている人に好感を抱きやすい傾向があるため、これを利用します。
相手の言葉遣いや話すペースに合わせる(やりすぎ注意)
相手がゆっくり話すタイプならこちらも少しペースを落とす、相手が丁寧な言葉遣いならこちらも丁寧に対応するなど、相手のペースや雰囲気に合わせることを意識します。
ただし、露骨に真似しすぎると、かえって不快感を与えたり、馬鹿にしているように受け取られたりする恐れがあります。
バランスを見極めながら、あくまで「さりげなく」行うのがポイントです。
ポジティブ・リフレーミングで視点を変える
ポジティブ・リフレーミングとは、物事の否定的な側面を肯定的な側面から捉え直すことです。
クレーム対応においても、ネガティブな状況を少しでも前向きな方向に転換するのに役立ちます。
否定的な言葉を肯定的な表現に言い換える
例えば、「〇〇ができない」と伝える代わりに、「〇〇は難しいのですが、△△であれば可能です」といった形で、できることに焦点を当てるような言い換えをします。
「問題点」を指摘された際には、「貴重なご意見として、今後の改善に活かしてまいります」と伝えることで、前向きな姿勢を示すことができます。
ただし、お客様の不満を軽視していると受け取られないよう、注意が必要です。
声のトーンとスピードを意識する
話す内容だけでなく、「声」そのものが与える印象も非常に重要です。
特に電話対応では、声だけが頼りになります。
落ち着いた、やや低めのトーン
クレーム対応では、興奮したり慌てたりせず、常に落ち着いたトーンで話すことを心がけましょう。
一般的に、やや低めの声のトーンは、相手に安心感や信頼感を与えやすいと言われています。
甲高い声や早口は、焦っているような、あるいは軽率な印象を与えかねません。
早口にならないよう、ゆっくり話す
お客様が興奮していると、こちらもつられて早口になってしまいがちです。
しかし、意識してゆっくり、はっきりと話すことで、冷静さを保ち、相手にも落ち着きを取り戻してもらう効果が期待できます。
また、ゆっくり話すことで、伝えたい内容がより正確に伝わりやすくなります。
これはNG!避けるべきクレーム対応の話し方

良かれと思って言った言葉が、逆効果になってしまうこともあります。
ここでは、クレーム対応で絶対に避けるべきNGな話し方や態度をいくつかご紹介します。
うっかり使ってしまわないように、しっかり覚えておきましょう。
- 感情的な反論や言い訳: お客様の言葉にカッとなって反論したり、「それは仕方なかったんです」といった言い訳をしたりするのは最悪です。火に油を注ぐだけです。冷静さを保ちましょう。
- 責任転嫁するような言葉: 「それは私の担当ではありません」「〇〇部署の問題です」など、責任を他の人や部署に押し付けるような言い方は、お客様をさらに失望させます。まずは窓口として受け止め、責任をもって対応する姿勢が大切です。
- 専門用語や難しい言葉の多用: お客様に状況を理解してもらおうとして、つい専門用語や社内用語を使ってしまうことがありますが、これは避けるべきです。相手に伝わらなければ意味がありませんし、場合によっては見下しているような印象を与えかねません。誰にでもわかる平易な言葉で説明しましょう。
- 上から目線の態度や言葉遣い: たとえお客様の言い分に理不尽な点があったとしても、決して上から目線で諭したり、馬鹿にしたりするような態度は取ってはいけません。常に敬意を払い、対等な立場で接することを心がけましょう。
- 「でも」「だって」「ですから」の連発: これらの接続詞は、言い訳がましく聞こえたり、相手の話を否定しているように受け取られたりしやすい言葉です。多用すると、お客様の反感を買いやすくなります。なるべく使わないように意識しましょう。
これらのNGな話し方を避けるだけでも、クレーム対応はずっとスムーズに進むはずです。
クレーム対応の文章作成を効率化する方法

最近は、電話だけでなく、メールやチャットでのクレーム対応も増えていますよね。
顔が見えない分、文章でのコミュニケーションは、より丁寧さや正確さが求められます。
メールやチャットでのクレーム対応の難しさ
文章でのやり取りは、声のトーンや表情が伝わらないため、誤解が生じやすいという側面があります。
ちょっとした言葉遣いの違いで、冷たい印象を与えてしまったり、誠意が伝わらなかったりすることも。
また、状況に合わせて適切な表現を選ぶのは、意外と時間がかかるものです。
定型文だけでは伝わらない誠意
もちろん、よくある問い合わせに対して定型文を用意しておくことは効率化につながります。
しかし、クレームの内容は千差万別。
定型文をそのまま送るだけでは、紋切り型で誠意がない、と感じられてしまう可能性が高いです。
お客様一人ひとりの状況に合わせた、心のこもった文章を作成する必要があります。
AIがサポートする文章作成
「毎回、適切な文章を考えるのが大変…」
そんな悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、こうした文章作成の負担を軽減するのに、AIの技術が役立つことがあります。
簡単な指示や要点を伝えるだけで、AIが状況に応じた丁寧なビジネスメールやチャットの返信文案を作成してくれるサービスが登場しています。
状況に応じた適切な表現選びのサポート
AIは、膨大な言語データを学習しているため、クレームの深刻度や相手の感情に合わせた、適切な言葉遣いや表現を選ぶ手助けをしてくれます。
例えば、「謝罪の気持ちを強く伝えたい」「代替案を丁寧に提案したい」といった意図を伝えるだけで、それに沿った文章の候補を複数提示してくれることもあります。
もちろん、AIが作成した文章をそのまま使うのではなく、最終的には人間が内容を確認し、必要に応じて修正を加えることが重要です。
しかし、文章作成の「下書き」や「たたき台」としてAIを活用することで、時間短縮や表現の質の向上につながる可能性があります。
特に、日本のビジネスシーン特有の丁寧な言い回しや敬語の使い方に自信がない場合などにも、参考になるでしょう。
クレーム対応に役立つ文章作成ツール『代筆さん』
こうしたAIによる文章作成支援サービスのひとつとして、『代筆さん』をご紹介します。
『代筆さん』は、クレーム対応やお詫びメールといった繊細なやりとりにも対応できる、ビジネス文書の作成に特化したAIツールです。
「謝罪を丁寧に伝えたい」「相手に寄り添った表現にしたい」「感情的にならずに冷静に対応したい」といった要望をもとに、状況に応じた適切な文章を瞬時に生成してくれます。
例えば、チャットでの即時返信が求められる場面や、同様のクレーム対応が複数発生しているようなケースでも、ニュアンスの異なる文案を複数提案してくれるため、機械的な印象を与えず、対応品質を保ったまま業務の効率化が図れます。
また、社内の対応方針や商品情報をあらかじめ登録しておくことで、それに沿った内容で文章を自動作成できる点も実務で非常に便利です。
敬語や言い回しのチェック機能もあり、文章作成に自信がない方でも安心して利用できます。
『代筆さん』には、すぐに使える無料プランが用意されており、まずは気軽に試してみることができます。
さらに、より多くの文案提案や便利機能を使いたい方向けには、比較的リーズナブルな有料プランも用意されているので、コストを抑えて導入できる点も魅力です。
クレーム対応における「文章の負担」を軽減したい方は、ぜひ一度『代筆さん』の活用をご検討ください。
まとめ:最強の話し方を身につけて、クレームをチャンスに変えよう

クレーム対応における「最強の話し方」は、決して相手を言い負かすためのテクニックではありません。
相手の話を真摯に聞き、気持ちに寄り添い、誠意をもって問題解決にあたる一連のプロセスを、言葉を通じて丁寧に進めていくためのスキルです。
最初は難しく感じるかもしれませんが、クレーム対応は経験と練習によって必ず上達します。
今回ご紹介した「傾聴」「共感」「事実確認」「謝罪」「解決策提示」という5つのステップと、応用テクニックを意識して実践してみてください。
そして、NGな話し方を避けるだけでも、あなたのクレーム対応は格段に向上するはずです。
冷静かつ誠実な対応を心がけることで、お客様の怒りを信頼に変え、ピンチをチャンスに変えることだってできるのです。
もし、メールやチャットでの丁寧な文章表現に迷う場面があれば、AIを活用したツールも選択肢の一つです。
例えば、AIメール作成支援ツール『代筆さん』は、簡単な指示で状況に応じた適切な文章を作成する手助けになります。
ぜひ、今日から「最強の話し方」を意識して、自信を持ってお客様と向き合ってみましょう。
あなたの誠実な対応が、お客様の満足と企業の信頼につながることを願っています。
今すぐAIでメールを作成してみよう!
伝えたいことを入力するだけで、プロ級のビジネスメールが完成します
